今、子どもが「ディベート教育」を学ぶべき理由 「⽴論グランプリ2020」、トップ校の熱い戦い
今回、「立論グランプリ」を主催した全国教室ディベート連盟は1996年に発足して(2004年からNPO法人に認可)以来、教室ディベートの教材・指導法の開発や全国各地でのディベート講習会の開催、そして「ディベート甲子園」(読売新聞社との共同開催)などの活動を行ってきた。一から組織の立ち上げに携わってきた藤川氏は、団体設立の経緯についてこう語る。
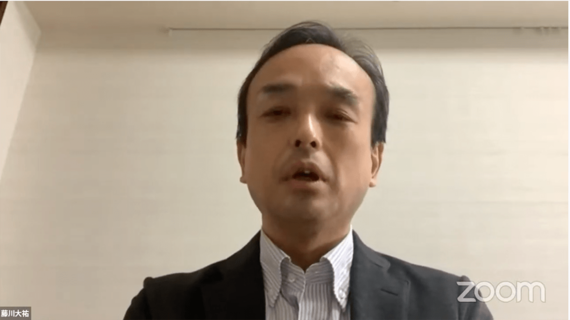
日本におけるディベート教育の幕開け
「90年代から日本の教育現場でも討論や話し合いの重要性が問われてきましたが、実際の授業では特別な能力を持った名人のような先生が教えるのみで、一般にどのようにディベート的な授業を広げていけばいいのか、なかなか有効な手立てがありませんでした。そこで私も参加していた教職員や研究者らの勉強会である『授業づくりネットワーク』を母体に教育者向けのディベート講座を立ち上げ、自分たちも教育法を学びながら、団体をつくり、ディベート大会も行うようになったのです」
団体設立時、藤川氏は30歳で大学講師になったばかり。その頃、活発な討論が行われる多様性を尊重した授業はあったものの、多くの授業は先生が一方的に教えるのみ。現状の学校の授業のあり方を変えたい、新しい教育をつくりたいという問題意識があった。
「ディベートに対する機運が盛り上がる中で、日本のディベート教育を発展させたいという熱い気持ちを持った仲間たちが集まりました。当時、東大助手で、その後エンジェル投資家として活躍し、『僕は君たちに武器を配りたい』などビジネス書のベストセラー作家でもあった故・瀧本哲史さんも支援してくれた一人です。そうした皆さんのおかげでディベート甲子園も団体設立の初年度からスタートし、多くの学校の参加がかないました。
以来、25年近く経ちましたが、これまで続けてこられたのも大会に参加したOB・OGたちが協力してくれたおかげだと考えています。今では運営スタッフのほとんどがOB・OGで、弁護士や医者、研究者など各界で活躍している方々も多く、年を重ねるごとに彼らの熱意ある支援もあって、充実したディベート大会が実現できるようになっています」
本来なら2020年の「ディベート甲子園」は25年目の記念となる大会になるはずだったが、コロナ禍で中止を余儀なくされ、代わって「立論グランプリ」を開催することとなった。
「ディベートの基礎として重要な部分である“立論”は、青年の主張のような単純なスピーチではありません。立場の違う相手がいる中で、批判的な見方を考慮に入れつつ、自分たちの主張を限られた時間の中で伝えていく。その意味で、“立論”は今求められる問題解決能力の基礎となるクリティカルシンキングを身に付けることにもつながっていくものなのです。今回、“立論”に集中したことで、これまでの大会の中でも、より議論を整理することができた。今後のディベート大会でも今回の経験が生かされていくだろうと考えています」






























