中2全員「iPad授業」、学び続ける子を育てるコツ 「授業と関係ない動画」を見ても注意しない訳
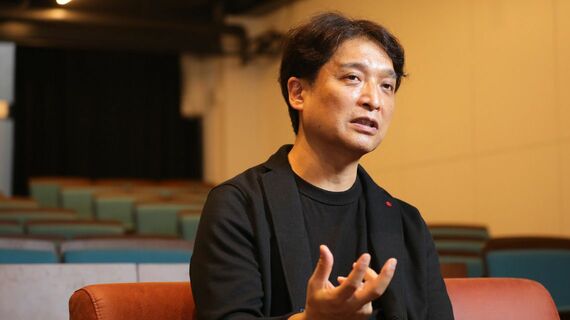
新渡戸文化小中高等学校統括校長補佐・横浜創英中学高等学校教育アドバイザー。 教員のほか、日本パブリックリレーションズ研究所主任研究員、Weblio教育アドバイザー、ゲイトCSR教育デザイナーなど複数の学校・企業でも活動する“兼業教師”。東京都立中高一貫教育校を経て2019年度より現職。「教えない授業」と呼ばれる自律型学習者を育てる授業を実践している。検定教科書『NEW CROWN ENGLISH SERIES』(三省堂)の編集委員を務めるほか、著書に『なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか』(日経BP社)など
授業から評価法の模索までICTの活用が進んでいる同学園では、オンラインとオフラインの生かし方も見えてきたという。
「リアルタイムで人とつながるにはオンラインが便利。個別最適化学習のほか、作画や作曲、クイズ作りなどのクリエーション活動もICTが活躍します。一方、課題解決型の授業のような非認知スキルが重要となるものは対面がよいと思っています」と、山本氏。
今後もコミュニケーションの手段としての英語を意識させる活動に重点を置き、対面とICTを掛け合わせたハイブリッドの形で授業を行う方針だという。そして、こう語った。
「日本は子どもに多くのものを与え続け、主体性を奪ってきました。企業が時短や働き方改革をしているのに、学校だけが授業時数や課題を増やし続けています。学校を社会につなげるためにも、やることを増やして数値のところで競い合っていてはいけない。授業数を減らして子どもたちの主体性が上がっていけば、学力向上などの成果につながっていく。そんな学校事例がどんどん出てくるべき。日本中の子どもたちが『できないことは可能性』だと感じ、学ぶことの喜びを感じてほしい。教育現場に生徒自身がデザインする余白の時間をつくるという、これまでと逆の価値観を取り入れていくことで、公立・私立を問わず、よい方向に向かうといいなと思っています」
(文:編集チーム 佐藤ちひろ、撮影:今井康一)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























