プログラミングで日本が挽回するカギは「教員」 STEAM教育が目指すのは「主体性」の獲得
日本の教育レベルが高いのは教員のおかげ
プログラミングに対する熱は教員によって大きく異なり、やる気のない教員も一定数いる。そんなとき、最も効果的なのは子どもの反応を伝えることだと利根川氏は明かす。
「校長がいくら言っても自分ごと化できない教員でも、『じっと座っていられないあの〇〇君が45分間集中できた』といった児童の反応を聞くと、一気にモチベーションが上がります。GIGAスクール構想※2で『1人1台PC』が実現すれば、これまで及び腰だった教員も動き出すでしょうから、一気にプログラミング教育が深まる可能性もあるのではないでしょうか」
教員自らプログラミングを学び、部首の仕組みが理解できる漢字シューティングゲームをつくって成果をあげている教員もいる。各地で成功事例も出てきているが、これはプログラミングという分野に精通しているから成し遂げられたのではなく、もともとの授業開発力が高いからだと前出の石戸氏は指摘する。
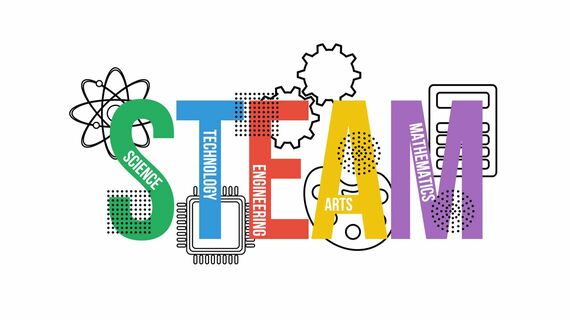
「プログラミング教育やSTEAM教育の推進という点で、日本が世界から遅れているのは事実です。では教育そのもののレベルはどうかといえば、少なくとも初等・中等教育における理数教育は、PISA※3でも相当高い水準に到達していることが証明されています。さらに、図工や音楽といったSTEAMのA(Art)の部分をこれだけしっかり教育している国はそれほど多くありません。だからこそ高度成長を成し遂げ、経済大国にもなったわけです。その要因は、日本の教員のレベルが極めて高く、情熱的に子どもたちへ学びを提供してきたことにあります。その優秀さを生かせば、Society5.0時代でも、世界に誇れる教育へとシフトできることは間違いありません」
では、具体的にどうやってシフトチェンジを成功させるのか。後編では、日本人女性初の数学オリンピック金メダリストでジャズピアニストの中島さち子氏に、海外でのSTEAM教育の現状を紹介してもらいながら、今後の教育のあるべき姿をさらに探っていきたい。
(注記のない写真はiStock)
※3 PISA:Programme for International Student Assessmentの略。OECD加盟国で実施される15歳を対象とした国際的な学習到達度テストで、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野の習熟度を調査する。最新の2018年度調査で日本は読解力が8位、数学的リテラシーが5位、科学的リテラシーは2位だった
制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































