こうした中、返礼品供給力の行き過ぎた量的・質的強化が、悪質な不正につながるケースも出てきている。今年6月から2年間のふるさと納税の指定取り消しという憂き目に遭った2自治体の事例を見ていこう。
1例目は、不正で最も多い返礼品の産地偽装が今年3月に発覚した長野県須坂市だ。
市では、契約する中間業者が6年間にわたって返礼品のシャインマスカットを他地域からも調達しており、その量はときに年10トンを超えていた。発覚後に長野県が県下自治体の実態調査を行うと、さらにいくつもの産地偽装問題が明らかになった。それらの不正の理由は、報道などによれば、①業者からの書面の確認や聞き取りしかしていなかった、②当初確認後の再確認はしなかった、③業者の事実誤認があった、というものだった。
ここからわかるのは、不正には悪意によるものと不注意によるものがあり、外部から認識、識別するのが容易ではないということだ。調査には専門性が必要となる。
自治体の自制には期待できない
また報道によると、不正のあった長野市と中野市が取引をする返礼品取扱業者の数は、ふるさと納税の担当職員1人あたり130~140社に上っていた。これでは職員による確認作業に限界が出てくる。ならば自治体が、品数や取引業者を減らすべきだとの指摘もあるだろうが、それをしていたのでは他自治体にパイを奪われてしまう。ゆえに自治体がルール順守のために自主的な規模縮小を行うことはなかなかあり得ない、と考えた方がいい。

2例目は岡山県吉備中央町の事例だ。返礼品調達額はふるさと納税額の3割以内という「3割ルール」に抵触した。

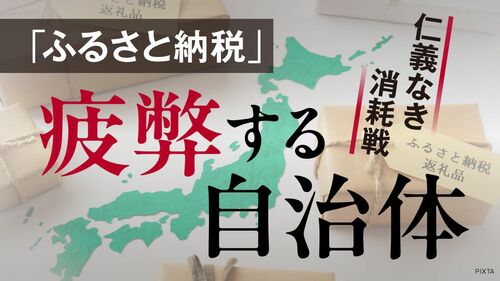































無料会員登録はこちら
ログインはこちら