資産を相続できない?突然死による「デジタル遺品トラブル」、企業は業務ストップや裁判沙汰のリスクも!正しい対策と専門事業者の選び方
その企業の担当者は、悪意があってデータを消去したのではなく、パソコンの使用がない状況が一定期間以上経過した時点でデータを消すというルールに従っただけのことだと説明したそうだ。
「しかし遺族からすれば、長時間労働やパワハラなどの証拠隠滅のためにデータを消去したのではないかと疑念を抱くのも無理はないことです」
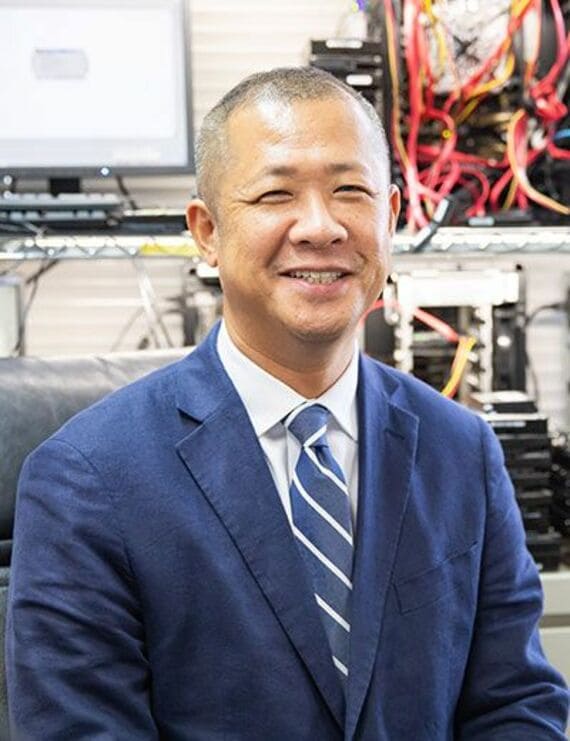
下垣内氏によれば、今は多くの大手企業が情報漏洩を気にするあまり、不要になったデータは速やかに消去するというルールが設けられているという。
しかし、一度消したデータを復元するのは容易なことではない。上記のような遺族とのトラブル以外にも、データの消去により、亡くなった社員と取引先との重要な交渉履歴が失われたり、退職した社員が不正を行っていた際に追跡調査を行うことが困難になったりといったことが起こり得る。
「企業は“消すべき情報”と“残すべき情報”のルール設定を、再検討すべきだと思います」
企業にとってデジタル遺品対策は、一種のBCP(事業継続計画)と位置づけることができる。大規模な自然災害や事故はめったに起きないが、発生すれば企業の事業継続に深刻な影響をもたらす。だからBCPが必要になる。
「従業員が突然いなくなるケースも同様に、BCPの意識で対応したほうがいい」と下垣内氏は言う。サイバー攻撃等が相次ぐ中、企業は情報漏洩への対策に追われがちだが、「従業員の突然の死や退職」で生じうるデジタル遺品に関するBCPについても、目を向ける必要がある。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら