今や錦の御旗となった「実質賃金の上昇」の残念感 抽象的すぎるフレーズ、実現の経路は複雑怪奇
日本の自動車企業を中心に、極限の効率化を経て投入を減らす傍らで産出を維持してきたことはよく知られる。製品やサービスではなく、生産・流通過程を改善することで日本企業が成長してきたとの議論は有名であり、いわゆるプロセスイノベーションと呼ばれる。
これに対し、産出を増やすことは不得手だともいわれてきた。産出の増大には技術革新を通じた新製品の誕生(スマートフォン、EV、ドローンなど)が想定される。こうしたいわゆるプロダクトイノベーションによって投入対比で産出を増やすことができれば生産性は上昇する。
マクロとミクロの中間にある論点であり、政治家や官僚やエコノミストのようなマクロ分析を担当する立場からは芯を食った情報発信が難しい現実がある。「技術革新が必要」という意見は正しいが、もちろん、それだけで現実が変わるほど甘い状況ではない。
経路が複雑すぎて政策目標にはならない
かくいう筆者も、実質賃金上昇に対して妙手を提案できるわけではない。しかし、少なくとも以上の議論を踏まえれば「実質賃金の上昇」を政策目標として持ち込んでも、これを実現するための経路は複雑怪奇であり、単純ではないことはわかっていただけるだろう。
「手取りの増加」という言い方にとどめているうちは、社会保障費など控除項目の規模を抑制していくことで実現可能かもしれない。だが、「物価の上昇を上回る所得向上」、すなわち実質賃金の上昇を明言してしまうと、そこに至るまでのルートが多岐に渡る。
ただでさえ政府の行う政策にタイムラグ(認知、実行、効果発現)が伴う中、壮大で抽象的な目標設定は結局、形骸化して終わる公算が非常に大きいといわざるをえない。
「実質賃金の上昇」という目標を掲げて反対する向きはいないだろう。しかし、あまりに抽象的なのである。これは過去30年余り、惰性で使用され続け、今や矛盾が指摘されるようになった「デフレ脱却」と同じ雰囲気を感じる。
より具体的な政策論に落とし込んだうえで政策を執行する姿勢が求められている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































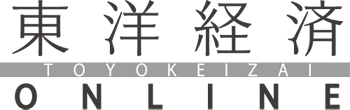


無料会員登録はこちら
ログインはこちら