大空小の初代校長・木村泰子、予測不能な社会生きる子どもに必要な「4つの力」 学力や他者評価で測る限り「本当の幸せ」はない
目的は「見えない学力」、「見える学力」はその手段
4つ目の「チャレンジする力」は、「失敗する力」と言い換えることができるだろう。子どもは安心できる環境でこそ挑戦することができる。間違えたり失敗したりしたことを自覚し、やり直すことが成長につながるのだ。木村氏は、大人は子どもが安心できる環境をつくるだけでいいという。
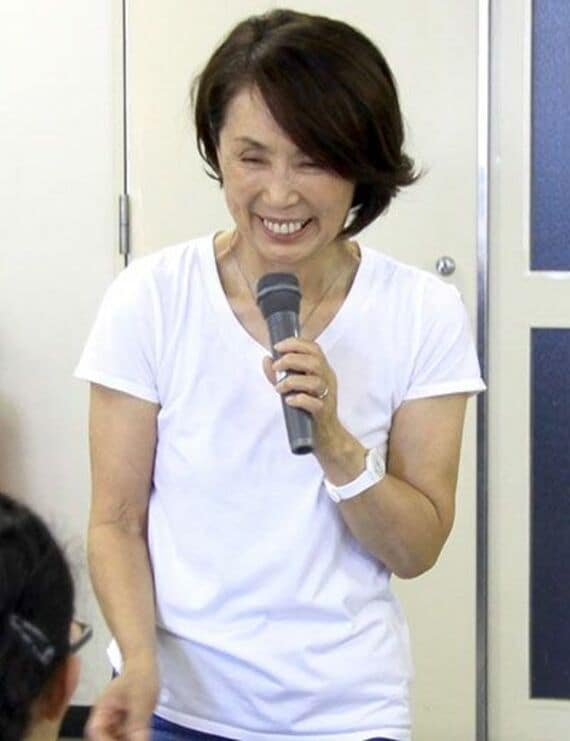
大阪府大阪市生まれ。武庫川学院女子短期大学(現・武庫川女子大学短期大学部)卒業。1970年に教員となり、2006年4月から、新設の大阪市立大空小学校の校長を9年にわたって務めた。著書に『10年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 「困った子」は「困っている子」』(青春出版社)、『学校の未来はここから始まる 学校を変える、本気の教育論議』(共著・教育開発研究所)などがある
(写真:木村氏提供)
「大人が正解を教える必要はなく、失敗したときには『大丈夫?』と聞いて寄り添うだけでいいのです。『大丈夫なわけあれへん!』と助けを求めるのか、『うん、大丈夫やで』と自分で解決するのか。それも子ども自身が決めることです」
こうした4つの力を伸ばすことで身に付くものを、木村氏は「見えない学力」だと説明する。これこそが、予想外の事態を自らクリアする力だ。大空小では4つの力を重視して子どもたちの「見えない学力」を高めたところ、「見える学力」である教科にも結果が表れたそうだ。その成果は大きく、全国学力調査で1位の県を上回った年もあるという。だがそれは「最上位の目的ではない」と木村氏は語る。
「受験の偏差値などの『見える学力』は、『見えない学力』が伸びる環境にいればおのずとついてくるものなのです。反対に『見える学力』だけを熱心に高めても、『見えない学力』はついてこない。『見える学力』を伸ばす教育は、『見えない学力』をつけるための手段にはなるけれど、目的にすべき一番大切な力を高めてはくれないのです」
目的と手段を取り違えてはいけないと繰り返す木村氏。「子どものウェルビーイング」を考えるヒントも、大空小が目的に掲げた「見えない学力」育成の過程にあるという。
「さまざまな環境要因もありますが、ウェルビーイングを実現するためには、子どもが自分自身で幸せになる力をつけることが重要です。他者評価で測ろうとする限りは本当の幸せとはいえないし、それは学力でも同じこと。旧来の『見える学力』は、担任教員などによる画一的な他者評価でした。でも大空小では、子どもが自分で目標を立て、達成度を自分で評価します。これによって、子どもたちは自分の成長や足りないことをしっかり考えられるようになるのです」
本当の学力も本当の幸せも、自分で自分を評価することができるようになってこそのもの。木村氏はそう考えている。
「学級王国」を打破し、子どもを主語に時間を使おう
大空小で子どもたちの「見えない学力」育成に寄与したもう一つの要因が、学級担任制を廃止して導入した「全員担当制」だ。これは固定の担任教員を決めず、すべての教員がすべての子どもを見守るシステムだ。東京・千代田区の麴町中学校で取り入れられて注目されたものだが、木村氏もこの考え方に賛同している。






























