経済|2018年に出たこの5冊|吉崎達彦

よしざき・たつひこ●1960年生まれ。旧日商岩井で広報、秘書などを経て現職。ユニークな視点に立った著書多数。テレビでコメンテーターも務める。(撮影:尾形文繁)
特集「ビジネスパーソンはこれを読め|2018年に出た「この5冊」」の他の記事を読む
歓迎すべき回顧録刊行 黒田さんも書いてほしい
2018年のベスト経済書はというと、やはり前日銀総裁による『中央銀行』にとどめを刺します。ピケティ以来のセンセーションじゃないでしょうか、厚さも含めて。金融政策の議論はさておき、バブルをどう思ったかとか、ゼロ金利解除ってやっぱりダメだったんだねとか、経済の同時代史を共有でき、貴重です。
驚いたのは、とても正直な点。たとえば東日本大震災のとき、日銀のメインコンピュータは本店とは別のところにあり、そこが計画停電実施地域になり、そうとう焦った、なんてことまで書いています。
なるほどなと思ったのは、白川さんはバブルを潰したことよりも、発生させたことを反省する方なんだということ。1980年代の日本は物価が安定していて、とても金利を上げるような状況じゃなかった。そしてバブルが発生した。人の思考は経験に規定されがちだ。白川さんは物価上昇目標2%に抵抗感があったのだと思う。
私の心に刺さったのは「ナラティブ(物語)の威力」という話。「円高は国難」「デフレが諸悪の根源」といった強いナラティブがあると、経済政策はどうにもならなくなる。昨今、確かにそうで、その傾向は年々強まっています。


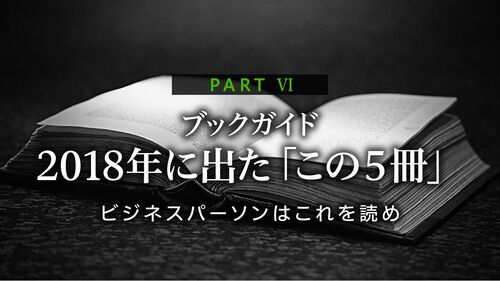































無料会員登録はこちら
ログインはこちら