価格高騰は一服でも消費者のコメ離れが加速 18年産米価格は下落へ
補助金政策で割を食った業務用米。実需に背いたツケは大きい。

今年も新米の季節が近づきつつある。10月に出荷が本格化する2018年産米は、その需給や価格が注目されている。国の減反(生産調整)政策の中心として約半世紀続いた都道府県別の生産数量目標の配分が廃止された後、初めて生産されるコメだからだ。
主食用米の価格(卸値)は17年産までの3年間で平均3割上昇した。背景には、減反をより促す手段として、飼料用米など主食用米以外の作物への転作助成金が14年度から拡充されたことがある。

収量の多い飼料用米へ転作すれば主食用米を生産するより農業所得が増えるケースも生じたため、転作が急増。13年には11万トンだった飼料用米の生産量は今や50万トン前後と、主食用米の生産量の7%近くに膨れ上がっている。

その結果、主食用米の生産は国の目標を下回る水準まで抑制された。特に、中食や外食など業務用に使われる低価格帯銘柄のコメは農家にとってもうけを出しにくいため極端な供給不足に陥り、3年で5割以上高騰する事態となった。









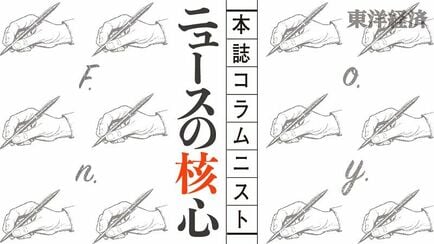






















無料会員登録はこちら
ログインはこちら