熱狂はいつまで続くのか 大流行のクラフトビール
シェアは1%未満、1990年代後半の地ビールブームの教訓を生かせるか。

「乾杯!」──。9月中旬、横浜港大さん橋ホールで「ビアフェス横浜」が開催された。司会の掛け声に合わせて、数百人の参加者が上機嫌でグラスを掲げた。
グラスを満たすのは、全国から集まった100種類以上ものクラフトビールだ。
クラフトビールとは、小規模な醸造所が製造するビールのこと。法律上の定義はないが、大手のビールに比べ、味や香りなどで個性を出しやすいことが特長だ。
ビール全体の課税数量は1994年度をピークに、2015年度は6割減の273万キロリットルにまで減少。一方で、クラフトビールの市場規模は推計で1%にも満たないが、数十社が新規参入し、15年度に2.3万キロリットルと、拡大が続く。

たとえば、新興クラフトビールメーカーのファーイーストブルーイング(渋谷区)は12年に参入し、15年8月期に売上高が1億円を突破。17年8月期も前年比40%増の数字を記録した。
実はこうしたブームを牽引しているのは、94年の酒税法改正による規制緩和で参入した、かつての地ビールメーカーだ。

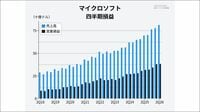









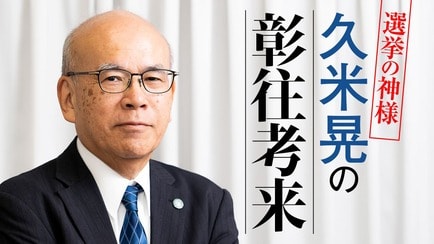




















無料会員登録はこちら
ログインはこちら