かのカール・マルクスが言った。「歴史は繰り返す。一度目は悲劇として。二度目は喜劇として」。
それでも歴史を繰り返したい人々がいる。とりわけ熱くなっているのが日本銀行の黒田東彦総裁である。
2014年10月31日、日銀はバズーカ砲第2弾をぶっ放した。長期国債の購入額を年50兆円から80兆円に拡大。新規発行の長期国債をほぼ丸のみにし、民間銀行から長期国債という安全な運用先を奪い去る。それをもって貸し出しなどリスク資産のほうへ銀行を追い立てる作戦だ。
同時に、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は国内債券(国債が中心)の運用比率を35%に引き下げ、内外株式の運用比率を40%超に引き上げる。
GPIFが売却する国債を引き取るのはもちろん日銀。日銀も自らETF(上場投資信託)やREIT(不動産投資信託)への投資を3倍に拡大する。
日銀は唯一無二の通貨発行権をフル回転させ、国全体がもっとリスクを取るよう誘導しているのだ。ちなみに、GPIFが想定する国内株式の利回りは1983~89年の企業収益・配当などを前提にはじき出している。想定期間の後半、日本はバブル(87年から90年代まで)の真っ只中にあった。
あの資産バブル期こそ、日銀と安倍政権が目指す「政策目標」なのだろうか。
89年12月29日、日経平均株価は史上最高の3万8915円をつけた。目もくらむ高みだが、すでにその1年前、日本株のPER(株価収益率=株価÷予想1株当たり利益)は55~60倍に達していた。米国株の平均PERはせいぜい15倍。ここで正気に戻ればまだよかった。が、株価が高すぎるのではなく尺度が間違っている、という議論が席巻した。

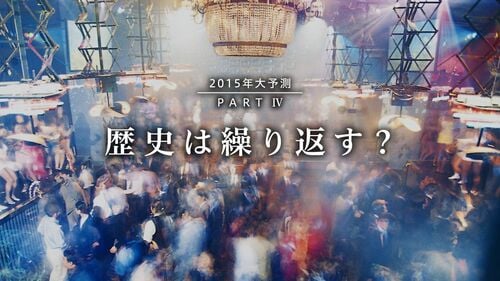
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら