iPad「賢くなるための道具」と徹底する、さとえ学園小学校の秘策 保護者とも連携、レベルアップ型ルールの効用

最終的には、子どもたちが自らiPadを管理し、スキルアップやモラル面での自己コントロール力を身に付け「BYOD」(Bring Your Own Device=個人所有の端末を学校に持ち込んで活用すること)を目指していくという。
同校が目指す子どもたちの姿の実現に向け、ICT教育を牽引してきた山中氏。自身のICT教育のルーツは、初任校である和歌山県のへき地小規模校にあるという。

「山と川の大自然に囲まれた公立小学校だったのですが、子どもたちが“田舎”にコンプレックスを抱いていたのです。ならば都会の小学校の子どもたちとつながり交流学習を行おうと。当時、町長はじめ教育委員会、町の方々の協力の下、コンピューター室に1人1台分のコンピューターを導入しました。1年生から学年に応じたテーマで、電子メールやテレビ会議システム、Webでのやり取りをしながら交流を深め、6年生の修学旅行で出会うというプロジェクトを通して、都会のよさを知りながらも自らの地域を再認識することができ、故郷を愛する心が子どもたちの中に芽生えました。この経験を通し、ICTは“やりたいことを達成するために必要不可欠なツール”であることを実感しました」
時代は変われども、ICTの神髄は変わらない。さとえ学園小学校が実現している学校づくりは、これから多くの学校が目指していく1つの形といえるだろう。
「子どもたちが1人1台端末を持つということは、新しい授業の創造への第一歩。新しいテクノロジーは、指導の個別化、学習の個性化など今までできなかったことをできるようにしてくれます。そのためには、まずはICTが空気のような存在にならなければなりません。とにかく『活用してみる』ことが大切です。ICTの活用は子どもたち、保護者、教職員をつなぎ、新しい可能性を見いだします。当校の取り組みを、多くの学校や教育関係者に参考にしていただきたいと思います」
(注記のない写真:さとえ学園小学校提供)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



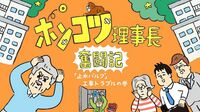




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら