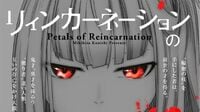「学校図書館」デジタル化阻む紙信仰と3つの壁 探究学習や多読と相性抜群のコンテンツとは
問題なのは2つ目の壁、「コンテンツ」だという。現在、端末整備が先行し、教材が不十分な状況にある。
「現状のデジタル教科書も検定教科書をスキャンしたようなPDFレベルです。これでは端末の本格活用は進みません。ただ、今までは教科書発行会社がデジタル教科書とデジタル教材を作って販売していましたが、今後は異業種の参入が期待されています。ICT活用が進んでいる通信教育や予備校、eラーニングやCBTシステムを提供する企業などのノウハウが入ってくることで、コンテンツ不足は解消されていくでしょう」
そして3つ目の壁が、「教員のノウハウの蓄積」だ。「端末活用は先生全員が新人です。端末やコンテンツを使いこなして先生たちがスキルやノウハウを高めていくところが、いちばん時間がかかると思います」と、植村氏は語る。
学校司書や司書教諭にも求められる「ICT活用能力」
こうした中、学校図書館を担う学校司書や司書教諭にはどのようなことが求められるのだろうか。
「先ほど紹介したようなレファレンスツールや電子書籍など、授業に活用できる魅力的なコンテンツはたくさんあります。まずはそういった信頼・安心できるコンテンツを導入し、マルチアクセスにして子どもたちがいつでも使えるようにしてあげられるといいですね。そして、端末やデータベースの使い方を教えてあげたり、困ったときにしっかり対応してあげたり、子どもたちがいつでも聞きに行ける環境を提供することが大切になります」

また、「教科教員との連携やサポート」も求められているという。新学習指導要領の総則には「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童(生徒)の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かす」と書かれている。今後、教科横断的な授業や探究学習が増えていく中、学校司書や司書教諭は各教科の教員と上手に連携を取っていく必要があるだろう。
「例えば、英語教員が『多読をやりたい』と言ったときに、どんなコンテンツでどんな授業をするのかということを提案するスキルが求められます。紙の本は付箋を貼りながら読むと記憶に残りやすいなど、空間把握的な力を生かした学習ができますが、調べる作業はデジタルのほうが圧倒的に優れている。こうした紙とデジタルの特性を踏まえた支援スキルなどが必要になってくるでしょう。また、私は小学校低学年ではデジタルコンテンツよりもリアルの経験が必要だと思っており、発達段階に応じた資料の提供も大事だと考えています」
こうしたスキルを養うためにも、学校司書や司書教諭は、ICT活用能力を身に付けて視野を広げていかなければならない。しかし、「図書館従事者の多くが、紙の本が大好きでICTに腰が引けている」と、植村氏。「読書は紙でするもの」といった考え方はいまだに根強く、電子書籍のメリットも理解していない人が多いことは大きな課題だという。
「世の中がデータベース化し、公共図書館も電子化が進み始めた今、学校図書館が変化に後ろ向きでいてよいのでしょうか。学校図書館は信頼・安心できるデジタルコンテンツを早く子どもたちに確保して学習環境を保障してあげるべき。そのことが、先生たちの新たな授業ノウハウにもつながっていくはずです」
(文:編集チーム 佐藤ちひろ、注記のない写真はiStock)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら