「理系学生の理系離れ」のなぜ、深刻な挫折理由 学生も教授も推す教育YouTuberヨビノリたくみ

東京工業大学大学院卒業。YouTubeチャンネル「予備校のノリで学ぶ『大学の数学・物理』」の創設当初から編集を担当する。高校生への指導経験があり、物理学や数学の面白い側面をわかりやすく楽しく伝えることに興味がある
大学に入学して、すぐにわかりやすい教材がないと気づいたことですね。博士課程に進んだ時点でも、まだそういうものが見当たらなかった。じゃあ、作っちゃえということで始めました。
高校生の時は、わかりやすい参考書があり、塾も予備校もあったのに、大学に入った途端になくなるのは何でなんだろうと、ずっと心に引っかかっていたんです。
僕は学生時代に予備校で講師のアルバイトをしていましたが、博士課程に進むときに日本学術振興会特別研究員に採用されました。ところが「副業禁止」だったんです。なので、講師は辞めるしかなかった。その代わりに何かしたいと思い、「科学の広報活動」の一環としてYouTubeだったら大丈夫だろうと考え、予備校講師の経験を十分に生かせる授業配信を始めたわけです。
──ヨビノリの理念は「理系の理系離れを防ぐ」だそうですが、自ら望んで理系学部へ進学した大学生が、なぜ入学後に理系離れを?
世の中には「子どもの理系離れを防ぐ」と言って、小中高校生を対象に理系科目を好きになってもらうための活動をしている方が大勢いらっしゃいます。サイエンスコミュニケーターという肩書の人もいますし、テレビ番組に協力して実験を魅力的に見せてくれる研究者もいます。
こうした方々の懸命な活動の結果、理系好きの子どもが育ち、理系学部へ進学するんですが、大学で勉強する内容は格段と難しくなるので、挫折して辞めていく学生も少なくありません。すごくもったいないですよね。そんな思いが、ヨビノリの理念と活動になっています。
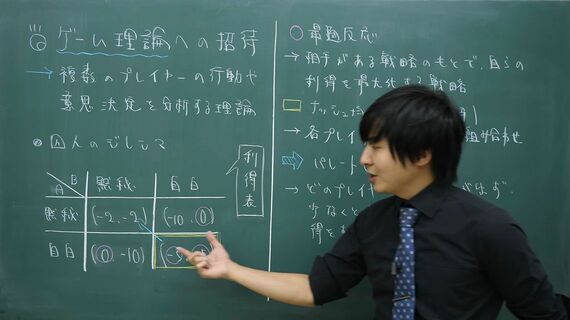
本当は進み切っている教育のICT活用、問題は子どものやる気
──小中学校では、いよいよ「1人1台PC」環境が実現します。たくみさんは、オンライン授業のメリット、デメリットをどうお感じですか。
わかりやすい授業を上手に展開できる人が1人いれば、誰もが、いつでも、どこででもその授業を見られる点が、オンライン授業の最大のメリット。一時停止も、繰り返し再生もできるので学生は大助かりです。
でも、いつでも、どこででもというのは、裏を返せば強制力がないということ。しかも緊張感を持って授業に臨み、集中力を保って視聴し続けられるかといったら、なかなかハードルが高い。これがオンライン授業のデメリットです。
対面授業なら、何時までに登校して、この授業を受けなければならないという決まりがあり、大抵はそれに従おうとしますよね。教室では周りがしっかり勉強しているし、おしゃべりやダラッっとした格好もできないから、緊張感も生まれる。耳と目に入ってくるのは、先生の言葉と板書と教科書、ノートだけだから集中しやすい。対面授業は時間対効果が非常に高いといえます。






























