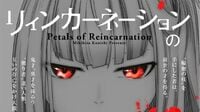中学校の「スマホ持ち込み」原則禁止から容認へ 災害時など緊急連絡手段としての活用を期待
中学生のみに認められたスマホ、理由は部活動
その条件とは、次のようなものだ。1つ目は学校における管理方法や、紛失等のトラブルが発生した場合の責任の所在を明確にすること。ここでは、生徒がかばんに入れて保管するほか、鍵付きロッカーでの保管や学校が一括して回収し、1つのかばんに保管するなどの方法が挙がった。この場合、学校や地域の実態を踏まえ、生徒や保護者、学校の間で共通理解のもとルールを策定し、同意書を提出することなどが求められる。
2つ目は指導体制の整備だ。あらかじめ学校から生徒に十分な指導を行い、生徒の自覚を促すなど、携帯電話の危険性や正しい使い方に関し、学校と家庭で適切に指導が行われていることが重要になる。そして3つ目には、フィルタリングが保護者の責任のもとで適切に設定されることが求められた。
では、なぜ中学校でのみ条件付きでの持ち込みが可能になったのか。
小学生のスマホを含めた携帯電話の所有・利用率は、2017年の内閣府の調査時点で55.5%と半数を超える(「平成30年度青少年のインターネット利用環境実態調査報告書」)。しかし、小学校の通学距離は大抵の場合、約4キロ圏内であり、登下校にさほど長い距離や時間がかかるわけではないという指摘から、引き続き原則禁止となった。ただ、地域により遠距離通学なども想定されるため、学校の許可を得るなどして例外的に持ち込みを認めることも考えられている。
一方、中学生の所有・利用率も66.7%と高くなっており、年を追うごとにその数字は上昇している。中学校の通学距離は多くの場合、約6キロ圏内。こちらでも、距離や時間の指摘に加え、SNSによるトラブルの発生が小学生と比べて高いことが懸念された。
ただ、中学校では部活動に参加する生徒も多く、帰宅時間が遅くなることから、条件付きで持ち込みを認めることになった。ちなみに高校生の所有・利用率は同じ調査で97.1%と100%近いが、校内での使用を制限するというこれまでの方針に変更はなかった。
以上のような状況を踏まえ、文科省では、児童生徒の登下校時の緊急時の連絡手段としてスマホのメリットを重視し、条件付きで中学校のスマホの持ち込みを容認することにした。今後も文科省では学校や教育委員会、児童生徒、保護者に対し、それぞれが意識を高め、ルールを守る姿勢を求めていく方針だ。
(写真:iStock)
制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら