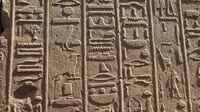「哲学対話の授業」確かな手応えと悩ましい課題 混迷の時代に育みたい「根本から問い直す力」
ガート・ビースタというオランダの教育哲学者は、今の子どもたちを自律的に掃除するロボット掃除機に例えてアクティブラーニングを批判しました。私も現代の学校教育がロボット掃除機のような、与えられた環境に適応して自走する子どもをつくるのでは駄目だと思っていて、そもそもそれが適応すべき環境なのかという根本から問える力を育てるべきだと考えます。そのツールとして、哲学対話やP4Cをもっと役立てていきたいです」
「鋭さ」と「場の安全性」の両立が課題
一方、課題もある。それは、開かれた対話や平等な対話をつくることの難しさだ。例えば男女差別の議論。先日も土屋氏が大学の授業で男女差別のテーマを扱った際、男女共に「大人が騒いでいるだけで差別などない」という意見が多かったという。
「学校の中では男女平等の理念が浸透しているため、実社会に触れた経験の少ない学生には『令和の時代に男女差別なんてもうない』という実感が強く抱かれるのかもしれません。それが経験量の偏りに基づいているのは明らかですが、哲学対話の理念は『多様な意見の尊重』なので、偏りに基づいた考えでも多数意見になると1つの考えとして容認しなくてはならないと思われがちです。

開智国際大学教育学部准教授。博士(教育学)。専門は哲学、哲学教育、教育哲学。2012年から学校法人・開智学園の複数の学校で、独自の教科「哲学対話」の専門教員として勤務。開智国際大学、立教大学、茨城大学、静岡大学等の非常勤講師を経て、20年4月より現職。主な著書に『僕らの世界を作りかえる哲学の授業』(青春出版社)など。毎日小学生新聞「てつがくカフェ」連載担当。NHK・Eテレの番組「Q~こどものための哲学」監修
(写真:本人提供)
しかし、こうした偏りを放置したままで『開かれた議論』を続けることは、それ自体が男女差別やセクシャルハラスメントで傷ついたことのある学生に対する暴力になりかねませんし、社会の分断をあおったり反知性主義に手を貸したりすることにもなりかねません」
こうした誰かを傷つけかねない状況は大人の「哲学カフェ」などでも問題視されており、昨今、哲学対話やP4Cの研究者および実践者たちの間でこの倫理的問題が共有されるようになってきている。
「場の安全性を改めて問い直す必要があるでしょう。とくに授業となると強制参加なので、どこまで踏み込んだテーマ設定や対話をするのかは考えなければなりません。しかし、哲学対話は攻めたことが言える自由さも大きな魅力であり、その鋭さが社会を問い直す力にもなる。非常に難しいですが、そこの両立が課題です」
また、土屋氏は、哲学対話が教員や生徒の重荷にはなってほしくないと思っている。「アクティブラーニングをやらねばと焦って始めたり、行政主導で強制的なものになったりするのはよくない。興味がある人も、構えず気楽に始めてほしい」と話す。
「対話もうまくいくときとそうでないときがあります。悩んでしまったら、『哲学プラクティス連絡会』のイベントや『哲学カフェ』などに参加し、実践者や研究者に相談するのもよいでしょう。私もコロナ禍が落ち着いたら月に1度の無料相談『子どもの哲学研修会』を再開する予定です」
(文:編集チーム 佐藤ちひろ、注記のない写真は開智日本橋学園提供)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら