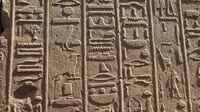「哲学対話の授業」確かな手応えと悩ましい課題 混迷の時代に育みたい「根本から問い直す力」
土屋氏は、以下の5つを哲学対話の授業の前に必ず確認している。
2:真剣に考えたことであれば、ほかの人を傷つける発言でない限り、どんなことでも自由に話してよい
3:わからないときは恥ずかしがらずに「わからない」と言おう
4:沈黙は気にしない
5:相手の話をよく聞こう
そして、「人はなぜ生きるか」「友達って本当に必要?」「大人と子どもの境目は」「名前はなぜ必要か」といったテーマをみんなで話し合って決め、上記の5つを前提に対話を進めていくという。

哲学対話の実践で見えてきた「教育効果」とは?
教育現場によって目的は異なるにせよ、これまでどのような成果が見られたのか。
例えば、リップマンの教材による実践は思考力の育成に成果があるというデータが多くあるという。2003年に宮崎県の公立小学校で行われた日本初のP4Cの授業でもリップマンの教材が使われ、論理的推論スキルの育成効果が認められた。今も哲学対話が盛んなオーストラリアでは1990年代後半に、ある州の公立小学校にて数学・理科・国語の学力が向上し、注目を浴びた。
土屋氏が心理学者と行った共同研究でも「自分とは異なる意見や考え方を受け止める姿勢」の向上が確認されているが、土屋氏は「どのデータも普遍的な効果とは言い切れない」と指摘する。哲学対話は実践者によって方法論が異なり、子どもの成長は学校全体でつくっていくものなので、その成果を見極めるのは難しいからだ。
しかし、この10年間の自身の実践を振り返り、「他者の意見を受け止め、物事をきちんと考える構えや態度が生徒たちに身に付いていると感じます」と、土屋氏は手応えを感じている。
学園の管理職やほかの教員からも、「話すことや聞くことに対する抵抗感がなくなった」「学び合いがスムーズにいくのは哲学対話のおかげ」「話し合いが必要になったときや教科でディスカッションしたいときにも議論を始めやすい」といった声が上がっている。
とくに土屋氏が実感しているのは「居場所づくり」への貢献だ。学校になじめないタイプの子が、面白い意見を言うことがよくあるという。
「学校になじめない子は、考えすぎて学業や日常生活でつまずいている場合が多い。でも、常識にとらわれていないから発言が面白い。私もそれを褒めるし、哲学対話の場はどんな意見も周囲から尊重されるので、生徒は『自分も学校にいていいのだ』という安心感を得ることができるのです」
また、土屋氏が授業を担当する学校では、哲学対話に夢中になる生徒が出てきて部活ができるという。開智日本橋学園中学校では、哲学対話が好きな生徒たちが集まって制服のあり方を議論し、学校に「女子もスラックスを選べるようにしてほしい」と起案書を提出。それが後押しとなり制服改革が実現したそうだ。
「哲学対話はこんなふうに学校を探究の共同体にし、何かを変える力を生み出すこともできます。実は哲学対話を始めるとその魅力に目覚める先生も必ず出てくるので、今後は先生たちも学校の中身を変えていくようになったら面白いなと期待しています」
土屋氏は、そのように今ある環境や現実そのものを疑い、問い直せる力を哲学対話で育みたいという。
「不安定な時代だから子どもたちはさまざまな力を身に付けなければいけないといわれていますが、そもそもなぜ不安定な時代になったのか、なぜ探究やプログラミングなど新たなことを学ぶ必要があるのかというところから自分で考え、批判的になれる力が今の子どもたちには必要です。