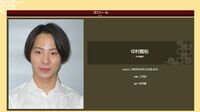子どもの主体性を高める「教えない授業」の今 新渡戸文化の英語教員に学ぶ「声かけ」の極意
「英語を使って何をしたいか」を問いかけ続ける
「子どもたちが学びたいと思っていない状態で、教員が教えすぎても何も残らない。大事なのは、学びたいと思わせることや、自分で一歩を踏み出す力を育むこと。どんな優れた指導法も子どもたちの『やりたい』にはかなわないと思っています」
そう語る山本氏は、コロナ禍においても、子どもたちの「やりたい」を大切にする「学びの起点づくり」に重点を置いた。
「各教科はあくまでも何かを達成するための手段。英語の場合は『言葉』を使ってどうしたいか、というところが大事。英語を使ってやりたいことが見えたときに、初めて文法を学ぶことの意味を知るのです」と、山本氏は説明する。
しかし、最初は「やりたい」や「なりたい自分」はなかなか出てこない。生徒たちは親や教員から「これをやりなさい」と指示されることに慣れており、「どうしたい?」と聞かれたことがほとんどないからだ。それでも問いかけ続けると、「英検を取りたい」「海外に行きたい」などそれぞれの「やりたい」が生まれてくるという。
コロナ禍でも、「やりたい」や目的意識を引き出すため、英語の面白さと出合えるようなオンラインならではの工夫を仕掛けた。例えば、Zoomを通じて、英語を使って仕事をしている人とつないだり、他校の英語教員に授業をしてもらったりした。
こうした刺激を与えながら、「学び方」も教えていく。「Weblioというサイトがあるよ」「教科書にこんなページがあるよ」と、単語の調べ方などを教えるほか、音読動画や教科書の解説動画を自作して掲示板ソフトのPadletにアップし、生徒がそれらを活用して自主的に学べるようにした。「『自分で学んでね』と指示だけして、最後に音読や自己紹介を撮影した動画を提出させるような授業を中心に展開しました」(山本氏)。

「できないことは可能性」だとすべての大人が言うべき
実際に、今年8月に行われた5日間のオンライン夏期講習を参観した。印象的だったのは、山本氏が「できないことは可能性」「できないことに優しくなろう」という言葉を繰り返し口にしていたことだ。
参加者は中学生で、3学年合同。英語の歌詞を聴き取る、英語のCM動画を見て主題を読み解くなど、各自が個々の英語の習得レベルに応じた課題に取り組んでいた。英語の歌で聴き取れた単語をヒントに、生徒たちがチャットに読み取った意味を書き込んでいく場面でのこと。「まったくわからない」と書き込んでいた生徒に対し、「いいねえ。まったくわからないということは、可能性の塊だね」と山本氏が声をかける。
「学習の目的は、できないことができるようになること。できないことはあって当たり前で、それは可能性だということを子どもたちに感じてほしい」と、山本氏は言う。

教員の役目は、枠組みをつくって子どもたちの可能性を「引き出す」役割に徹することだという。いろいろな可能性を見せて主体的な学びや成長を待つ。その結果、山本氏は、生徒たちが自らの「好き」「やりたい」を突き詰めすばらしいものを生み出したり、力を大きく伸ばしたりする姿を何度も見てきた。