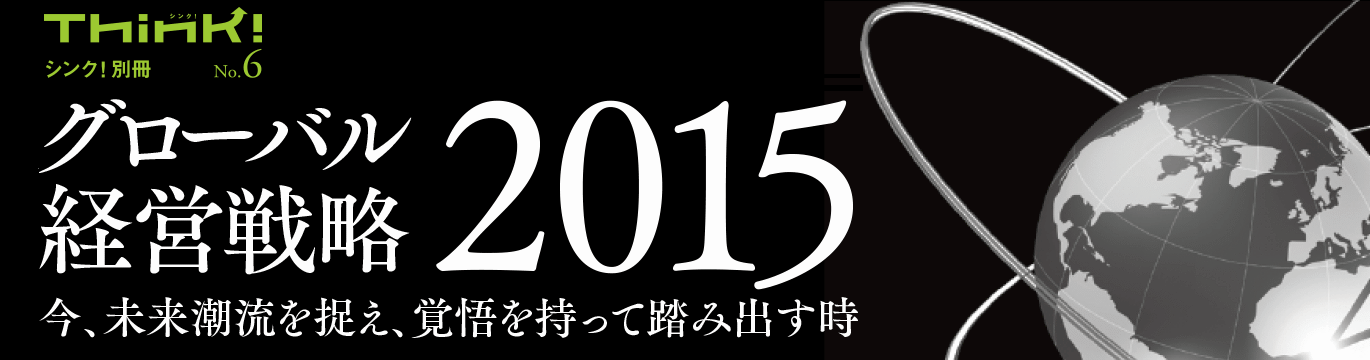自動車産業の構造変化に対応した勝利のシナリオ
佐瀬 真人(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)
× 田中 義崇(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)
「モノづくり競争時代」の終焉
T型フォード誕生以来、約100年にわたり自動車産業は持続的成長を遂げてきた。1990年代までの成長は日米欧といった先進国を主要マーケットとして、それ以降はBRICsやASEANに代表される新興国における人口増加や経済水準の向上に対応することにより、リニアな成長を遂げている。足元では自動車メーカー各社は車両のモジュール化や新興国への世界戦略車の投入等により、量的拡大と多様性への対応をめざし、しのぎを削っている。
そして今、自動車産業は新しいステージに突入しようとしている。その背後にあるのは、第一に、市場の世界拡大と供給不足である。2030年の市場規模は1億2000万台程度になるものと予測されているが、デモグラフィックベース(自動車購入が可能な所得層ベース)でのポテンシャルは1億5000万台である。つまり需要と供給のギャップが自動車メーカーの生産能力の上限を超えており、従来型の自動車産業が限界を迎えている状態となる(図表1)。
第二に、スマイルカーブ化による産業構造変化である。中長期的な目線で見れば、家電や半導体など他業種で見られるようなスマイルカーブ化、すなわち組み立て領域の相対的な付加価値低下と川上・川下領域への付加価値シフトは自動車業界にも生じることが予見される。それは自動車メーカーを頂点とする垂直的ピラミッド構造により成り立ってきた産業構造そのものを変化させる可能性が高い。
第三に、従来技術の成熟と、新しい技術の台頭がある。従来の内燃機関を中心とした技術に代わり、有害物質を一切排出しない究極のエコカーである燃料電池車や、人間が運転に介在しない、すなわち事故が起きない車を支える自動運転技術などが注目を集めている。
これらの変化が想定される環境下において、自動車メーカーが持続的な成長を実現するためには何が求められるだろうか。
社会課題解決が次世代バトルフィールド
広く世の中に目を向けると、依然として多くの社会課題が存在している。たとえば「2度上昇の危機」。地球温暖化問題は深刻さを増しており、特に今後気温が2度上昇すると、地球と人類社会は甚大かつ不可逆なダメージを被ると言われている。ほかにも、水問題や資源枯渇、高齢化、都市化など、今後さらに深刻になる課題は多い。
そうした社会課題の解決に向けて、企業に対する期待が高まりを見せている。NGOは社会課題を引き起こす企業に対する批判を活発に行っており、国家政府でも、環境への対応が不十分な企業を締め出す動きが複数国で見られている。また、株式市場においても、環境への対応が企業の強力なパフォーマンス指標になっている。こうしたさまざまなステークホルダーからの企業に対する社会課題解決にかかる期待を受け、経営学の領域でも、CSV(Creating Shared Value)に象徴されるビジネスと社会課題解決を同時追求する経営モデル構築の必要性が提唱され、すでに多くの先進企業がその実践を始めている。
自動車産業は、これらの社会課題と密接にかかわっている産業の代表格であると言っても過言ではない。地球環境を脅かす地球温暖化や都市生活の快適さを奪う渋滞、交通事故は、自動車産業の発展に伴う負の影響に起因している部分が大きく、自動車業界こそが社会課題に真正面から対峙しなければならない産業であると言えるだろう。
新しいステージを迎える自動車産業/業界が中長期的に社会から必要とされる存在であり続け、かつ持続的な成長を遂げるためのカギは、従来の「モノづくり」にとどまるのではなく、その枠を超えて社会課題解決を導き出すところで競い合う「事業モデル」までバトルフィールドを拡大することにあるのではないだろうか。
「事業モデル競争時代」を勝ち抜く戦略
「モノづくり」の枠を超えて社会課題解決を導き出すところで競い合う「事業モデル競争時代」を勝ち抜くための要諦は、いかに社会課題を的確に捉えて対峙するかにある(図表2)。その観点において、これまでの市場の中心であり成熟化が進展する先進国と、今後の市場の中心である新興国では、優先すべき社会課題が異なることは明白だ。