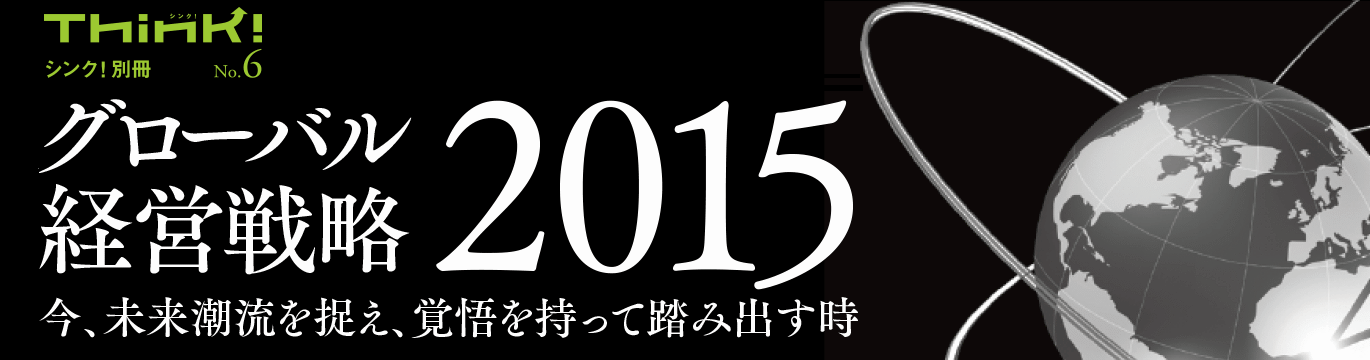自動車産業の構造変化に対応した勝利のシナリオ
佐瀬 真人(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)
× 田中 義崇(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)
先進国においては、「地球環境の浄化と、都市生活の向上」が求められる。危機的な状況にある地球を守るべく、率先して地球レベルの社会課題に取り組むことは、先進国の責務と言える。今後は新興国においても都市人口の増加は不可避な状況であり、渋滞や交通事故など新興国の都市生活を脅かす課題に対しても適用できる、人類として真のソリューションを導き出すことが不可欠である。加えて新興国においては「歪みなき、さらなる経済発展」が求められる。引き続き経済発展が求められる一方で、環境へのダメージや貧富差拡大といった、経済発展が生み出す負の側面としての「歪み」を是正していくことも、同時追求しなくてはならない。
各地の歴史的・地政学的な背景を踏まえつつ、この大きな2つの方向性を追求していくことが、自動車メーカーが「事業モデル競争時代」を勝ち抜くための戦略であると言える。
先進国モデル:「持続的モビリティ社会の創造」

自動車業界企業に対する競争戦略立案、技術戦略立案、組織・プロセス設計に関するコンサルティングに従事。近年は次世代自動車の普及に伴う業界構造の変化に対応した、成長戦略/新規事業立案や異業種企業の参入戦略などに注力。著書に『戦略のパラドックスへの解』(共著、翔泳社)、『図解 次世代自動車ビジネス早わかり』(共著、中経出版)がある。Consumer & Industrial Products Division共同リーダー。
人命を預かるという製品特性を持つ自動車産業は、高度かつ広範な技術領域の総合格闘技であり、開発・生産・販売の垂直統合型ビジネスモデルに代表される高い参入障壁に守られた「ガラパゴス産業」であった。しかしながらIoT(Internet of Things)の進展はその産業構造を一変させるインパクトを秘めている。
この数十年で飛躍的に技術進化を遂げ、さらにこの先の数十年のパラダイムシフトのドライバーであるIT技術を最大限活用することで「既存の製品・産業構造を前提とした付加価値向上・効率化」ではなく、「ITをフル活用することで初めて実現できる付加価値の創出」への挑戦が可能となるはずだ。自動車の宿命である安全性の確保と燃費の最大化について、現状の取り組みは“頑丈な”車をIT活用した衝突安全技術を駆使して安全性を高めるとともに、電動化技術を搭載することで個車単位での環境性能を最適化するという発想である。一方でIoT化された社会・交通システムをデザインすることにより、そもそも“ぶつからない”車が実現されれば、圧倒的に簡素な車両構造や軽量化に最適化された素材を採用することが可能となり、交通事故ゼロ・圧倒的環境性能を実現することが可能となるであろう。
新興国モデル:「真の産業報国」
これまでの時代において自動車メーカーが各国に対して果たした貢献、つまり産業報国とは産業政策への対応であり、特に雇用創出を軸とした、現地への資本投資が最大の手段であった。しかしながら社会課題が多様化する昨今の環境下においては、産業政策への対応は産業報国の一部でしかない。国家が抱える環境問題、産業の高付加価値化、教育水準の向上、格差問題の解消などのさまざまな社会課題を踏まえた新たな次元の対応が求められている。つまりは国家が直面する成長のボトルネックを解決することによる真の産業報国への貢献が求められており、国づくりのパートナーとしての役割を全うするというスタンスで臨むことが必要であろう。

自動車メーカー、部品サプライヤー、その他製造業を中心に、海外事業戦略、事業・組織再編、地域統括会社・持株会社設立、買収・合併・統合支援等に関するプロジェクトに多く携わっている。特に日本本社のみならず、海外現地事業体を巻き込んでのプロジェクト実績を多数有している。Automotive Sectorリーダー。
近年施行されたインドネシアのLCGC(Low Cost Green Car)政策を具体的事例として考えてみたい。当時のインドネシア政府は、①産業空洞化(2012年の機械・部品の輸入額は前年比15%増の一方、輸出額は前年比3.4%減)、②移動手段の未整備(鉄道密度世界最低:0.35km/100km2、乗用車保有台数:4台/100人)、③CO2削減(CO2の排出量世界4 位、COP15にて26%削減目標〈2020年〉)、④財政逼迫(燃料価格引き下げのための補助金が政府支出の30%となり、自動車普及のジレンマになった)という課題を抱えていた。
これらの課題への対応策として「市場活性化、部品産業の育成・強化」を目的として、現地調達率80%以上の条件を満たす車両を認定し、奢侈税を減免する恩典を与えたのがLCGC政策である。しかし、これに呼応して行われた各社の投資は、販売市場の中心であるジャカルタ近郊に集中し、廉価車を大量販売する事態となり、結果として都市部の渋滞、大気汚染が深刻化し、本来の目的である産業振興機運の減退要因となってしまった。
当初政府が期待をしていたのは、農村部における産業振興とモータリゼーションである。地方分権化により独立採算を余儀なくされている地方政府の財務状況の改善や、首都と地方では3~5割も乖離している最低賃金の引き上げを実現するという真のねらいをつかみきれていなかったことが原因として考えられる。
そのような原因を踏まえれば、総国民移動手段確保への支援として、「残価設定ローンの導入」や「中古車市場の構築」、さらには「公共交通網整備(地方都市・路線バス)」が需要サイドの真のニーズ解決策であり、供給サイドに対しては地方部での工場建設が望まれると考えられる。つまりは新車増産だけではインドネシアのためにならず、「農村部を中心に広く国民に交通手段を提供する」ための支援こそが真の産業報国であると捉えられるであろう。
さらには同じアジア諸国においても、一見すると似ている投資誘致の産業政策も、丁寧に背景をひもとくと、自動車メーカーが取るべき対応が各国ごとに異なるはずである。政府のニーズを理解し社会課題に対応することによって、政府・地域との関係強化を図り、事業成長の地固めを行うことが、今後の持続的成長には欠かせない取り組みであると考える。