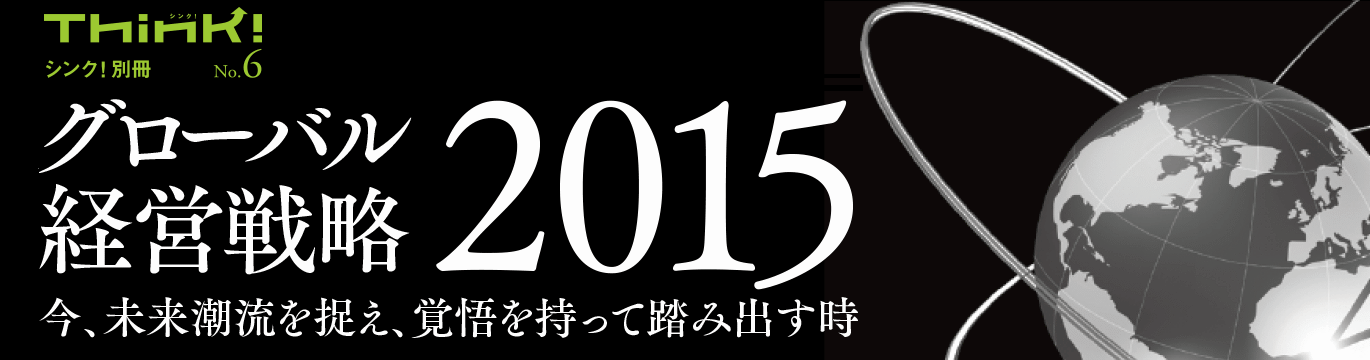スケーラビリティと日本らしさで
成熟した海外の旅行者を呼び込む
星野 佳路(星野リゾート代表)

インタビュアー:
萩倉亘(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)
日本のホテルが海外進出に失敗した2つの理由
萩倉 亘(以下、萩倉) 日本の産業の発展は、モノづくり分野を中心とした機能や品質の追求という「日本発」の強みを世界に売ってきた歴史といえると思いますが、グローバル競争のなかで「日本発を世界に売る」ことをあらためて捉え直し、もう一歩踏み出さないといけないという認識があります。ホテル産業で日本の魅力をグローバルに発信されている星野さんの視点から、「日本発を世界に売る」ために何が必要なのか、お考えをお聞かせください。

1960年長野県軽井沢町で星野温泉旅館の4代目として生まれる。慶應義塾大学経済学部卒業、米国コーネル大学ホテル経営大学院修士課程修了。日本航空開発(現・JALホテルズ)に入社。シカゴにて2年間、新ホテルの開発業務に携わる。89年に帰国後、家業である株式会社星野温泉に副社長として入社するも、6カ月で退職。シティバンクに転職し、リゾート企業の債権回収業務に携わったのち、91年再び星野温泉(現・星野リゾート)に入社、代表取締役社長に就任。
星野 佳路(以下、星野) 確かに日本ではこれまで、トヨタ自動車やソニーなどの製造業が中心となり、日本の製品を世界に輸出することで外貨を稼いできました。しかし、ご承知のとおり、日本の産業構造は製造業からサービス産業へのシフトが始まっています。だとすると、これから日本では、サービス産業が海外からお金を稼ぐ産業になるべきであり、ホテル産業はその一翼を担うと考えています。
萩倉 日本のホテル産業の海外進出というのは、これまでどのようになされてきたのでしょうか。
星野 過去に何度か、世界に打って出ようという試みがありました。最大の挑戦は1980年代後半から1990年代前半のバブル時代のことです。日航ホテルが世界でチェーン展開し、セゾングループがインターコンチネンタルホテルを買収するなど、この時期、数多くの海外進出がなされました。しかし結果的に、日本のホテルは世界進出を断念せざるをえませんでした。
萩倉 バブル崩壊がそのきっかけでしょうか。
星野 確かにそれもありますが、原因はそれだけではありません。私は、失敗の原因は大きく分けて2つあると考えています。1つは、スケールです。海外の巨大なホテル運営会社に戦いを挑むなら、当然、スケールメリットでも勝負する必要があります。でないと、ブランドアピールやコストコントロールの面で太刀打ちできないからです。このスケールの面で、当時、日本のホテルは外資に勝てなかったと思います。
そしてもう1つは、日本のホテルが、海外の観光客に対して「日本らしさ」「日本ブランドのホテルに泊まる理由」を明確に提案できなかったことです。日本はこれまで製造業において機能の秀逸さで世界を席巻することができましたが、ホテルではそういうわけにはいきませんでした。日本ブランドのサービスや「おもてなし」を選ぶ理由を、もっと打ち出すべきだったと思います。
この2つの教訓こそが、かつて日本のホテル産業が世界に挑戦し、撤退したときに得た学びです。この先グローバル競争で戦っていく際には、「スケール」と「日本らしさ」について考えておかないと、同じ轍を踏むことになります。
所有と運営を切り分けてスケールを追求する
萩倉 スケーラビリティという点では、ホテルの所有と運営を切り離し、「運営のプロフェッショナル」になることがポイントになりそうですね。
星野 おっしゃるとおりで、海外のホテル運営会社にスケールで負けないようにするためには、運営に特化することがわれわれにとって当然の選択なのです。というのも、バランスシートが不動産と債務で膨らむと、やがて資金調達に限界が訪れ、スケールを追えなくなるからです。
しかしながら、日本の多くのホテルや旅館では所有と運営の分離に抵抗があるようです。星野リゾートが過去20年間で成長できた背景には、私たちの戦略が正しかったこともありますが、競合が所有と運営の分離に踏み切れなかったことで差が開いたのも事実です。
萩倉 ホテルや旅館は経営母体が家業であることが多いゆえ、目に見える資産である不動産を次世代に承継したいという思いが、そこに踏み込めない理由なのでしょうか。
星野 不動産の所有権を手放すと、ホテルや旅館の運営に自分のコントロールが利かなくなる不安があるからでしょう。この根拠のない漠然とした不安が、所有と運営の分離を妨げているのだと思います。
また、そもそも家業が何を目指すのかという定義が曖昧なことも、問題の根底にあると思います。家業として運営のプロをめざすのか、資産管理のプロを目指すのか、まずそれを明確にするべきです。もし所有を続けるなら、資産管理に手を取られることになるので、当然運営のプロは目指せません。
コモディティ化した外資の運営手法と、
日本独自の「旅館メソッド」
萩倉 もう1つのポイントである「日本らしさ」については、どのようなことを大切にされているのでしょうか。たとえば消費財メーカーでも、ローカルの市場で成功を収めたものを製品という形式知でそのまま海外に展開しても、なかなかグローバル競争では勝てません。これは日本企業のことだけでなく、かつてはP&Gのようなグローバル企業でも苦戦しました。サービス業においては、ことさら暗黙知を組織の知とすることが大事だと思います。
星野 日本国内にある巨大な観光需要を基盤とし、そこで培ったものを海外に持っていくことが「日本らしさ」につながると思うのですが、私が特にこだわりたいのは運営手法です。実は日本のホテル運営の手法は非常に独特で、これこそが日本のホテルに泊まる理由になると考えています。
萩倉 外資のホテルチェーンとは同じ土俵に上がらない運営手法、ということですね。
星野 過去30年、外資の運営会社が世界を牛耳っていた時代の基本的な概念は「スタンダード化」でした。スタンダードをつくり、モジュール化することによって効率性も高くなった側面はあるので、私もそれをまったく否定するわけではありませんし、確かに彼らは強い運営をしているのですが、その手法はすでにコモディティ化しています。彼らの運営方法はすべて同じになってしまったのです。マニュアルがほとんど変わらないので、マリオットの総支配人だった人が、すぐにヒルトンやハイアットの総支配人を完璧に務めることができるくらいです。実際、人材の動きも激しいといわれています。
そしてリーマンショック以降は、ヒルトン、ハイアット、マリオットが運営しないヒルトン、ハイアット、マリオットのホテルが誕生しました。これは衝撃的です。なぜなら、誰が運営しても同じだと証明されてしまったのですから。投資家たちはそれ以降、それらの大手ホテルチェーンに、本当に運営ノウハウがあるのか、それが本当に特別なものなのか、問いかけ始めています。
萩倉 今もその傾向は続いていますか。
星野 さらに進んでいます。彼らの運営手法に満足できない投資家は、名前だけ残して自ら運営する方向に向かっています。ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーも、今では自ら運営会社を持つようになりました。