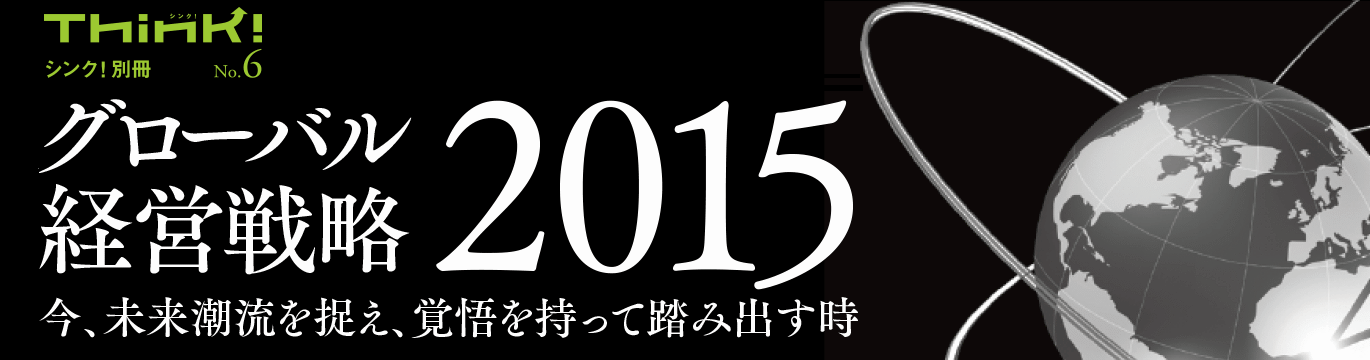スケーラビリティと日本らしさで
成熟した海外の旅行者を呼び込む
星野 佳路(星野リゾート代表)
萩倉 ホテル運営のあり方そのものが見直され、新しい価値を模索しているように見えますね。
星野 一昔前までは、スタンダード化によって、カイロでもロンドンでも東京でも、ヒルトンと名がつけばある一定の基準を満たしてくれる安心感こそが、ホテルチェーンが提供すべき最大の価値でした。
ところがここ10年ほど、先進国の旅行者が急速に成熟し始め、彼らは渡航先の「ローカル色」を求めるようになりました。カイロではカイロらしさ、ロンドンではロンドンらしさ、東京では東京らしさを求めています。

成長創出にフォーカスしたコンサルティングに従事。コーポレートアントレプレナーシップの醸成が持続的成長の源であるという信条の下、成長のためのアジェンダであるイノベーション、トランスフォーメーションの各領域にてさまざまなサービスを提供している。近年は共通価値創造(CSV)、および新産業起点の地域活性化等も多数手掛けている。Consumer & Industrial Products Division共同リーダー。Cross Sectorリーダー。
萩倉 世界標準のスタンダードだけでは満足できなくなり、ローカル色に価値を見いだすようになったということですね。これは、日本がグローバルに出ていく上で追い風になるのではないでしょうか。
星野 そうです。そして、ローカル色、地域らしさ、それを良い形で提供するおもてなしは、日本の旅館が得意としてきた分野です。日本の旅館は、地産地消や季節感の反映、お客さまの趣向の反映について長い間研究してきています。私はこれを「旅館メソッド」と呼んでいますが、これこそが海外進出の際のキーになる「日本らしさ」だと思っています。
萩倉 旅館メソッドについて、もう少しその具体的な内容を教えてください。
星野 旅館メソッドを支えるのが、私たちが「サービスチーム」と呼んでいる仕組みで、これは世界中のホテル運営会社のどこにもまねのできない、非常に行き届いた仕組みになっています。
一番の特徴は、多能工化――つまりマルチタスクです。前に挙げたような外資のホテルチェーンでは、フロントスタッフは専任の人がやり、調理は調理師に任せ、部屋の清掃は外注する、という運営方法がとられていますが、サービスチームでは、トヨタ自動車がやった多能工化を、ホテルの運営において徹底的にやるのです。ベッドメーキングからレストランサービスまで1人ですべてこなせるからこそ、お客さまへのシームレスなサービスや気配りが可能になります。また多能工化することで、限られた部屋数でも高い生産性が確保できます。
萩倉 非常に共感できるお話です。たとえば製造業の世界でも、Fortune Global 500にランクインするような企業の多くが今、モジュール化の世界で戦っているのですが、モジュール化を進めるとコモディティ化していくことが目に見えています。一方で、サービス業においては擦り合わせを価値の中核に置いているトヨタ自動車のような会社から学ぶべきことがあるのではないでしょうか。暗黙知の移転・形式知化を進めながら効率も上げていくというスタイルに。
星野 実は日本でも多くのホテルマンたちが、多能工化に強く抵抗しています。「自分はフロントのプロ、ベルボーイのプロだ。部屋の清掃などパートの人たちに任せればいい。調理は調理師の専売特許だ」と営々と培われてきたこのようなホテルマンの文化は、今も根強く残っています。星野リゾートでも多能工化を宣言すると、半分程度の従業員が辞めていきました。しかし私は、このことをむしろ歓迎すべき現象だと捉えました。巨大な組織を持つ外資の運営会社が多能工化をまねしようとしても、それが困難であることの証だからです。
多能工化されたサービスチームによって実現される、旅館メソッド。星野リゾートが世界の投資家に訴えていく上で、これは最大のアピールポイントになります。極端な考え方をすれば「名前はメジャーなホテルだけれど、運営は星野リゾートが担う」ホテルが生まれるかもしれません。スタンダードの安心感は重要ですが、それに旅館メソッドによる「日本らしさ」を足すことができれば、まねのできない新しい価値を提案することができると考えています。
萩倉 まさに今、日本がこだわるべきなのは“Made in”ではなく“Made by”や“Produced by”ではないでしょうか。
海外進出第1号「星のや バリ」の挑戦
萩倉 2015年にオープンする「星のや バリ」は、星野リゾートにとって海外進出の第一歩となります。これは今後のグローバル展開における試金石になりますね。
星野 バリで私たちが成し遂げたいと考えていることが2つあります。1つは「ローカル色」をサービスや食事に落とし込むことです。現在、バリにあるフォーシーズンズやアマンなどのリゾートホテルは、いずれも西洋人から見た快適性を求めて設計されています。星野リゾートがやるべきことは、バリの人がヒンドゥー文化など、来訪者に伝えたいこと、ご当地自慢したいことを汲み取り、それを中心にサービスや食事を設計することです。バリの人の生活のなかにこそ、成熟した旅行者を満足させるヒントがあると考えています。
萩倉 そうした地域の文化のこだわりや季節感をサービスや食事に反映させるメソッドこそ、「旅館メソッド」なのですね。
星野 そうです。そしてそれを支えるサービスチームの運営方法を海外に持ち込み、通用することを証明する。これが、バリで成し遂げたいもう1つのことです。現在、インドネシアをはじめとした東南アジアのホテルでは、頭数を揃えてサービスを向上させる運営方法が主流になっています。これは人件費が低いからできる方法なのですが、いずれ東南アジアでも労働生産性が問題になるはずです。そのときに、人件費単価が低いことを利用したオペレーションに甘えないわれわれの運営方法は、大きな強みになっていると思います。
日本の観光産業の隆盛に欠かせない
「休日の平準化」とLCC
萩倉 観光の世界において海外に日本を売るという視点からは、2020年の東京オリンピック・パラリンピックはこの上ないイベントですが、星野さんは今からその先(2021年以降)を見据えておく必要があると強く主張されています。日本がこの先、観光立国としても成長していくためには、国として、あるいは業界として、何を考えていく必要があるでしょうか。
星野 日本を観光立国にする上で、「人材をどう確保・育成するのか」「インフラ整備が足りないのではないか」「利益率や生産性が低いのではないか」といろいろ考えるべき問題がありますが、こうした諸問題を解決するためにも、まず「休日の平準化」を真剣に検討する必要があるでしょう。
観光業界ではよく「100日の黒字と265日の赤字」という言葉を使います。1年のうち週末や祝日から成る100日は極端な需要過多のため、努力をしてもしなくても黒字になるのです。たとえばゴールデンウイークは、人気のある宿から埋まりますが、結局最後には人気のない宿も満室になる。これは休日が集中しているからです。
反対に、残りの265日は極端な供給過多のため、努力の差がほとんど出ないような仕組みになっているのです。努力してもしなくても結果が同じであれば、努力しないほうが得だというマイナスのモチベーションが働く。これでは、健全な競争環境が形成されるはずがありません。
萩倉 そうした不健全な状況を打開するために「休日の平準化」が必要なのですね。
星野 日本のホテル産業の生産性を向上させる本丸です。消費者から見ると価格の低下、混雑緩和という恩恵が受けられます。一方で、健全な競争が始まると淘汰が起こるので、努力を怠っているホテルは困ります。だから、「休日の平準化」の導入に反対しているのは、実はそのようなホテル自身だったりするのですが、そうした考え方が日本のホテル産業の競争力を弱め、グローバルで勝てない状況を自らつくり出していることに、彼らは一刻も早く気づくべきです。