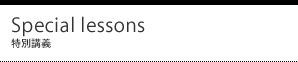経験と言語の螺旋で、学びが深まる 知識を創造しイノベーションを起こす教養
ライフワークとしての知識創造理論

それと時を前後して、私のライフワークとなる知識創造理論のもととなった概念が浮上してきます。1970年代の経営学では、1978年にノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモンの情報処理モデルというものが学会を席巻していました。サイモンは人間を、情報の処理をするコンピュータに見立てたのですが、私は情報と知識とは異なるもので、情報は与えられてそこに存在するものですが、知識は与えられてそこに存在するものではなく、組み合わせれば新しいものが生み出されるという単純なものではないと考えるようになっていきました。知識というものはもともと主観的であり個人の暗黙知に根差します。その個人の暗黙知を言語化することによって形式知に置き換え、他者と共有し合意形成しながら、他者の暗黙知や形式知と組み合わせて新たな知識を創造していくプロセスなのです。最近では、そういうプロセスがイノベーションにつながっていくと考えるようになりました。
知識が主観的であるという意味は、その主観を持つ個人が何をやりたいかが非常に重要であり、自らの身体で感じる経験を積まないと生み出されません。バークレーを卒業後、日本に帰国して日米企業の比較研究をしていた私は、この暗黙知と形式知のスパイラル・プロセスに着目しました。バークレーの1期後輩の竹内弘高氏(現・ハーバード大学教授)と幾つかの日本企業の事例を取材して、新製品開発のプロセスに関する論文をまとめ、1984年にハーバード大学の記念シンポジウムで共同発表をしたのです。この論文は、着眼の新規性もあって非常に注目されました。
この論文で得た概念をさらに発展させるべく、日本企業のイノベーションの源泉が身体に根差す暗黙知にあることを二人で調べていき、1995年にThe Knowledge-Creating Company(邦訳は『知識創造企業』1996年)という書籍を出版しました。これは英語で海外向けにまず発表したのですが、その理由は、コンセプトの共有をグローバルに行うことが大切だと常々考えていたからです。そのおかげか、「知識」という概念や「知識創造」という研究は、今では経営学にとどまらない領域でも注目されるようになっています。
そして私は今も、知識創造理論を一歩でも完成に近づけたいという思いで研究活動を続けています。充実すべき領域は無数にあって、どこを攻めるかは現場に行きながら考え、どこにいてもその場にあてはまる最適な言葉は何かと思いをめぐらしています。動きながら考えるのでとんでもない展開になることもありますが、知識ベースの経営学を完成の域にまで高めたいという目的意識だけはいつもしっかり持っています。その目標があるから、現場でも概念や意味がつながって新たな関係性ができてくるのです。逆に言えば、そういう目標やビジョンをきちんと持たないと、理論を持続的に積み上げていくのは難しいのではないでしょうか。