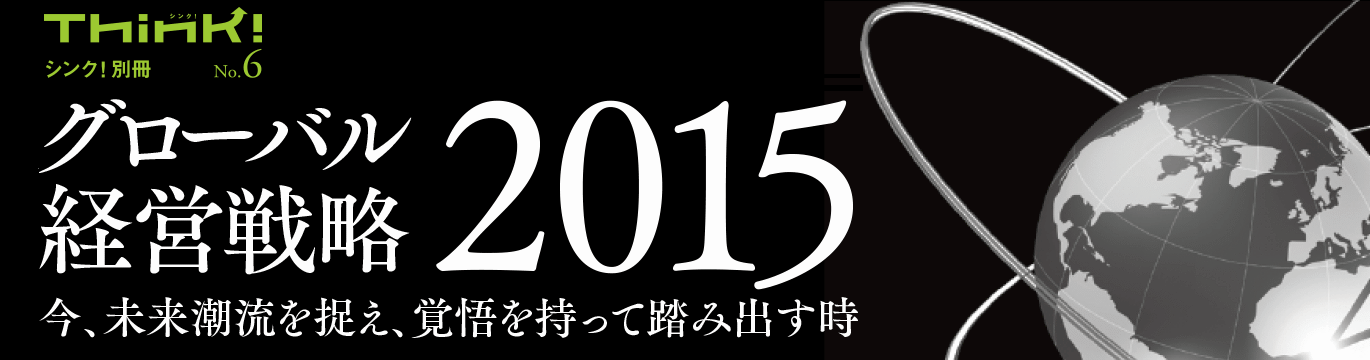グローバルを錯覚するな 入山 章栄(早稲田大学ビジネススクール 准教授)
「グローバル」に惑わされないためにも「知の往復」を
本稿では、近年の経営学の学術的な知見から、「グローバル」を正確に、客観的に、冷静に理解する必要性を述べてきた。「グローバル」と聞くと、世界中の経済が何もかもつながって津波のように押し寄せて、世界中の市場を満遍なく支配するような企業が続々と登場し、どのような役割も果たせるグローバル・エリートが出現しているイメージがある。しかし現実は、そのイメージから程遠いのだ。日本企業には、その事実を理解した上での戦略・組織作りが求められている。
他方で、本稿で述べたことは、あくまで学術的な知見にすぎない。これが実際のビジネスに落とし込まれるには、経営者・コンサルタントなどビジネスの第一線に立つ方々の知見と比較され、集約されることが欠かせない。この「経営者=コンサルタント=学者」の対話の重要性は、『Think!』2014年春号でも筆者が主張したところだ。その意味で、本誌の意義は大きい。なぜなら、本誌にはこの3つの視点が同時にあるからだ。「グローバル」の新しい学術的知見は、すでに筆者が論じた。ここから本誌を読み進めていけば、そこには三菱ケミカルホールディングスの小林善光氏、ピジョンの山下茂氏、星野リゾートの星野佳路氏など、今注目されている経営者の「グローバル」の視点が紹介されている。さらに急成長するコンサルティング会社、デロイト トーマツ コンサルティングのトップ・コンサルタントによる「グローバル分析」の知見がふんだんに盛り込まれている。
読者の皆さんには、ぜひこの三者の視点による「知の往復」を通じて、皆さんなりのグローバルの視点を磨いていただきたい。それこそが、言葉面の「グローバル」に惑わされないために、最も効果的な方法なのだ。
*1 JETRO 公表データより、名目額ベースによる計算。
*2 Ghemawat, P.(2003)“Semiglobalization and International Business Strategy,”Journal of International Business Studies 34(2):138‐152.
*3 Ghemawat(2003)によると、この「グローバル化」のベンチマーク指標を提唱したのは、経済学者のジェフリー・フランケルである。くわしくは、Frankel, J. A.(2001)“Assessing the Efficiency Gains from Further Liberalization,”in Porter, R. B. et al.(eds.)Efficiency, Equity, and Legitimacy: The Multilateral Trading System at the Millennium, Brookings Institution Pressを参照。
*4 Rugman, A. M. and A. Verbeke(2004)“A Perspective on Regional and Global Strategies of Multinational Enterprises,”Journal of International Business Studies 35: 3‐18.
*5 Bartlett, C. A. and S. Ghoshal(1992)Transnational Management: Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management, Richard D. Irwin(梅津祐良訳『MBAのグローバル経営』日本能率協会マネジメントセンター、1998 年)。
*6 朝日新聞グローブ、2014年9月16日配信記事より。
*7 http://geert-hofstede.com/national-culture.html
*8 http://www.weforum.org/issues/global-competitivenessprofile