「クソババア!」と言われたら、親はどうする?子どもの言葉遣いが悪い時の対応 「I話法」によるフェアなコミュニケーションを
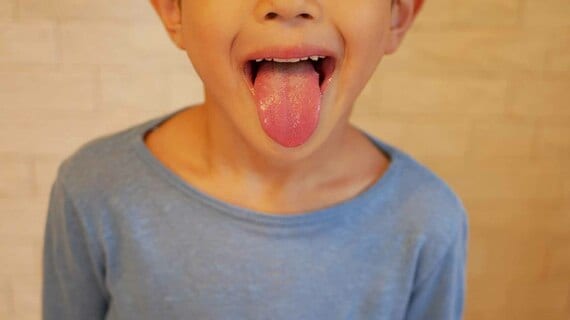
「You話法」と「I話法」で印象はここまで変わる
例えば、子どもが母親に対して「クソババア」と吐き捨てたとしよう。
親としては、どこでそんな言葉を覚えたのか、どんな友人と関わっているのか、などと環境のせいにもしたくなるだろう。とはいえ、子どものコミュニティーを制限するわけにはいかず、人間関係をコントロールするのも難しい。

作家・心理カウンセラー。東京大学教養学部卒業後、角川書店、博報堂を経て、五百田達成事務所を設立。豊富なカウンセリング実績に裏打ちされた、人間関係・コミュニケーションにまつわるアドバイスが好評で「ヒルナンデス!」(日本テレビ)、「この差って何ですか?」(TBS)ほか、メディアにも多数出演。『超雑談力』『察しない男 説明しない女』『不機嫌な長男・長女 無責任な末っ子たち』『10歳までに身につけたい 自分の気持ちを上手に伝える ことばの魔法図鑑』など、著書は累計120万部を超える。スコラが展開するオンラインアカデミー「東大式 親子の会話アカデミー」監修
(写真は本人提供)
そこでつい、「汚い言葉を使うと頭が悪くなるよ」「乱暴な子だと思われちゃうよ」「友達や先生に嫌われるよ」などと「あなたが/君は」というトーンで声をかけてしまうのだが、こうした「You話法」での受け答えはフェアではないと五百田氏は語る。
「対人コミュニケーションにおいて、こういった返答は一方的な押し付け、偽善に陥りがちです。親にはまず、わが子が人格を持った、『家族』という社会コミュニティーの構成員の1人であることを念頭に置いてほしいのです」
五百田氏は、子どもに対しては「You話法」ではなく「I話法」で答えるべきだと語る。
「一対一のコミュニケーションなのに、『みんなにどう思われるかな〜?』と第三者を持ち出すのは大人の狡さです。子どもは、自分が『乱暴な子』と思われて困るのが親の都合であることを見抜いています。冒頭の『クソババア』に対する声かけは、『私はその言葉を使ってほしくない。だからやめてほしい』と伝えるのがよいでしょう」
































