現場を支える「脂の乗った」ミドルリーダーたちが疲弊、離職する学校の深刻 五木田洋平「ポリシーメイキング」を勧める理由

「学校組織を変えたい」と願う割には…
今、本屋の教育書コーナーに行くと「定時に帰る! 時間術」といった類いの本がズラッと並んでいる。これに僕は猛烈な違和感を感じている。定時に帰りたければ帰ればいいし、仕事が嫌いではない僕でも定時には帰りたい(無駄な会議が嫌いで、有給を消化して定時前に帰ることも、前職ではザラだった)。
ただ新人時代は仕事がまったくできず、毎日校舎が閉まる21時、学校に無理を言って22時まで働いて、さらに家でも仕事をしていた。だから、なおさら定時に帰ったほうがいいと思う。でも、この違和感は何だろう。そう考えるうちに、あるCMを思い出した。
飲み屋の隣の席から聞こえる「うちの会社はさぁ、新しいチャレンジを認めてくれなくて困ってるよ」。そんな話を聞くたびに心のどこかにしこりができるのを感じていた。変えるならきっと今だ――。
自分の可能性を試したい若者向け転職サイトのCMだ。それまでの違和感が、この飲み屋にいるサラリーマンの愚痴とつながった。「学校組織を変えたい」と願う割には組織論として話していない。ただ学校が変わらないことを嘆いている、誰かに変えてもらうことを待っている、それでいて変わることを拒否しているダサい教員の世界が僕は嫌いだった。自分が学校という組織を変えるきっかけをつくらなければ!と。
子どもの可能性を引き出すことは教員に「よはく」がないとできない
自己紹介が遅くなった。僕は10年間、私立の小学校で勤務をしていた。2015年には茨城県にある開智望小学校の立ち上げに関わり、22年にはヒロック初等部というオルタナティブスクールを立ち上げた。
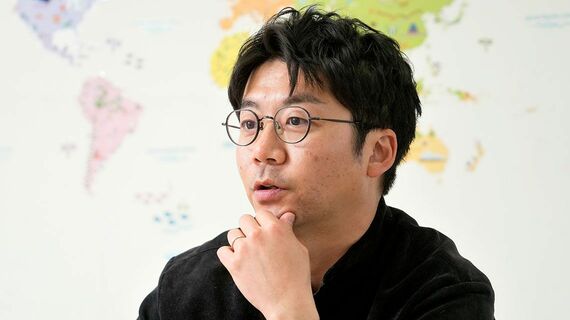
HILLOCK(ヒロック)初等部 カリキュラムディレクター
私立小学校で10年間勤務した後、2021年3月に東京・世田谷にオルタナティブスクール、ヒロック初等部を創設、22年4月に開校。教員時代はクラス担任、学年主任、ICT部主任などを兼任し、学び合いの授業実践を研究しながら子ども同士が学び合う、自分たちを表現するクラスを運営。2014年度~20年度に私立開智望小学校の設立と運営にも参画し、ICTを用いて日本語版のインターナショナルバカロレアの理論を取り入れた探究学習を推進した。シンガポール日本人学校の研修講師や、大学の特別講座なども担当している。22年に『ICT主任の仕事術 仕事を最適化し、学びを深めるコツ』(明治図書)を刊行。またICTのみならず、学校組織のアップデートを目指し、ポリシーメイキングプロジェクトを主催している
(撮影:梅谷秀司)
もともと「中学校でハンドボールを教える先生になりたい」と教員になったが、開智望小学校の立ち上げに誘われて「学校の立ち上げを経験できる先生は100人に1人もいないだろうから、やってみよう」と挑戦することにした。結局その5年後、ヒロック初等部の立ち上げを仲間と決意し、独立するわけで……落ち着かない教員人生である。






























