東大卒の国語塾経営者が選ぶ、国語力がメキメキ上がる小学生向けマンガ7選 『SPY×FAMILY』『ヒロアカ』など有名作品も
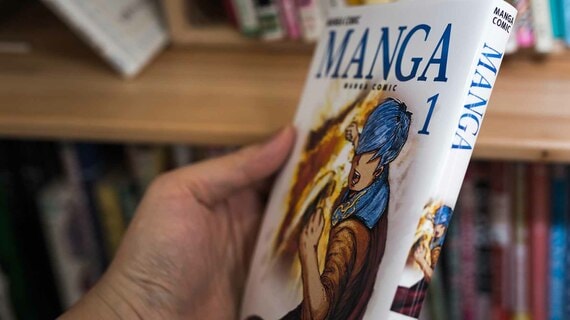
“読むスピード”は“書く”の10〜20倍も速い

1998年茨城県ひたちなか市生まれ。中学生のときに東大を目指すことを決め、高校にも塾にも通わず、通信制のNHK学園を経て、独学で2018年東京大学文科Ⅰ類合格(2次試験は首席合格者と3点差で合格)。2022年東京大学法学部卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。2023年に東大生がつくる国語特化のオンライン個別指導「ヨミサマ。」を立ち上げる。現在、東大生講師150名、生徒数は900名(延べ)を超える規模に成長
(写真は本人提供)
神田氏の経歴は異色だ。幼少期を茨城の祖父母のもとで過ごし、小学校から両親のいる東京へ。中学受験をするも、急きょドイツのミュンヘンで7年間過ごすことに。現地の日本人学校に通う中で、ふと中学3年生のとき「東大に首席で合格してみよう」と思い付いた。
「中学生らしい無邪気な思いつきでした。当時の成績は学年11人中4位でしたが、東大は約400人に1人が入れるかどうか。目指すにはかなり微妙なレベルでした」と振り返る。
このまま普通に勉強していても受からないと考えた神田氏は、「生きているすべての時間を勉強に費やそう」と、通信制高校への進学を選択。図書館などを活用し、独学で猛勉強した末、一浪を経て東京大学文科Ⅰ類にトップクラスで合格した。
こう聞くと、神田氏がもともと勉強に熱心だったのではという思う人もいるだろう。しかし、東大合格を掲げるまでの勉強時間は「1日30分以内」だったという。
「わが家の子育ては実に自由奔放でしたが、たった2つ、絶対的なルールがありました。その1つが、『1日の勉強時間は最大30分』。普通は『最低◯分は勉強しなさい』と言われるものですが、うちでは上限時間が定められていたのです」
幼稚園時代、かけっこや垂直跳びなど、つねに周りと競争させられていた神田氏。小学校時代は周りと比べて運動が得意で、自尊心も高かったという。当然負けず嫌いで、「勉強でも負けたくない」と意気込んでいたが、1日の勉強時間には制限がある。そのため、どうすれば効率よく勉強できるか、常日頃から考えていたそうだ。そこで神田氏が辿り着いたのが、「書く勉強を捨てる」ことだった。
「同じ10分で考えたとき、東大生でも書ける文字数は550字程度、せいぜい文庫本1ページ弱です。それが、話せば3928文字程度、読めば1万58字程度にもなります。読むことで、書くことに比べてざっくり20倍も吸収できるのです。当時の自分も、読んだほうが多くインプットできることに気づき、『ドリルに書き込んでいる暇はない』と悟りました」
































