「家族団欒」を知らない子のために、民泊修学旅行の実態と受け入れ家庭の本音 不登校の生徒にも影響、職業観や勤労観を養う

家族で食卓を囲む時間が減った生徒たち
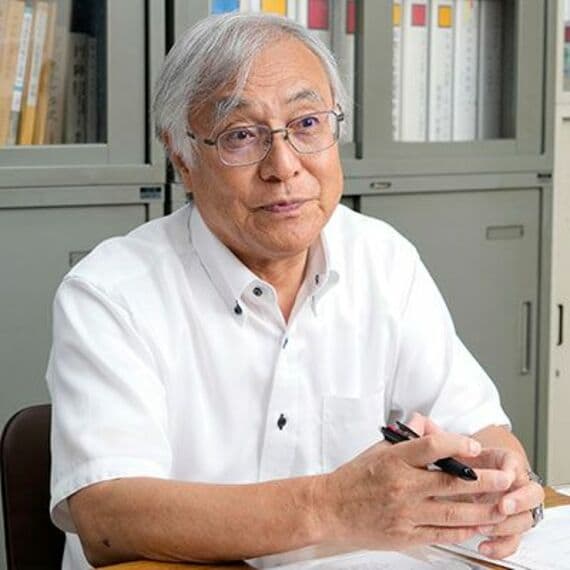
竹内秀一(たけうち・しゅういち)
(撮影:梅谷秀司)
農山漁村民泊(以下、民泊)とは、個人宅に宿泊する旅のスタイルで「農泊」とも呼ばれるが、これを修学旅行に導入する学校が増えている。公益財団法人 日本修学旅行協会 理事長の竹内秀一氏はこう語る。
「民泊修学旅行は、関西の都市部の中学校から広がったと言われています。家族で食卓を囲む時間が少なくなった生徒たちに、家庭の雰囲気を味わってもらおうと始まりました」
民泊修学旅行の動向を遡ると、農林水産省が1990年代から行ったグリーン・ツーリズム政策を源流に、2008年には農林水産省・文部科学省・総務省が連携して「子ども農山漁村交流プロジェクト」を実施。ここでは、5年間で約2万2000校の学校が農山漁村で長期宿泊体験活動を行うことが目標にされた。
「『子ども農山漁村交流プロジェクト』は、予算が削減されながらも現在まで継続されており、民泊を導入する中学校や高校が増えました。当協会の調査では、2013年の民泊修学旅行は中学校が2.6%、高校が1.4%でした。これが、コロナ禍前の2019年には中学校で4.0% 、高校で7.0%にまで増加しています」
物価高やインバウンド増加による宿泊費の高騰も背景
民泊修学旅行では、受け入れ家庭一軒につき4人程度のグループに分かれて宿泊する。中学校の修学旅行では2泊3日が多いが、1泊は民泊、もう1泊はホテルに滞在することが多い。
一般的な流れとして、1日目は入村式などで生徒と受け入れ家庭が対面し、各家庭に移動して畑の見学をした後、ともに夕食を楽しむ。2日目は午前中に農作業などの体験があり、昼食後にお別れ式だ。
民泊の教育的意義について、竹内氏はこう話す。
「滞在先の家庭の多くは、農業や林業・漁業等の1次産業に携わっています。一方で生徒の中には、農業に触れたことがなく、切り身でしか魚を見たことがない子もいます。生業は生徒にとって非日常。異なる価値観は成長のきっかけになります。家庭の雰囲気を味わうだけでなく、職業観や勤労観も養えるのです」
一方で、旅行費用の高騰も要因だ。
「宿泊施設の人件費や光熱費・食材費など、あらゆる価格が高騰しています。同時にインバウンドが回復し、高くても泊まる外国人にターゲットを絞る宿泊施設も増えました。結果、これまでと同じ費用での宿泊は難しくなっています。一般的に、修学旅行費用の4分の3は交通費・宿泊費が占めており、体験費用は全体の1割もありません。今後さらに交通費・宿泊費が上がれば、体験費用の確保はますます厳しくなります」






























