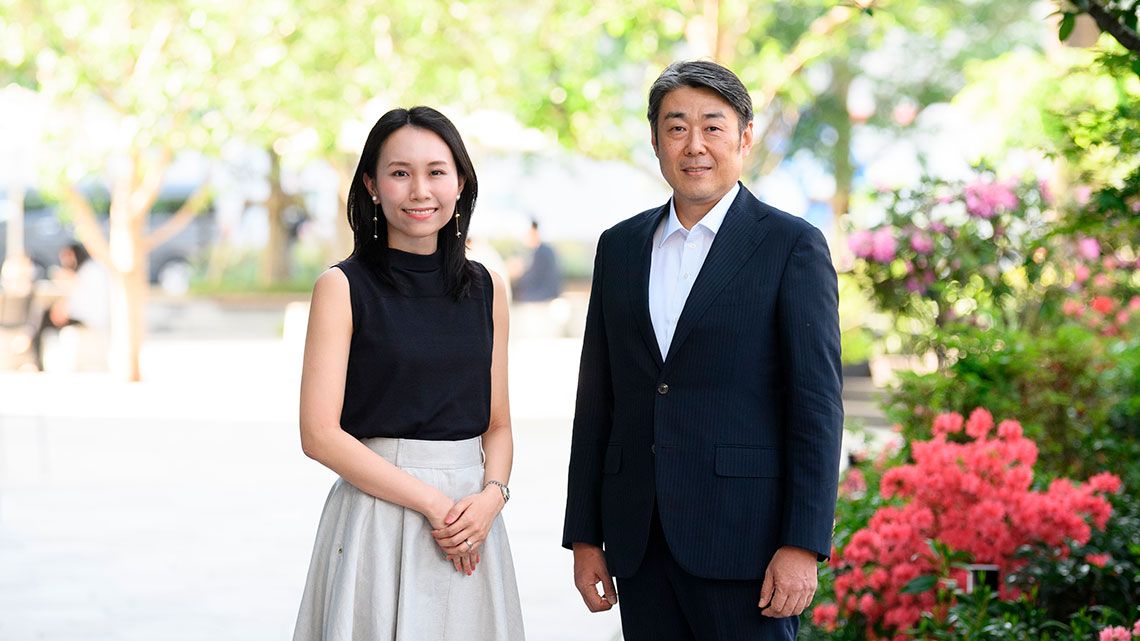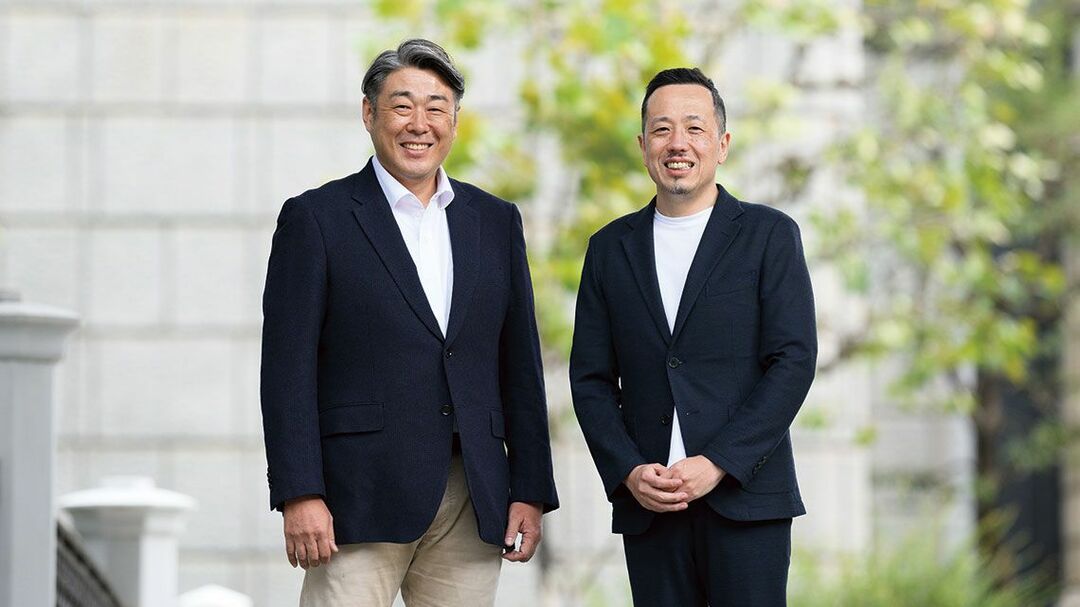売上1.1兆円電子部品メーカー、営業DXの行方 「アナログな手法だけでは限界」…狙う新戦略

「黒子的な存在」の電子部品を扱うメーカーを貫く理念
「Your Committed Enabler」のスローガンを掲げ、2022年4月に発足したパナソニック インダストリー。もともとパナソニック社内でデバイス領域を担っていたが、グループ新体制への移行に当たり、事業会社化して新たなスタートを切った。
具体的にはICTインフラ、FA、車載という3つの重点分野を中心に、約20万の品番を取り扱う。価格帯は1つ当たり数円~数百円のものが中心だ。一方で顧客の裾野は広く、取引先は2万5000社。問屋を通した顧客を含めると、60万社に商品を提供している。
営業担当副社長の寺岡義隆氏は、スローガンに込めた思いを次のように語る。

パナソニック インダストリー株式会社
副社長執行役員 営業担当(兼)営業本部長
寺岡 義隆 氏
「当社が取り扱う電子部品は、黒子的な存在です。そのせいか、以前は顧客の要望にコツコツ応えていくことをよしとするカルチャーがありました。しかし、これからはそれに加え、半歩先に踏み出して顧客が抱える課題の解決と未来の進化の実現にコミットし、共に歩んでいくパートナーになりたい。そのような思いで掲げたスローガンです」
顧客の課題解決に迅速にコミットするには、スピーディーな意思決定が欠かせない。そこで同社は"リアルタイム衆知経営"を目指し、営業、ものづくり、開発設計など各機能のDXを全社レベルで推進している。目指しているのは必要な情報をリアルタイムで集約させて、経営や現場の意思決定に活用することだ。
中でも、大胆な改革に取り組んでいるのが営業部門だ。商品の単価が安く、顧客の規模が大小入り交じる同社。その営業の特性について、営業本部DX推進部長の山田正和氏はこう分析する。

パナソニック インダストリー株式会社
営業本部 DX推進部長
山田 正和 氏
「一つひとつの商売は細い糸です。しかし、それを長く、いくつも紡いで太くしてきた結果、売り上げは1.1兆円(21年度)になりました。DNAとして引き継いできたのは、お客様以上にお客様を知ること。例えば、技術部門の方は案外、自社の購買部門のことを知らなかったりします。私たちは取引先のさまざまな部門の方と関係を築き、真に役立つ情報を提供するなどして信頼関係を築いてきました」
「人」の力で関係を構築する営業手法は、今なお同社の強みの1つである。しかし、アナログなやり方だけでは限界もある。
「電子部品は、スペックの良しあしで選ばれます。スペックの比較は、営業と会って話を聞くよりデジタルのほうが早い。アナログの強みを生かしながらデジタルでサポートしないと、顧客のスピード感に対応することはできない。そうした問題意識の下、営業DXを推進しました」
組織の壁を越えて顧客情報を一元化する意義
営業DXとしてまず取り組んだのは、顧客情報の一元化だ。パナソニックはパナソニック電工、三洋電機などを経営統合した歴史を持つ。そのデバイス事業を担うパナソニック インダストリーは、各社が独自に行っていた顧客管理がそのまま生きており、システムが統一されていなかった。
それだけではない。同じ事業部内でも、サイロ化は進んでいた。DX推進部の隅谷三喜夫氏はこう語る。
「横で情報が共有されずに、商機を逃すこともありました。例えば取引先のキーマンの方とA分野のビジネスでずっとつながっているのに、B分野の当社担当者はその方を知らず、ビジネスをつくれないなど。非常にもったいなかったですね」

この問題を解決するため、分析用の顧客データベースを内製で構築。2021年6月から稼働している。DX推進部の平野将三氏は、「LUCIB」と名付けたこのデータベースについてこう解説する。
「これまで蓄積してきたデータのほか、オンライン展示会やWebサイトなどデジタルの顧客接点も含めてデータを集約。事業部の壁を越え、横断的に把握できる環境が整いました」
ただし、データを可視化して終わりではない。集約したデータを分析して営業活動に生かすことが真の狙いだ。「そこで浮上してきたのが、実行系の基盤となるCRMプラットフォームの導入です。分析用のデータベースが完成する前から検討を開始し、議論の末、HubSpot社のマーケティングオートメーションツールの導入を決めました」(平野氏)
「ユーザー企業を顧客目線にさせる」HubSpotの底力
営業DXを実現する中核のツールの1つとして、数ある選択肢の中からHubSpotを選んだことには伏線がある。実は9年ほど前から、パナソニックの一部の事業部がHubSpotを活用していたのだ。2013年に導入したメカトロニクス事業部の中澤剛士氏は、使用した感想をこう明かす。
「HubSpotは、直感的に使えるUIがいちばんの魅力。そのおかげで、社内の横展開も容易でした。例えば、HubSpotのデータを基にメールマガジンの文章を工夫しようとなれば、成功した部門のノウハウをスムーズかつ簡単にほかの部門に共有できます」

産業デバイス事業部の水崎陽一氏は、HubSpot社のスピード感に驚いたという。
「使い方に迷ってHubSpot社のカスタマーサポートにチャットで尋ねると、『こうすれば解決します』『現在その機能はありませんが、実現するためにどのような技術的な解決方法が考えられるか、技術部門に確認します』と即座に回答が来ました。その徹底された顧客中心の対応に、当社のサービスもこうありたいと考えるようになりました。顧客目線を実感できる学びの多いツールだと思います」
もちろん、事業部によってはほかのツールを導入しているところもあった。なぜ全体のプラットフォームとしてHubSpotを選んだのか。
「顧客との接点から情報を集めて分析し、迅速に行動を起こすことで顧客体験を高めていくことが営業DXの目的です。この大きなビジョンを実現するために最適だったのがHubSpot。私たちも手探り状態でしたが、パートナーのクリエイティブホープ社から導入の支援を受けて安心できました。HubSpotは製品の進化スピードが非常に速いのですが、当社の事情に精通しているクリエイティブホープ社の手厚いサポートによって、それに追従できることがわかって期待感が高まり、選定に至りました」(山田氏)

執行役員 シニアコンサルタント
篠原 誠 氏
カスタマージャーニー全体を顧客目線で最適化するマクロの視点と、日々のマーケティングや営業活動で使いやすいというミクロの視点。両方の視点から同社のニーズを満たすのがHubSpotだったわけだ。
いつどんなアクションを取ると顧客体験が向上するか?
もともと一部の部署でスモールスタートしていたHubSpotの導入は、自社データベースの本格稼働時点で営業組織全体での運用に拡大していった。ベースとなる顧客情報と、それを生かすための武器がそろったことで、顧客体験はどう変わったのか。
「それまでは人が一対一でアナログ対応していたため、お客様をお待たせすることもありました。しかし、今はデジタルで複数の対応を同時に動かせます。その結果、顧客が望むタイミングで当社側からアプローチできた事例も増えてきました。どのタイミングにどのようなアクションを取ると顧客体験が向上するのか、これからさらに模索していきます。それをデータで検証できる環境が整ったことは大きい」(中澤氏)
顧客一人ひとりにパーソナライズするアプローチが合っている事業部がある一方、全体の売れ筋をデータ分析しビジネスに生かしているケースもあるという。事業部によって濃淡はあるものの、現場では早くも効果を実感しているようだ。顧客起点のマーケティング・営業をさらに深化させるとともに、海外展開や他部門との連携も視野に入れる同社。

取締役 シニアコンサルタント
藤井 廣男 氏
「個人情報保護の観点も踏まえ、海外の関係会社とのデータ連携については、そのあり方を模索している状況です。情報をどのように活用すれば顧客体験が高まるかというノウハウの共有に対する期待は大きいです。また、同時に進めているものづくりや商品開発、経営管理のDXと連携することで、顧客の声をタイムリーにほかの部門に届けていきたい」と、山田氏は期待を寄せる。
製造や開発の面からも"リアルタイム衆知経営"を実現していく秘訣は、事業部によらず全社で取り組む「顧客体験の向上」にあるようだ。