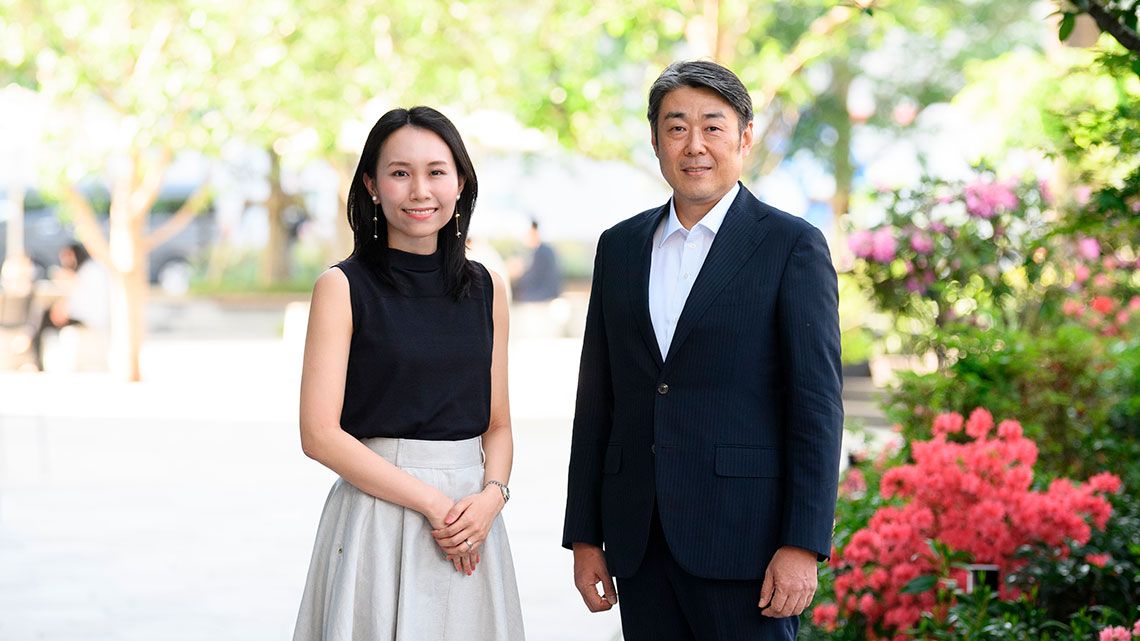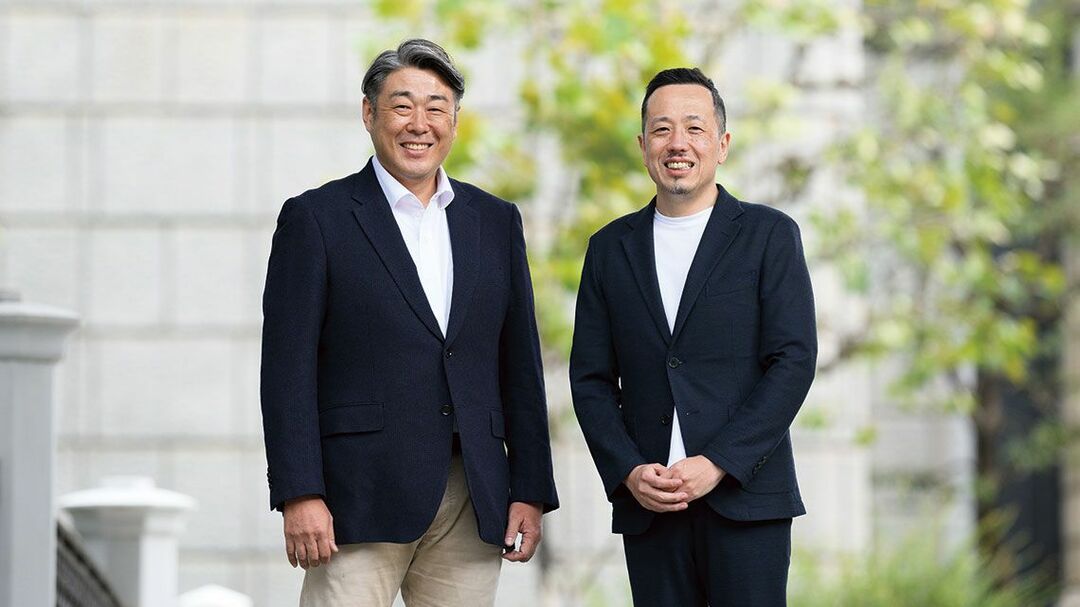「右脳思考」でつくる、ビジネス×アートの戦略 「ロジックだけ」で正解を導ける時代は終わった

※HubSpot Research「Consumer COVID Survey」2020年4月実施
情報が玉石混淆の今、ブランドはフィルターの役割を果たす
――顧客が、企業の「信頼性」を重視する傾向が強まっています。これをどのように分析していますか。

教授
内田 和成
内田:2020年の春、日本中でマスク不足の騒ぎが起きましたね。やや落ち着いた頃、海外製マスクが入ってきても、多くの消費者は「日本製がいい」と望みました。具体的な性能差がなくても日本製が望まれたのは、「メイド・イン・ジャパン」に高い信頼性があるから。
私が注目しているのは、ブランド形成プロセスの変化です。かつては企業がマス広告を通して情報を発信し、それを消費者が見聞きすることでブランドが形成されました。しかし今、消費者は企業発の情報をあまり信用しなくなり、口コミやSNSを頼るようになった。ブランド形成の経緯が複雑化している。これは非常に大きな変化です。
伊佐:人々が情報を得る経路が複雑になるほど、ブランドの重要性は増します。インターネット上の情報は玉石混淆で信頼性を見抜きにくく、真偽を一つひとつ調べるのは難しい。フィルターの役目を果たすものが必要になりますが、それがブランドではないでしょうか。
内田:そうですね。私を含めほとんどの消費者は、大量の情報の真偽を瞬時に見抜く力は持ち合わせていません。さらに消費行動には感情が入りますから、すべてを客観的に判断することはできず、何かしらのフィルターに頼らざるをえません。そこにブランドが生きてきます。
――そもそも、「ブランド」とは何なのでしょうか。

共同事業責任者
シニアマーケティングディレクター
伊佐 裕也
伊佐:企業が「わが社の考えはこうです」「うちの商品はこんなにいいものです」と広く情報を発信すれば、ブランドが出来上がると考えている人はいまだに多いかもしれません。しかし、実際に買ったとき、使ったとき、サポートデスクに連絡したときなど、人々が企業とタッチするすべてのポイントにおいて、ブランドの捉えられ方は変化します。つまりブランドとは企業のマーケティング部門のみがつくるものではなく、顧客をはじめ、企業とそのステークホルダーとのすべての接点で醸成されていくものだということです。
内田:よく言われるのが、ブランドは「約束」だということ。例えば車なら、安全性や乗り心地のよさを顧客に約束して、それが無事守られたときに初めてブランドになる。伊佐さんがおっしゃるように、約束する相手は顧客に限りません。取引先や小売店、あるいはノンユーザーとの間でも約束をして、愚直にそれを実行していくことが、ブランドの強さを育んでいきます。
「八方美人」ではブランドが成り立たないと腹をくくるべき
――企業と顧客のつながり方が複雑化している中、企業は「約束」をどのように果たしていけばいいでしょうか。
内田:商品により、やり方は異なります。セグメントが明確な商品は、従来型のマーケティング手法が比較的通じやすい。一方、万人向けの商品は、情報の入手経路が複雑になったことで非常に難易度が高くなりました。
例えば100人中90人が好感を持ってくれたとしても、残り10人の中にインフルエンサーがいて「このブランドに嫌な思いをさせられた」と発信すれば、一気にイメージが毀損されてしまう。「9割の人が好感を持った」というデータに満足するのではなく、つねにターゲットの反応を見ながらコミュニケーションをチューニングする必要があり、ここに感性が求められます。本当に強いブランドができてくると、コアユーザーが自然とスポークスマンになって新規ファンを開拓してくれます。
伊佐:もちろん認知度を数字で見ることも大切です。しかし今は、広告に触れた100万人が、100万通りの受け取り方をする時代。先ほど「フィルターとしてのブランド」と言いましたが、自社が本当に価値を提供できる層の人々に自社を見つけてもらうためには、企業としてどのような行動をし、メッセージを発信していけばいいのか。その判断には感性やセンスといった右脳的なものが必要でしょう。
内田:まさにそうで、これを私は「右脳思考」と呼び、数年前から提唱しています。「ブランド=認知度」だった時代とは違い、「このテレビ番組に広告を出せばこのくらいの人に見られる」といったロジックだけで正解が導けるケースばかりではありません。

伊佐:ブランディングの観点で言うと、質のいい製品を持っていることは当然として、自社の価値基準や企業としてのあり方、思想などに共感してもらうことが必要だと思います。「当社は従業員を大切にします」と掲げている企業の従業員が、不満ばかりを抱えて働いていたら、ステークホルダーは約束が破られたと感じますね。例えば車なら「うちは高級感」「うちは安心感」というように、自社の価値基準やユニークさを明確にし、徹底的に行動に落とすこと、そしてそれをブレずに続けることが大事だと思います。
内田:まさにおっしゃるとおりで、ステークホルダーとのあらゆるタッチポイントで「一貫性」を持つことがカギです。これだけ顧客の購買行動や考え方が変わってきている以上、売り手である企業も、変わらなければならないと思います。そして「自社の価値基準」を定めるとき、経営者にわかっていてほしいのは、旗幟(きし)を鮮明にしないといけないということ。例えば株主至上主義なのか、顧客ファーストなのか、従業員を第一とするのか。どっちつかずでは結局、誰とも何の約束もできない。八方美人では生き残れない時代だと、腹をくくるしかありません。
信頼づくりには「アート」と「サイエンス」の両方が必要
――信頼関係をつくるためには、ロジックだけではなく「感性」も重要です。感性はどうすれば身に付けられるのでしょうか。
内田:感性は生まれ持ったものに加え、自分の頭で考えて挑戦し、痛い目に遭いながら、磨かれていくものです。誰もがオールラウンダーになる必要はありませんから、まずは自分がどんな感性に長けているのか観察しましょう。そして感性を発芽させるのは、何よりも「自分が物事をリードしていく経験」。受け身の姿勢で言われたことをこなし続けるだけでは、感性を磨き目覚めさせることはできません。
伊佐:組織としては、若手社員にも積極的にチャレンジする経験を積ませるべきですね。

内田:はい。小さなチームのリーダーでいいから、若いうちに経験させるべきです。それで自分の感性を花開かせた人が増えれば、組織全体が右脳を使いこなせるようになるでしょう。一方で、今は、新卒で入社した企業に定年まで勤め上げるのが唯一の正解だった時代とは違います。さまざまなバックグラウンドを持つ人材たちと1つの価値観を共有するには、仕組み化も必須です。
伊佐:顧客が自社と関わる際の“体験の質”を上げていくために、当社では「アートとサイエンスの両方が必要」と提言しています。「アート」とは、ここまでもお話ししてきた「企業の価値観」や「企業文化」など右脳的感覚で磨いていく部分。当社においては「Solve For The Customer.」(顧客の成功のために尽くす)という価値観がこれに当たります。そして、この価値観をどうやって体現するかという段階で「組織の連携」「システムの連携」などの仕組み化、つまり「サイエンス」が必要になってきます。
内田:右脳と左脳、両方を使うからこそ力を発揮できるんですよね。例えばデータ収集を左脳で行い、そこから右脳で示唆を得て何かを発想し、そしてそのアイデアを左脳で具体的な施策に落とし込んでいく。「左脳→右脳→左脳」のサンドイッチ構造が理想です。
さらに言えば、今後はデータを基に事後的に対応する方法は通用しなくなるでしょう。「社会にこんな変化を起こしたい」というビジョンを持ち、その実現のためにデータを活用しないといけない。そういう意味では、右脳を使うことがビジネスの第一歩になるかもしれません。
伊佐:自社のビジョンや価値基準を明確にすることが、ブランドづくりの出発点になるというわけですね。右脳思考を実践するうえで、これは重要な考え方だと思います。
>顧客体験の質向上を支援。HubSpotのCRMプラットフォーム についてはこちら