高校の新しい情報科、一斉授業だけではNGな理由 元文科省・鹿野利春「"やめる勇気"も大切」

全員「情報Ⅱ」まで学ぶと「ジェンダーギャップの解消」に
――2022年度4月から新しい情報科の授業がスタートします。これまでの学びとどう異なるのか、ポイントをお聞かせください。
まず、従来の「社会と情報」と「情報の科学」を「情報Ⅰ」に集約した点が大きなポイントです。日本人の素養として、両方の領域について全員が学びましょうというわけです。目標は「問題の発見・解決」で、そのためのツールとして3つを扱うことになりました。
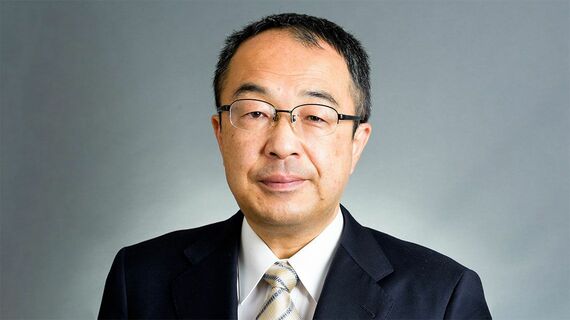
京都精華大学メディア表現学部教授
石川県の公立高等学校、教育委員会を経て2015年に文部科学省の高等学校情報科担当の教科調査官を務める。これまで新学習指導要領「情報科」および解説の取りまとめ、「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」の教員研修用教材や「情報」実践事例集の取りまとめ、GIGAスクール構想、小学校のプログラミング、情報活用能力調査などに関わる。21年4月から現職。現在、文部科学省初等中等教育局視学委員(STEAM教育)、経済産業省「デジタル関連部活支援の在り方に関する検討会」座長、国立研究開発法人情報通信研究機構主催「SecHack365」実行委員長、大阪芸術大学アートサイエンス学科客員教授も務める
(写真:本人提供)
1つ目は、「プログラミング」。小中学校では授業が始まっていますが、引き続き高校でも全員必須で学びます。
2つ目は、「情報デザイン」。これまではWebページやポスターを作成する際の工夫レベルの内容でしたが、今回からは例えば「情報を論理的に構造化したうえでWebサイトのデザインに入っていく」ことができるような、発展的かつ体系的な内容になりました。
そして3つ目が、「データの活用」。新学習指導要領では、数字をベースに物事を考える力の育成に重きが置かれています。そのため、小中高を通して統計教育が強化されているのですが、高校の新学習指導要領の解説には、「情報Ⅰ」と「数学Ⅰ」との連携が今まで以上に詳細かつ具体的に示されています。「情報Ⅰ」も「情報Ⅱ」も2単位しかないので、数学と連携することで相乗効果のある学びが期待できます。また、より発展的な内容となる選択科目「情報Ⅱ」には、「データサイエンス」が盛り込まれ、「数学B」と連携することになっています。
私の思いとしては、文理関係なく、高校で「情報Ⅰ」と「情報Ⅱ」を学び、さらに大学に進んでデータサイエンスをしっかり学んでいただけるといいな、と。全員が学ぶことで、ジェンダーギャップの解消にもつながると考えています。
中学で生じた「格差」は授業を変えればプラスにできる
――情報科担当の教員に求められるスキルや心構えについてお聞かせください。






























