湘南学園はなぜ「ESD」と「BYOD」が根付いたのか 前例がない中、挑戦を「正解」に変えるには?

実は約30年の歴史がある「総合学習」
湘南学園中学校高等学校は、独自の「湘南学園ESD」を掲げて教育活動を展開している。その柱となるのが、「総合学習」だ。学年ごとに学びのテーマを設定しており、生徒たちは企業や行政、NPOなどの協力を得て、体験学習やフィールドワークに取り組む。実は、この総合学習は約30年の歴史があるという。校長の伊藤眞哉氏は、こう振り返る。
「当初は『特別教育活動』、通称『特活』という名称で、私が新卒でここへ来た頃に始まりました。狙いは、中1から高3までの6年間の発達段階に応じ、多様な人との関わりの中で自分なりの視点や考え方を磨いていくこと。このコンセプトは今も変わりません」
やがて学習指導要領の中に「総合的な学習の時間」が設けられ、ESDの観点も盛り込まれるようになっていった。多様性を受け入れるベースを育む特活は、まさに国連が提唱するESDの考え方にマッチしていたため、2013年にユネスコスクールに加盟したという。これを機に「湘南学園ESD」を打ち出し、特活も「総合学習」へと名称を変えた。
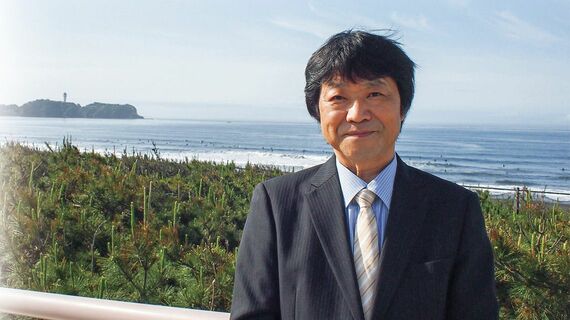
1965年生まれ。大学卒業後、同学園で国語教員となる。2017年にICT導入委員会の責任者を担当。20年から中学校高等学校校長
ESD浸透のカギは「推進委員会」
この頃、新たにできた校務分掌が「ESD推進委員会」だ。委員の経験があるICT主任・国語担当の山田美奈都氏はこう説明する。

「現在、各学年に1名ずつ委員がいて、毎週集まっています。すべての教育活動をESDの観点からチェックしたり改善したりするほか、委員も学び合い、それを各学年でシェアするのが仕事。他校からしたら、特殊な活動ですよね。でも、うちにESDの文化が根付いていったのは、この委員会の存在が大きいのではないかと思います」
例えば総合学習。以前はインプット型の活動が多かったが、ESD推進委員会で「自ら行動を起こすことも重要ではないか」という話になり、4年ほど前からPBL(Project Based Learning・課題解決型授業)にも力を入れ始めた。
中学2年生が地元の宝製菓と共にお菓子のパッケージデザインや販売を行ったプロジェクトに始まり、クラウドファンディングで資金調達を図るなど徐々にPBLは進化。課外活動としての自主的なプロジェクトも発生するようになった。例えば児童労働根絶の啓発に取り組む「チョコプロ」や、「SDGsが達成された世界」をマインクラフトで作るプロジェクトなどがあり、学年を横断した形で有志たちが活動している。

長年培われてきた校風も、ESDの浸透に関係がありそうだ。同学園は、「毎日のすべてが学び」と捉え、生徒1人ひとりの主体性を大切にしているという。
































