行政DXの「ジレンマ解消」に欠かせない視点とは 「自治体施策の成功と失敗」セミナーレポート
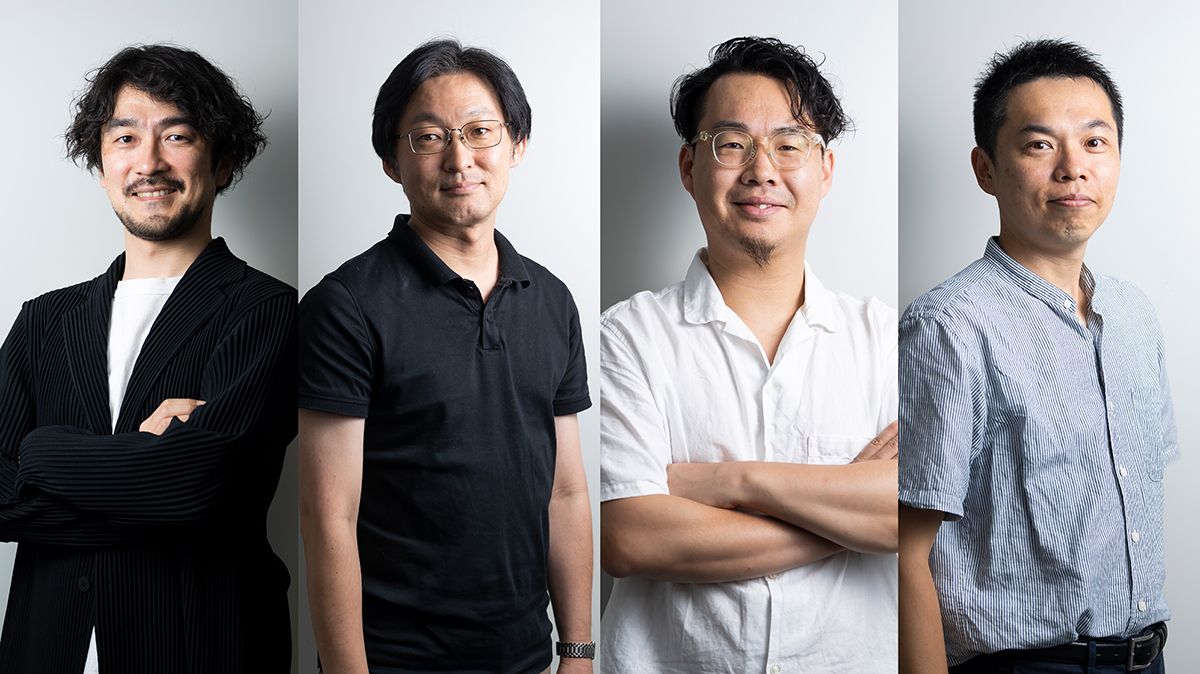
【ジレンマ1】市民の利便性は向上したが、行政現場の負担が増した
行政DXで今、ホットな取り組みの1つはマイナンバーカードだろう。政府が2020年12月に策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」でも、普及促進が重点取り組み事項となっている。
本セミナー「行政DXのジレンマ」でも、まずはそのことが話題に上った。デジタル庁参与でもある構想日本・総括ディレクターの伊藤伸氏は、マイナンバーカードの取り組みを積極的に進めることで、市民の利便性が格段に向上する事例が出ていると語った。

総括ディレクター(理事)
デジタル庁参与
伊藤 伸氏
「例えばある市では、23年4月末時点で交付率が9割を突破しました。かなり早い段階から市長が陣頭指揮を執って、強力に普及促進を図っていた成果だと思います。オンライン行政手続きやキャッシュレス決済の普及も進んでおり、例えば家にいながら戸籍謄本も取得できるようになりました。デジタル庁が目指す『行かない市役所、書かない窓口』の好事例の1つです」(伊藤氏)
これだけ聞くと行政DXがスムーズに成功しているようだが、気になるのは新システムへの移行による、窓口など行政現場の負担の実態だ。モデレーターの構想日本の尾中健人氏は、「マイナンバーカードでも、裏側を担う現場の作業は煩雑になって『何のためのDXなのかわからない』との声もよく聞く。うまくいっている自治体ではどうなのか」と投げかけた。
伊藤氏はそれに対し「その市の職員に話を聞くと、自分たちの負担軽減より市民の利便性向上を最優先にするという考えが念頭にあった」と回答。加えて「DXによって創出する価値を、どう生かすのか明確にしたことが成功の要因の1つではないか」と話した。

戦略・デザインコンサルティング統括部
ディレクター
坪井 壘氏
データ連携基盤の構想策定や、DX人材育成メニューの開発などを多数の自治体と進めるNECの坪井壘氏はこれに対し、「提供価値をしっかり定めたうえで、便利になったという実感を積み上げていくことが、DXを成功させる大きなポイントだと思う」と語った。
「自治体の皆様とDXについて議論をして感じるのは、テクノロジーの導入が主題になりがちだということ。最も優先すべきは導入そのものではなく『何を実現させるためにDXを進めるのか?』という目的意識です。そこが定まって成果が上がれば徐々に業務も効率化し、負担軽減も進んでいくと思います」(坪井氏)
【ジレンマ2】民間の活用は有効だが、コストがかかる
一方、坪井氏と別の視点で行政DXを成功させる方法に言及したのは、自治体と市民をつなぐコミュニティアプリ「いれトク!」を提供するEXxの青木大和氏だ。

代表取締役CEO
青木 大和氏
「一緒に取り組む自治体には、弊社の社員が週2日ほど常駐するケースがありますが、さまざまな部署の方がご相談に来てくださり、DXへの関心の高さを感じています。また弊社は、住民が主体的に参加したくなる街づくりをミッションとしていますので、必要に応じて他社サービスの活用なども提案します。それがよい結果につながることも多く、民間が行政の現場に入ることでDXが大きく前進するという手応えを感じています」(青木氏)
官民連携はそれほど目新しい取り組みではないが、「要件定義の際に、技術力やノウハウのない行政側がうまく民間を活用しきれていないケースも多い」と尾中氏は問題提起する。「人事異動などで引き継ぎがうまくいかないから、『外部に一気通貫で任せましょう』となっても、『この機能を使うだけでこんなに金額がかかるのか』といった悩みをよく聞くのはなぜか」と投げかけた。

プロジェクトマネージャー
尾中 健人氏
それに対し、構想日本で行政事業レビューに力を注いできた伊藤氏は、「とりわけITシステム関係の事業はコストがかさんでいく傾向がある」とし、「具体的に事業内容を見ていくと、ハイスペックなシステムのうち、ごく一部しか使えていないことが多い」と明かした。
「なぜそんなことが起きるのかというと、仕様書の段階で必要以上のスペックになっているからです。専門的な知見がないため、要件定義から仕様書の作成までベンダーやコンサルタントに頼っている自治体があることが原因です」(伊藤氏)
この問題にEXxの青木氏は、補助金や単年度予算で事業に取り組む行政の構造も関係していると指摘。「基幹システムの構築では国から大きな補助金の交付を受け、その後の運用は自治体の財源で賄うケースをよく見る」と話す。
「初期投資は大きいけれども、その後はコストをかけられないわけです。現在、ITシステムはSaaSに移行しているのが世界のトレンドですが、費用は月額払いがスタンダードですので、移行したくてもできないジレンマがあるのではないでしょうか」(青木氏)
そうした状況に、ベンダー側として危機感を持っているとNECの坪井氏は語る。「Future Creation Design™」と銘打ったDXデザインコンサルティング・サービスを2020年に強化した背景には、構造的な変化を後押ししたいという思いもあったという。
「本当にするべきことは何かを厳選し、アジャイルに動かせるように、初期費用はもちろん全体的なコストも抑えられる方向へNECは舵を切っています。具体的には、単年度の予算ですべてを完了させるのではなく、将来的な目標達成に向けたロードマップを作成し、必要に応じて随時自治体側と細かく目線合わせを行いながら、迅速に対応していくことに力を注いでいます」(坪井氏)
【ジレンマ3】完璧さとスピードを同時に求められる
だが、日本の行政においては、さまざまな取り組みにおいてミスを最小限に抑えるのが重要となる。SaaSのような「リリース最優先で、バグは随時修正していく」という考え方へ移行するのは難しいだろう。しかし、そうした中でも「日本の行政の中にある『無謬性』の考え方から脱却し、スピードを重視しながら、迅速に修正を加えていく発想が行政DXには必要」と伊藤氏は話す。
また青木氏はそのような課題に対して、自社のサービスをはじめとした自治体間でのナレッジ共有の仕組みも有効活用してほしいと話す。
「例えばわれわれのサービスでは、A市で成功した取り組みを翌日にはB市で導入するといったシームレスな対応が可能です。こうしたナレッジの共有をより多くの自治体間で行うことができれば、システムや人的エラーなどを最小限に抑えつつ、有効な取り組みをスピーディーに進めることができます」(青木氏)
その基盤として期待されているのが、ガバメントクラウド(政府共通のクラウドサービスの利用環境)を活用した自治体システム標準化だ。ベンダー側もこれを活用した開発を進めることで、迅速かつ柔軟なシステム構築が可能となる。NECの坪井氏は、自治体ごとに異なる優先順位に合わせたシステムやサービスの開発が可能となり、地域活性化にもつながると期待を込める。
「そもそも自治体の特性によって、求められるサービスは異なります。山間部が多ければMaaS関係のサービスが必要になりますし、どの地域でも重要な防災への取り組みも、ロケーションによって内容は変わります。そうした独自性に対応するには、民間も1社単体で自治体と向き合うだけでなく、さまざまな強みを持った事業者が連携するのが有効でしょう。それこそ、EXxのような事業者と、オープンイノベーションのような取り組みを自治体の領域で広げていくことが、行政DXを推進させ、地域の活性化につながると思っています」(坪井氏)
ユーザーの生活にデジタルの恩恵をもたらすことが行政DXの大きな目的だが、変革期には混乱がつきもの。パラダイムシフトが起きているといわれる今はなおさらだ。
「ユーザーファーストで対応を進めることで、行政職員の負担は増えているけれども、それは一時的なもの。いずれは標準化されていくというマインドセットが必要かもしれない」と尾中氏は議論をまとめ、さらに「行政職員の皆さんだけに頑張っていただくのではなく、ベンダーなどいろいろな民間の力をうまく活用することが重要」と呼びかけた。
誰1人取り残されることのないシステムの実現が求められるが、乗り越えなければいけない課題やしがらみが山積する行政DX。変革期ならではの「ジレンマ」を乗り越えるためには、組織や属性を超えて知恵を合わせていくことが成功へのカギとなる。




 木村屋×NEC「100年企業タッグ」で商品開発に挑戦
木村屋×NEC「100年企業タッグ」で商品開発に挑戦 大東建託「スモールスタートのDX」を推進した理由
大東建託「スモールスタートのDX」を推進した理由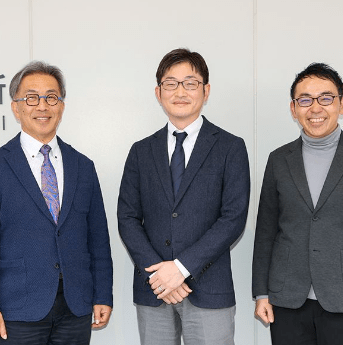 千曲市DX「職員の機運醸成」を最重要視した理由
千曲市DX「職員の機運醸成」を最重要視した理由 DXは「止まらない社会インフラ」をどう変えたか
DXは「止まらない社会インフラ」をどう変えたか ノーリツがDXで「人材定義」を優先させた深い訳
ノーリツがDXで「人材定義」を優先させた深い訳 データマネジメントへの挑戦が人材成長を加速させる
データマネジメントへの挑戦が人材成長を加速させる 「NEC×トレジャーデータ」戦略協業で加速するDX
「NEC×トレジャーデータ」戦略協業で加速するDX ブラザー工業がDXで強化したセキュリティ戦略
ブラザー工業がDXで強化したセキュリティ戦略 安全性と利便性を両立「高精度の生体認証」の正体
安全性と利便性を両立「高精度の生体認証」の正体 「サイバーセキュリティ最前線」舞台裏の緊迫
「サイバーセキュリティ最前線」舞台裏の緊迫 地域活性化のカギを握る観光DXの可能性
地域活性化のカギを握る観光DXの可能性 経営層の意識改革と「DX人材」育成を推進するには
経営層の意識改革と「DX人材」育成を推進するには 組織全体で「イノベーション創造力」を高める
組織全体で「イノベーション創造力」を高める デジタルの力でモノとコトを融合し新価値を創造
デジタルの力でモノとコトを融合し新価値を創造 カゴメとNECが共創で進める「変革への第1歩」
カゴメとNECが共創で進める「変革への第1歩」 NECは「DXの実践と深化」を、ここまで徹底する
NECは「DXの実践と深化」を、ここまで徹底する

