「子どもの読解力」問題解決能力との意外な関係 先生がいなくても学び続けられる基盤とは
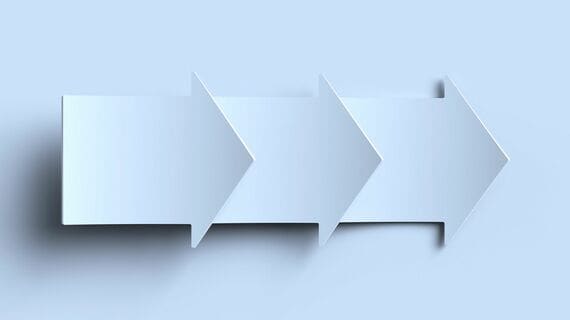
読解力とは、問題解決のプロセスそのもの
「読解力が低下したと聞くと、多くの方は国語の教科書に載っているような文学作品を読む読解力が落ちたと考えるのではないでしょうか。しかし、PISA2018で問われた読解力は、従来考えられてきたものとは異なるものなのです」と語るのは東京学芸大学教育学部の高橋純准教授だ。
PISA2018の読解力を問う出題の1つが、ある大学教授のブログだった。ブログには著者の体験や経歴に加え、イースター島のモアイ像に関する話や本の話など、さまざまな情報が盛り込まれている。それを読んで、問いに答えなくてはならない。
「問題を解くには、①雑多な情報の中から必要な情報を探し出す②情報を理解する③熟考するというプロセスが必要となります。つまり、この一連のプロセスこそがPISA2018で問われた読解力なのです。この①②③のプロセスごとの各国の順位も明らかになっていて、日本は①が18位、②が13位、③が19位という結果となりました」
この結果は読解力の定義が変化したことと無関係ではないようだ。では、なぜPISA2018ではこうした読解力とそのプロセスが重要視されるようになったのだろうか。
「受験者をふるいにかける入学試験と違って、PISAは学習到達度を測るもの。ですから、世の中の変化やニーズを受けて試験の内容が大きくリフォームされたのです。今、世界は異常なスピードで超情報化社会に変化しており、求められる学力や資質・能力が変わってきています。その中で問われた読解力の①課題を持って情報を集め②それを理解し③評価して熟考するというプロセスは、実は問題解決のプロセスそのものなのです」
つまり今、世界で求められている読解力とは問題を解決する力とも言い換えられるだろう。その重要性を言い当てているのが、小学校ではこの4月から導入された新学習指導要領だ。
具体的には、「言語能力、情報活用能力(情報モラルを含む)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から、教育課程の編成を図るものとする」とある。
「つまり」と高橋氏は続ける。「問題解決能力は言語能力や情報活用能力とともに教科の枠を超えたすべての基盤となるのです」。
空欄を埋める力から気づいて行動する力へ
GIGAスクール構想によってICT環境の整備が促されているが、これも問題解決能力の育成と無縁ではない。






























