「相性悪いから友だちやめる」MBTI誤解に波紋、教員が児童生徒に適用する例も 不安で不眠症になることも、低年齢ほど影響大

「貧乏になりやすいタイプ」と誤った情報で不安に──
「自分はMBTIの◉◉タイプだから、◆◆タイプの子と相性がいいらしい」
「MBTIの▲▲タイプは貧乏になりやすいらしい、★★タイプは自殺しやすいらしい」──
今、「16Personalities」と呼ばれるインターネットの無料診断を受けた子どもたちが、自分のタイプを歪んだ形で解釈する事態が起きている。しかし、この「16Personalities」診断は、人間の性格タイプを16に分けて英文字4つで表記する点で、国際規格に基づく性格検査「MBTI」と共通しているものの、実際は「MBTI」とはまったくの別物だ。
約20年前、日本にMBTIを紹介した日本MBTI協会代表理事の園田由紀氏に、MBTIをめぐる昨今の状況を尋ねた。
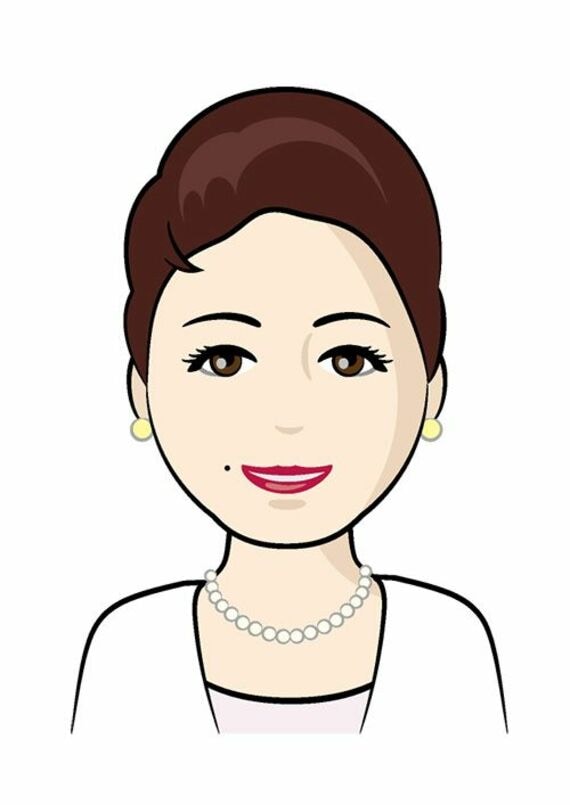
日本MBTI協会認定MBTIマスタートレーナー、認定臨床心理士
東京大学大学院医学系研究科非常勤講師、京都大学大学院医学研究科非常勤講師。株式会社PDS総合研究所代表取締役社長。日本版MBTIの研究開発を手掛け、日本におけるMBTIの普及に努める。『MBTIタイプ入門』(JPP株式会社)など著書・訳書多数
(画像は本人提供)
「MBTIは、スイスの心理学者であるカール・G・ユングのタイプ論をベースにアメリカのマイヤーズ母娘が開発しました。一方の16Personalitiesは、その後イギリスで作られたまったく別のテストです。問題は、MBTIのオリジナルである英文字4つの表記を、16Personalitiesがそっくりそのまま転用したことでした。
16Personalities側は『あくまでMBTIのいいとこ取りをしただけで、MBTIではない』『16Personalitiesはビッグファイブ理論をベースにしている』などと主張していますが、ベースの理論が異なる以上、受検者の利益のことを考えたら、結果表記も異なってしかるべきと思うのです」
16Personalitiesが日本に流れてきた当初は、日本語訳が不自然だったこともあり、実はそれほど問題視されていなかった。しかし昨今はAIの翻訳精度も向上し、想像を超える勢いで広がりを見せている。日本語のほかにも多くの言語に訳されており、各国で、MBTIとの混同をおこし広がっている状況だ。日本では2023年ごろから、MBTIと勘違いして16Personalitiesの無料診断を受けた人から、日本MBTI協会に多数の相談が入るようになったという。
「自殺しやすいタイプと言われて不眠症になってしまった」
「母親には向かないタイプと言われて自信をなくしてしまった」
































