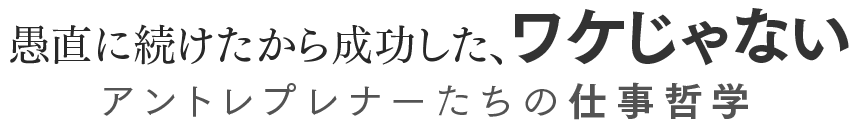Access Ranking
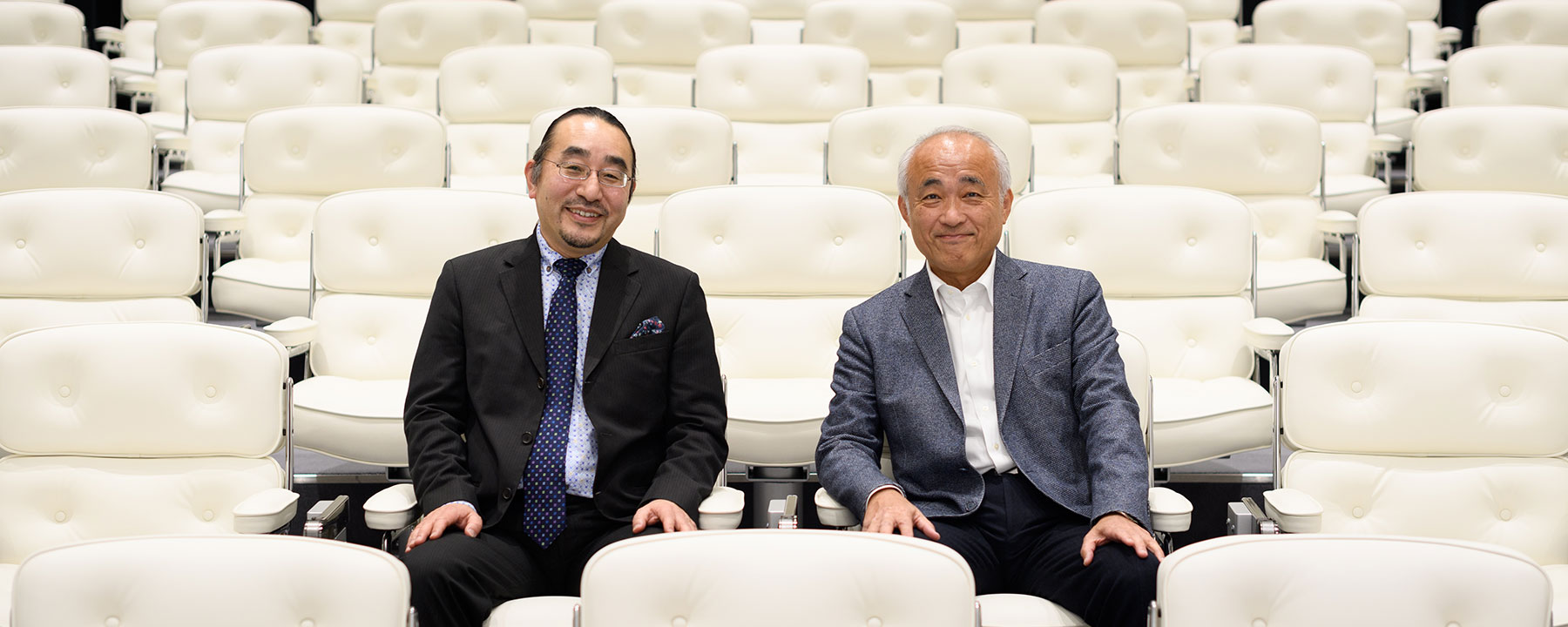
29
ペプチドリーム 共同創業者・取締役会長窪田規一
共同創業者菅裕明
アントレプレナーではない
ベンチャーの中でも、とりわけ生き残りが困難といわれるバイオ分野。そんな常識を覆すように、2006年の創業後、13年に東証マザーズに上場し、15年には東証1部上場を果たしたのが、創薬バイオベンチャーのペプチドリームだ。現在も好調な業績を維持し、高い利益率を誇っている。19年11月にはその功績が認められEYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーの日本代表に選出された。窪田規一会長と菅裕明東京大学教授という2人の創業者に迫る。
飲んで楽しい人でなければ
長く続けられるわけがない
――昨年11月、EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー(EOY)日本代表に選出され、今年モナコでの世界大会に出場されます。まずは受賞のご感想をお聞かせください。
窪田受賞後に多くの反響があり、とんでもない賞をいただいたと感じております。受賞時に会場の皆様の前で「モナコの世界大会で世界一になる」と宣言しましたが、今は少しだけ後悔しております(笑)。
菅ペプチドリームとしてはこれまでも数々の賞をいただきましたし、私自身もアカデミックな賞をいただいてきましたが、今回のように大きな反響のある賞をいただく機会はそうありません。知り合いの銀行の方からもお祝いの花をいただいたりするなど、それほどの賞なんだと受賞後にびっくりした次第です。

――菅先生が開発された特殊ペプチドをもとに創業されて今年で14年目ですが、当初窪田会長との出会いはどのようなものだったのですか。
菅私がアメリカの大学から帰国した後、この特殊ペプチドをもとにバイオベンチャーを立ち上げるという話になったんですが、私自身はビジネスをする気がない。そこで社長探しをして、窪田さんと出会いました。ほかにも何人かの社長候補の方とお会いしましたが、窪田さん以外とは会社をつくる気にはなりませんでした。
じゃあ、どこに魅かれたという話になりますが、簡単に言えば、飲んでいて楽しかったことです(笑)。長いパートナー関係を目指すわけですから腹を割って話せて楽しくなければ、うまくいくはずがない。人柄に加え、何よりも人格者であることにほれたんです。また窪田さんは「going concern」という言葉をよく使われていて、会社として持続させるためにはどうすればいいのかを重視していることにも感銘を受けました。ただ、会社をつくった当初は、このビジネスがこんなにうまくいくとは思っていませんでした。
バイオベンチャーが成功しないのは
ビジネスモデルが悪いから
――今も業績は好調で高い利益率を維持されています。生き残りが難しいといわれるバイオベンチャーの中で、なぜこうしたことが可能になったのですか。
窪田バイオベンチャーは長い研究開発期間と経営を両立させるのが難しく、新薬を開発するまでは赤字経営がつきものと考えられてきました。しかし、私はなぜバイオベンチャーは黒字にならないのかを考えたんです。
創業当時、面白いことにほとんどのバイオベンチャーは同じビジネスモデルに立脚していました。同じビジネスモデルの事業がいっぱいあって、それらがことごとく成功していないのであれば、それはビジネスモデルが間違っているわけです。そもそもビジネスモデルにはイグジットプラン(出口戦略)が必要であり、そこに至るまでにタイムラインをしっかり組んで事業計画を考えることが重要です。しかし、多くのバイオベンチャーのビジネスモデルにはそうしたストーリーがありませんでした。そこで私たちは黒字経営を実現するために、借入や無駄な資金を扱わないで済むような分相応な体制づくりから始めました。
東証1部に上場したときもオフィスは東大のインキュベーション施設を使っており、受付もありませんでした。電話をかけても誰も出ない。近くのドアを開けると、白衣を着た研究者が一生懸命仕事をしている。そこで聞くとオフィスのいちばん奥の小さな部屋を案内され、そこに社長である私がいる。そんな会社でした。
ただし、分相応といってもケチなだけではいけません。必要なところには資金を投じ、そうでないところでは節約する。無理無駄はしない。いわば、基本的なビジネスのあり方を実践し、計画的にビジネスを実行してきたことが成功の要因だと考えています。

窪田規一(くぼた・きいち)
ペプチドリーム取締役会長
1953年生まれ。早稲田大学卒業後、76年日産自動車に入社。78年に臨床検査のエスアールエルに入社し、2000年にDNAチップなどを扱うJGSを設立。01年に社長となるが、同社は05年に解散。その翌年の06年に菅教授とペプチドリームを設立し、社長に就任。15年に東証1部に上場させ、19年より取締役会長。
――「言うは易く行うは難し」と言いますが、なぜほかのバイオベンチャーができないことができたとお考えですか。
窪田会社が上場準備に入るまで研究者以外の人間は私しかいませんでした。経理から総務、人事などありとあらゆる雑用を社長である私が1人で担当してきました。まさに雑用係。資金も限られているので、それも当然のことだと思っていました。
そもそも私は40代後半でバイオベンチャーを立ち上げた経験があります。創業は2000年、大手企業など5社から資金を提供してもらい、ある種、鳴り物入りで始めたビジネスでした。しかし、数年で会社は頓挫。将来のリスクに対する準備を怠ったことが失敗の要因でした。今思えば、危険だというアラートが鳴っていたはずなのに、当時は気づきませんでした。会社には30人ほどの従業員がいましたから再就職の世話や退職金の手当てなど大変な苦労をしました。
そうした経験から、会社の経営というのは、ビジネスモデル、そのタイムライン、それらを俯瞰する中で、結果としてのPL(損益計算書)やBS(貸借対照表)ではなく、そのプロセスの中で資金財務計画をつねに見なければならない。そのことを実感しました。
ペプチドリームには私1人しかビジネスを見るものがいませんでしたから、毎夜会計ソフトを使って、自分自身で帳簿をつけていました。そうやってつねにお金の流れをすべて把握していたので、経営的に危機に陥ることはありませんでした。
圧倒的技術力があるから
まねはされない
――菅先生は成功の要因についてどうお考えですか。
菅そもそもバイオベンチャーは創薬のシーズ(種)からスタートして、1つの新薬が当たればマーケットができるという目論見でビジネスを始めます。アメリカではそれで成功したベンチャーがあるので、日本もそのビジネスモデルをフォローしてきたんですが、実はそのビジネスモデルでは成功に近づく段階で必ず競合が生まれます。だから、なかなか勝てない。その方向性一辺倒では成功できないんです。
特殊ペプチドはさまざまな用途に適用可能ですが、私たちの会社は規模が小さいため、多くの疾患に対応する治療薬をすべて自前で開発することは不可能です。そうであるなら、薬の開発をするのではなく、大手製薬会社のニーズに合わせてこちらの技術を提供し、彼らに薬を開発してもらえばいいと発想を変えたわけです。
製薬会社とパートナーシップを組み、リスクをシェアする形で、私たちの技術と重ね合わせる。そうすることで、従来の“一発勝負”とは異なる別のビジネスモデルが可能になりました。ただ、これはほかのバイオベンチャーにはそうまねができないことです。なぜなら、それは圧倒的な技術力に立脚しているからです。かつてアメリカで私たちの技術と似た技術を持つ会社があって一時期競合状態になりましたが、結果的には私たちが勝ちました。

菅裕明(すが・ひろあき)
東京大学大学院理学系研究科教授
1963年生まれ。86年岡山大学工学部卒業後、同大学院を経て94年にマサチューセッツ工科大学(MIT)Ph.D取得。ハーバード大学研究員、ニューヨーク州立大学助教授などを経て、2003年東京大学先端科学研究センター准教授、05年教授。06年に窪田会長とペプチドリームを設立。
窪田私たちの強みということで言えば、次世代の革新的な創薬を探索できる、独自の創薬開発プラットフォームシステムPDPS (Peptide Discovery Platform System)を有していることです。このPDPSは多くの特許で守られていますが、運用するうえでも独自のノウハウが必要になってきます。そのため、ほかの会社は同じことが決してできないんです。
このPDPSを利用すれば、製薬会社は自分たちが作りたい新薬を開発できる成功率が格段に高まる。一方、私たちは新薬に関する知財は放棄する代わりに、PDPSで新薬が開発されていく初期、中期、後期の各段階で一定の報酬やロイヤルティーなどの成功報酬をいただく。そのトータルな契約をプロジェクトが立ち上がる最初の段階で結ぶことで、経営上のリスクを低減し収益を確定できるようにしています。
――製薬会社にも大きなメリットがあるということですね。
菅製薬会社が新薬を開発するまでには膨大な時間がかかります。その時間をどれだけ短くするかが競争に勝つ要素の1つです。早く、いい品質のものができれば、それだけ勝つ確率も高まるからです。その時間を短くする効果がPDPSにはあります。ペプチドリームとパートナーを組めば大きなメリットがあるということなんです。
それと、私は大学の研究者として製薬会社と一緒に研究することはありません。多くの声をかけていただきますが、私の技術を利用したいときは必ずペプチドリームを通してもらっています。ビジネスと研究を厳密に分けているのも大きいと思います。
窪田通常、大学の研究者が自分で開発した薬は、まさに“自分の子ども”であって他人の手に渡すことはありません。そのため、いざビジネスとなったときに、研究者の思いが強すぎて支障が出るケースが少なくないんです。しかし、菅さんの場合は、あっさりと技術を提供してビジネスと研究を分けた。それもペプチドリームが成功した要因の1つだと思います。
創業者2人のミッションは
すでに完了している
――創業時に苦労されたことはありますか。
菅貧乏ですね。貧乏以外の何物でもありませんでした(笑)。しばらく大学の施設にいましたから、事務所の椅子も机もすべて大学の中古品。同じく実験台もそうで、当初は本当にコストをかけずにやっていました。
窪田ただ、大学にいたことはありがたかった。大学の倉庫にいろいろと使えるものがあったんです。創業から2~3年前後までは、朝出社すると倉庫に何か使えるものはないかと探しにいくことが日課でした。それに、私も菅さんも創業から1年半くらいは給料をもらっていませんでしたね。

――今、お2人の役割分担はどうなっているのですか。
菅私は社外取締役からも外れて、会社とは今ほとんど関わりがありません。大株主ではありますが、会社の最新情報も何も知りません。私のことを知らない従業員も増えていて、受付で「菅です」と言ったら、「どちらの菅さんですか」と言われましたから(笑)。
窪田私は会長の役職に就いていますが、代表権は返上しています。2017年に私が会長になる段階で、経営陣を若手に入れ替えました。なぜなら私が思い描いてきたタイムライン上のビジネスモデルがすべて完了したからです。その段階で私の役割は終わった。これから10~20年先のことは若手に任せたい。そのため日常のオペレーションはすべて彼らに任せています。
――それは世間的には潔いとは思いますが、ほかの成功したベンチャー経営者の考え方や行動と比べると欲が少ないように見えます。
菅窪田さんのミッションは会社をつくり、育て、成長させて、会社の認知度を上げることです。そして、私のミッションは薬である特殊ペプチドの認知度を高めることですから、私たちのミッションはもう完了しているんです。私たちの目的は会社で高い地位に居続けることでも、贅沢な生活をすることでもありません。あくまで病気の患者さんを助けることです。その理念がなければ会社をやっている意味はありません。それだけはブレていない。
窪田いい薬を作って、患者さんにお届けするという意味では、まだまだペプチドリームは完成していません。私は会社として1つの仕組みをつくって継続的に利益を得られるようにし、特殊ペプチドをマーケットに出せる体制にした。その薬を世の中に広める仕事は若手のミッションになります。これから会社はセカンドステージに入っていきますよ。
異端は認められた瞬間に先端になる
――創業時から愚直に続けてきたこととは何でしょうか。
菅研究を続けてきたことです。特殊ペプチドについては、私が25歳の大学院生の時代から考えて続けてきたことですが、これまでの研究生活でも特殊ペプチド以外の研究プロジェクトにはほとんど関わっていません。ですから、これは愚直に続けてきたと言えるでしょうね。
窪田たった一人の人でもいい。病気で苦しんでいる方にありがとうと思ってもらえる仕事をしたい――。これは会社を立ち上げたときからずっと思ってきたことです。私の母親も治療薬のない疾患で亡くなりました。そんな患者を一人でもなくしていきたい。そんな思いを持ち続けています。それと同時にもう1つは働いていて楽しいことをやりたいという気持ちを持ち続けていることです。
私はワークよりもジョブが好き。人に言われて何かをすることが元来嫌いなんです。サラリーマンの時も上司の言うことを聞いたことはほとんどありません(笑)。本当に使いにくい部下だったと思います。自分で言った以上は実行し、成功させる。まさに有言実行を1つのモチベーションとして持ち続けています。
――では、愚直以外に成功の要因となったものは何でしょうか。
菅私の哲学は「異端は認められた瞬間に先端になる」というものです。つまり、先端をやっていても先端にはなれない。異端とは、人と違うことをするという意味です。私の愚直さの中身を見ると、人と違うことをやって、それを達成してきたということです。
しかも、うまくいくだけでは駄目で、うまくいった後に周囲の人たちから「これはすごい」と評価される必要があります。その瞬間になって初めて先端になれるんです。そうすると、人が集まってくる。だから、また異端の道に行かなければならない。つねに私はそうして生きてきた。愚直に、異端を走ってきました。
窪田私の信条はケ・セラ・セラです。なぜなら人間は成功し続けることは絶対にできないからです。人間は多くの失敗を必ずします。そのとき反省は必要ですが、それで落ち込むのではなく、失敗を素直に認め、前を向けばいいんです。タイムマシーンもないんですから、失敗しても次に進めばいい。世の中なるようになります。何よりも先に進んでいく気持ちが大事だと思います。

――では、社会の中でアントレプレナーはどんな存在だと思いますか。またはどのように定義されていますか。
窪田リスクを背負って、世の中にない新しいものを創造していく存在だと思っています。既存の成功例をまねるのはアントレプレナーではない。世の中にないものをつくりあげて成功させる。それがアントレプレナーのいちばん大きな素養だと思っています。
菅日本社会は失敗を認めないとよく言われますが、そんなことはありません。失敗したときにもう一度立ち上がる勇気がある人が少ないだけだと私は考えています。もっと言えば、一度失敗した後に、リスクを過大に評価して避けてしまう人たちが多いだけなんです。だからこそ、アントレプレナーとは何度でもリスクを取れる人たち。危ない橋を何度も渡れる人たちだと考えています。それができる人こそ、アントレプレナーと呼ぶべきでしょう。
――アントレプレナーが成功に近づくにはどうすればいいですか。
窪田世の中に成功本はたくさんありますが、成功本で成功するのは著者と出版社です(笑)。成功本を読んで成功する人はほとんどいません。本当に学ぶべきは失敗例なんです。
菅しかもメジャーなところで勝負するよりも、マイナーなところで勝負したほうが成功率は高い。
――最後に読者へのメッセージをお願い致します。
菅「誰もまねできない、まねしようとすら思われないレベルのイノベーションを続けろ」というスティーブ・ジョブズの言葉があります。これはまさに私の糧になっている言葉で、その言葉の「続けろ」というところが大事なんです。1回ではダメで、続けないといけない。そんな気持ちを持ってほしいですね。
窪田日本にはアントレプレナーのエコシステムがないと言われます。確かにそうかもしれませんが、愚痴を言っているだけでは現状は変わりません。必ずどこかにチャンスはあるはずです。だからこそ、諦めることなく、チャレンジし続けていく。しかもガムシャラではなく、なぜうまくいかないのかをつねに考えながら、再度チャレンジし続けること。それが重要なことだと思います。
文:國貞文隆
写真:今祥雄
取材:2020年1月17日


“世界一”を決める起業家表彰制度
EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーとは?
EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーは、1986年にEY(Ernst&Young=アーンスト・アンド・ヤング)により米国で創設され、新たな事業領域に挑戦する起業家の努力と功績を称えてきた。過去にはアマゾンのジェフ・ベゾスやグーグルのサーゲイ・ブリン、ラリー・ペイジらもエントリーしている。2001年からはモナコ公国モンテカルロで世界大会が開催されるようになり、各国の審査を勝ち抜いた起業家たちが国の代表として集結。“世界一の起業家”を目指して争うこのイベントは、英BBCや米CNNなど、海外主要メディアで取り上げられるほど注目度が高い。