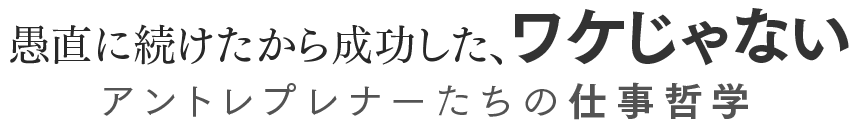Access Ranking

24
マザーハウス
代表取締役社長/デザイナー
山口絵理子
見過ごされているものの
価値を見出していくこと
アジア最貧国と言われたバングラデシュに渡り、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念を掲げて、立ち上げられたマザーハウス。創業者、山口絵理子氏の途上国支援とビジネスを両立させる姿勢は多くの支持を得て、バッグからスタートしたビジネスは、今ではジュエリー、ストールなどに広がっている。そんな山口氏の起業家としての生き方について語ってもらった。
経営をしているうちに
デザインの魅力にとりつかれた
――2006年に創業されて、12年が経ちました。
山口創業以来、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもと、私たちは、「モノづくり」を通じて「途上国」の可能性を世界中のお客様にお届けしてきました。その間、生産国もバングラデシュやネパールから、インドネシア、スリランカ、インドへと広がり、バッグ以外にも、ジュエリーやストール、シャツなどのアイテムも扱うようになりました。スタッフは全世界で約650人。販売拠点は日本30店、台湾6店、香港2店の計36店に拡大しています。来年春にはシンガポール店がオープンする予定です。
――社長もしながら、デザインもすべて担当されているそうですね。
山口最初は全然やるつもりはなかったんです。プロにデザインをお願いしても、現場がなかなかその通りにつくってくれないことを何度も経験して、その時、ようやく現場が「キー」であることに気づきました。
でも、デザイナーにバングラデシュまで行ってもらい、職人とコミュケーションをとってもらうのは難しい。結局、私しかいなかったんです。必要に迫られて、自分でデザインして、皮を切り、ミシンで縫い始めました。そして、気が付いたらバッグだけで2000モデルもつくっていました。
デザインを専門に勉強したことはないんですが、やり続けているうちに、その魅力に取りつかれてしまいました。そのうちポイントは形よりも素材であることに気づくようになり、今はレザーのなめしもオリジナルでやるようになっています。
――現地の職人さんと直接コミュニケーションするんですか。
山口そうです。英語以外に、ベンガル語、ヒンディー語、インドネシア語、スリランカのシンハラ語など現地の言葉で打ち合わせをしています。勉強は基本的には現地に行くまでの飛行機の中(笑)。「小さくして」とか「早くやって」とか、モノづくりに必要な言葉はどの言語でもわかります。
やはり職人とは直接打ち合わせしないと、こちらの意図は届きません。世界共通かもしれませんが、職人は自分の仕事にプライドを持っています。ですから、大事なことは、リスペクトの姿勢で臨むことです。まずはインタビューのように「あなたはどんな人間なのか」という問い掛けから始め、彼らの歴史や背景について理解するように努めています。
たとえば、インドネシアのジョグジャカルタでようやく探し当てたジュエリー職人と対面したときは、まったくコミュニケーションが取れない状況でした。外国人に対して抵抗感があり、家にも入れてくれない。そんなとき現地の言葉で「私はこんなことをやりたいんですが、あなたがやってきた仕事を見せてくれませんか」と話して、何カ月もかけて彼らの仕事の理解をしていく。そのうちに、少しずつですが、心を開いてくれようになるんです。そこから彼らの働く価値観を探っていきます。

――働く価値観とは、どのようなことですか。
山口それは国や地域によっても違っていて、たとえば、バングラデシュは、アメリカンドリームならぬ、ダッカドリームのようなものがあり、ハングリー精神が旺盛です。残業も自分が一番になれると思ったらやるし、自分が周囲にどれだけ影響力を持っているか競い合いもします。現地では起業家も多く、サクセスストーリーもたくさん生まれています。
他方、ネパールはおカネが稼げるというだけでは動かない。信頼感や地元の慣習を大事にしてくれる相手と仕事をすることを好みます。そうやって働きながら、現地の人たちが大事にしているポイントは何かを探りながら、徹底的に歩み寄り、信頼関係を築いていくんです。まるで人類学者みたいですけど(笑)。
――人口の多いインドネシアはいかがですか。
山口ジョグジャカルタではジュエリーをつくっていますが、生産地の中ではいちばんの村社会で、水と野菜の物々交換といったことも行われています。ネットも通じていません。そこで、「東京向けに商品をつくって」と言っても、最初は現地の人もなかなか理解できない状況でした。しかし、生産が軌道に乗り始めると、おカネを得たことで「バイクを買った」「奥さんがきらびやかになった」というように人生が変わってしまう職人も出始めました。
だからこそ、私たちの影響力をミニマムにしなければならない。その気の遣い方はとても大変です。もし職人が偉ぶってしまうと村社会の人間関係に波紋を広げることになる。私たちも職人に対しては、細心の注意を払って対応しなければいけないとつねに考えています。
私たちの仕事は社会貢献とか
そんなきれいなものじゃない
――そうやって途上国で生産を続けてこられて12年。これまでお客様に商品が支持されてきた理由は何だと思われますか。
山口マザーハウスの場合、やはり直営店を持っていて、本当に商品に理解のあるスタッフがたくさんいることが大きいと思います。接客がいいと言ってくれるお客様は多いです。なぜそんなスタッフが多いかといえば、会社のビジョンや哲学を共有してくれているからだと思います。商品がどのように出来上がっていくのか。職人に対する信頼感も非常に高い。心を込めてつくった商品を、心を込めて売る。そんなきれいなリレーができるのがいちばんの強みだと思います。そうしたスタッフたちの“心の濃度”を薄めないためにも、私は現場に行き続けるんです。昔は私も社長だからマネジメントの比率を高くしなければならないと思っていましたが、次第に私の価値をいちばん出せるのは現場だと思うようになりました。
――なぜスタッフにそこまでビジョンや哲学が浸透しているのでしょうか。
山口社員研修はありますが、実は私自身は言葉で伝えることはしていません。むしろスタッフから「いつも山口さんは現地にいる」「また大量の商品を持って帰ってきたぞ」と思われていることがいちばん大きいのではないかと考えています。

――進出する国や手掛ける商品について、どんな判断基準があるのでしょうか。
山口市場規模や競合他社について調べることはありますが、最終的には感覚で決めています。自分でもよく説明できないんですが、ある国に進出するとき、「本当に価値あるものができるのか」「本当に私たちしかできないのか」、いつも自分にそう問いかけるようにしています。創業当初から、私たちはカウンターメジャーになりたいと思ってきました。ほかの大きなブランドと同じことをやっても負けることはわかっている。だからこそ、私たちがやる意味を問い続けなければならないと思っています。
――山口さんのモチベーションはおカネではないと思うんですが、一体何でしょうか。
山口それはよく勘違いされますが、社会貢献とか、誰かの役に立ちたいとか、そんなきれいなものではないんです。私も学校で問題児だったころがあるからわかるんですが、それまでネガティブにとらえられていたものがある日突然ポジティブになるとか、黒から白に変わるとか、世の中にはそんな瞬間があって、それがとても好きなんです。途上国も、貧しい、汚い、怖いといったイメージだったものが、モノをつくることですべてをポジティブに転換できる。その瞬間がすごく爽快なんです。誰かができないと言ったら、私はできるんじゃないかと考える。そういう感覚です。
結局、起業家のような方たちって、根っこがハングリーか、アンチな方が多いんですよね。ビジネスですから、真っ向からアンチだとは言えませんが、「やってやるぜ!」みたいな気概は確かにあります。
――創業して以降、苦しいときもあったと思いますが、どうやって乗り越えてきたのでしょうか。
山口たくさんあり過ぎて言えないくらい(笑)。創業当初によく考えていたのは、企業として持続的な経営をすることがこんなにも難しいのかということでした。創業時から黒字化するまでは、スタッフに給料を払うことが最終的なゴールと考えてしまうくらい、おカネもありませんでした。そうやっておカネのことばかりを考えているうちに、「なぜこの仕事を始めたのかなぁ」と思ったこともあります。
バングラデシュでジュート(麻)を見つけたときの感動がどんどん遠のいていって、経営する、雇用するということがどんどん負担になっていったんです。そのとき、「これは私のやりたいことじゃない」と思ってしまいました。会社は重たいし、「一人でやりたいことをやればいいじゃないか」って。当時は副社長とも相当ケンカをしましたし、会社の規模を大きくする意味もまったくわからなかった。
特に女性の経営者はそう考える人が多いかもしれません。自分の中の価値観が明確にあるからこそ、小さくても美しければよしとしたくなる。大きくすると何かが壊れてしまいそうで怖いんです。
――ターニングポイントはどこで訪れましたか。
山口次第に会社の口座におカネが貯まるようになったときです。そうすると「この素材が使えるかも」「あのデザインが試せるかも」と、いろんなことに挑戦できるようになったんです。それがとても楽しかった。だから、私は経営だけをやっていたら挫折していたかもしれません。モノづくりをやっていたからこそ、続けることができたんです。
会社が利益を上げて、生産国も広がり、職人と出会え、新しいものがゼロから生まれる。おカネを得る意味は、これだと思いました。今は職人に対しても、自分がやりたいことを思い切って言えるようになりました。会社を大きくすることが、クリエイションの喜びと直結していることが、私が経営を続けてきた理由だと思います。

伝統工芸でも大量生産でもなく
第三の道を進みたい
――創業から、これまで愚直に続けてこられたことは何でしょか。
山口それは、やっぱり現場でつくり続けてきたことです。
――では、愚直以外で成功したきっかけとは何でしょうか。
山口つくり続けるだけだったら、成長は止まっていたと思います。バングラデシュのバッグ屋だけでやっていたら、会社は違う方向へ行っていたかもしれません。それが最終的なゴールだとしたら、スタッフのモチベーションも、ゼロからイチにするワクワク感もなくなっていたでしょう。私は企業経営をしながら、新しいものを生むということを戦略的にやっているつもりです。バッグからジュエリーをやって、アパレルへ。企業内ベンチャーを立ち上げることは、人を育てるうえでも非常に大事なことです。しかもゼロイチで事業を始めることが、結果として組織の活性化にもつながる。ずっとバッグだけだったら、私も続けられていたかどうかわかりません。
――EOY(EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー)などの起業家賞について、どのようにお考えですか。
山口いくつか賞をいただいたときに鮮明に覚えているのは、とても大きな自信をもらえたことです。私の場合は、起業してからも経営者としてなかなか自信が持てませんでした。やりたいことを始めて、代表という肩書がついて、頑張れば頑張るほど背負うものが大きくなる。とても怖いなとか、自分が本当にやっていけるのかなとか、創業時は思っていました。上司もいないし、誰からも褒められない。そんなとき賞をいただいて、「頑張ろう」と素直に思うことができたんです。
――起業家の社会的意義については、どのようにお考えですか。
山口見過ごされているもの、存在しているのに見えないものの価値を掘り起こしていくことだと思います。それには多様な見方を持っていなければなりません。どんなものにも見方次第でいろんな価値を見出すことができるんです。マザーハウスは、伝統工芸でも大量生産でもなく、第三の道を進みたい。途上国の素材や技術をふんだんに使って、彼らがきちんと自立できるようにすると同時に、ビジネスとしても成功させたい。それがアジアのモノづくりとして、私がやりたいことなんです。
――この企画は起業家を目指す方を応援する意味も込めています。最後にメッセージをお願いします。
山口起業家になること自体はゴールではありません。むしろ自分のやっている事業に、どれだけ惚れ込んで、どれだけ付加価値を与えられるか。それが大事です。ある意味、起業はアクションとしては簡単ですが、それを継続することは難しい。そこを忘れてほしくないと思っています。
文:國貞文隆
写真:今祥雄
取材:2018年10月19日

山口絵理子(やまぐち・えりこ)
マザーハウス代表取締役社長/デザイナー
1981年埼玉県生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、バングラデシュBRAC大学院開発学部修士課程留学。ワシントンの米州開発銀行でのインターン時代、国際機関の途上国援助に疑問を感じたことをきっかけに、当時アジア最貧国バングラデシュに渡り、そのまま日本人初の大学院生になる。2006年にマザーハウスを設立し、以降、バングラデシュ、ネパール、インドネシアなどの自社工場・工房でバッグ、ストール、ジュエリーなどのデザイン・生産を行っている。

“世界一”を決める起業家表彰制度
EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーとは?
EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーは、1986年にEY(Ernst&Young=アーンスト・アンド・ヤング)により米国で創設され、新たな事業領域に挑戦する起業家の努力と功績を称えてきた。過去にはアマゾンのジェフ・ベゾスやグーグルのサーゲイ・ブリン、ラリー・ペイジらもエントリーしている。2001年からはモナコ公国モンテカルロで世界大会が開催されるようになり、各国の審査を勝ち抜いた起業家たちが国の代表として集結。“世界一の起業家”を目指して争うこのイベントは、英BBCや米CNNなど、海外主要メディアで取り上げられるほど注目度が高い。