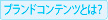Access Ranking
21世紀に入り、私たちが生きる世界はますます複雑になっているように見える。政治やビジネスだけではなく、様々な分野で地殻変動のように変化が起きている今、最も必要とされるのが“人物×人材力"だ。各界で活躍するプロフェッショナルたちはどのように自らを磨いてきたのか。
第5回は、2006年に『いやしい鳥』でデビューし、13年に『爪と目』で第149回芥川賞を受賞した作家・藤野可織さん、毎日放送アナウンサーとして活躍し、06年に優秀なアナウンサーを表彰する「アノンシスト賞」を受賞、豊富な海外経験も活かして、今はフリーアナウンサーとして活躍する八木早希さん、2人のプロフェッショナルの対談を収録する。同時期に同志社大学で学び、それぞれの世界に羽ばたいた才色兼備のふたりが、プロフェッショナルとして重視していることとは――。

アメリカ生まれ。同志社大学文学部卒。2001年、毎日放送へ入社。06年、JNN・JRN系列各局の優秀なアナウンサーに与えられるアノンシスト賞(ラジオ「フリートーク」部門)を受賞。11年に退社し、フリーアナウンサーに転身。14年3月まで『NEWS ZERO』(日本テレビ系)の金曜日のキャスターを担当した。14年10月より同志社大学客員教授就任予定。
――まずはおふたりの学生時代を振り返っていただきたいと思います。1年先輩の八木さんは帰国子女で、藤野さんは中学から同志社で過ごされています。おふたりはなぜ同志社大学を選び、どんな学生時代を過ごしたのでしょうか?
八木 私はアメリカ生まれで、日本では故郷の大阪の町から出たことがありませんでした。私が知っている日本は、“ご近所”の狭い世界だけだったんです。だから、大学は、ワールドワイドで日本らしいイメージもある京都の同志社大学に行きたいと考えました。実際、入学すると北から南までさまざまな出身地の方と出会うことができ、多くの刺激を受けましたね。
藤野 私は中学から同志社でしたし、高校生のときに美術館の学芸員になりたいと考えていたこともあって、同志社大学の文学部美学芸術学科に進みました。在学中はカメラクラブで活動していて、学芸員とともにカメラマンに憧れたりもしていました。
八木 私もテニスサークルで活動したり、テレビ局でアルバイトをしたり、楽しく過ごしていました。ただ、2回生からはアナウンス学校に通って、アナウンサーになるために一生懸命勉強しましたね。3回生の3月には就職が決まっていたので、その後は中国語、韓国語、スペイン語……と、語学の授業をたくさん取りました。「同じ学費を払うなら、きちんと元をとるんだ!」と思って(笑)。
藤野 八木さんは、そもそもどんなきっかけでアナウンサーを目指されたんですか?
八木 小学4年生のときにソウルオリンピックが開催されて、陸上の女子短距離で3つの金メダルを獲得したフローレンス・ジョイナーという選手に釘付けになったんです。テレビを観ていると、競技のあと、マイクを持った人たちがジョイナーに駆け寄ってインタビューするシーンがありました。そのとき、マイクを持てば、憧れの人だったり、本当は出会えるはずのない人ともしゃべれるんだ!と思ったんです。それがアナウンサーを夢見るようになった原体験ですね。
藤野さんも、小さいころに「お話を作る仕事」に興味を持たれたそうですね。
藤野 そうなんです。幼稚園に入る前から、母が毎晩、絵本を読んでくれました。読み終えたら寝かされてしまうから、母を引き止めるために、ページをめくらせない勢いで絵や話の内容について質問したんです。そのうちに勝手に字が読めるようになり、絵本がもっと大好きになって、「私もいつかお話を作りたい」と思うようになりました。特に「小説家になろう」と考えていたわけではなく、人が大人になるように、自然とお話を作る人になるんだろうなと思っていたんです。
そうして大学院に進み、学芸員になるために勉強をしていたのですが、その2年間で自分にはとても無理だとわかってきて、「そういえば、物語を作る人にまだなってないやん」と思い出して、小説を書き始めたのです。
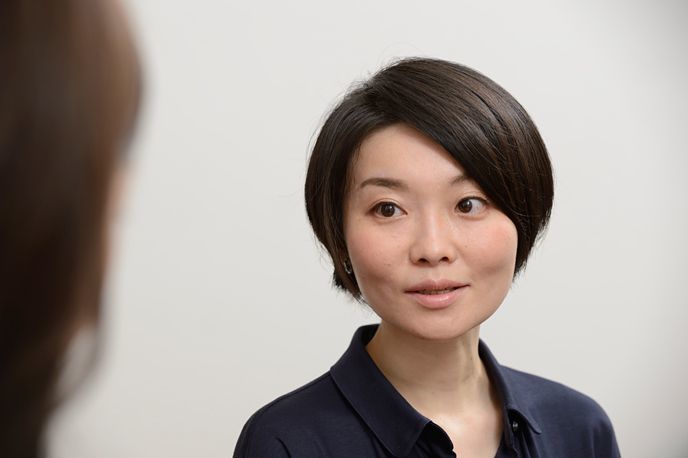
壁に突き当たった社会人時代
八木 卒業後は、就職されたんですよね。
藤野 京都の小さな編集プロダクションに就職して、スタジオカメラマンの助手をしていました。でも、カメラは好きでやっていただけで専門的な知識はないし、決められた内容の写真も撮れる自信がなくて。入社した年の10月には辞めて、学術出版社でアルバイトをしながら、小説を書こうと決めました。文學界新人賞を受賞してデビューしたのは、その2年後でした。
八木さんは難関を突破して、アナウンサーとしてテレビ局に就職されましたが、どんな準備をされたんですか?
八木 局アナになるための唯一の入口が、「4年制大学の新卒」だったんです。チャンスは一度でしたから、逆算していったときに、「夢をかなえるなら今しかない」と思い、大学2回生からアナウンス学校に通い始めました。それと同時に、友人やマスコミで働く先輩たちに協力してもらい、試験内容を細かく調べて対策を練ったんです。
アナウンサーの合格者には、容姿が美しい人、会話が上手な人など、それぞれに武器があると思いますが、私の場合は「入念に準備をしたから、合格できた」とハッキリ言えます。だから面接では開き直っていました。「これであかんかったら仕方ないわ」って(笑)。
――おふたりがアナウンサー、小説家とそれぞれのプロフェッショナルとしてどのようにスキルを高めていったのか、どんなことを大切にされているのか、ということも聞かせてください。
八木 私は就職してから3年間は、とにかく怒られ続けましたね。人と話すのが好きだし、どんな人ともわりとすぐに打ち解けられるほうなので、この仕事に向いていると思っていたのですが、実は「自分らしさ/個性」というものの出し方をはき違えていたのです。テレビの向こうの何百万人という人に向けて話すには、正しい日本語、正しい振る舞いという基礎をしっかり固めて、決して不快感を与えないようにしなければいけない。それができないのに自分らしさを出そうとしていたのです。やるべきことに気づいてからは、「アナウンサーの基礎」を大事にし、どんどん仕事にぶつかって学んでいきました。
藤野 作家も「文章の基礎」が大事だと思っています。私はそれを大学院時代、岸文和先生に「論文を書くポイント」を通して教わりました。まずはとにかく、対象を正確に描写すること。そして、言語を“考え方の道筋”だと捉え、論理的に構成することです。世の中には、現実には考えられないめちゃくちゃなことが起こる小説がありますが、実は小説内の論理ではきちんと筋が通っているものなのです。岸先生に教わったことは、いまでもとても大切にしています。
八木さんは、アナウンサーという仕事のどんなところにおもしろさを感じますか?
八木 今は時間のマネジメントを考えながら、いいインタビューをつくり上げることにやりがいを感じています。例えばインタビュー時間は15分、聞かなければいけないテーマは3つ、私が聞きたいのは2つ。でも、お話をしているうちに、ほかに聞きたいことが出てきて、そのテーマにもう2分使った……という状況で、どう話を広げ、集約していくのか。放送は「オンエア」というくらい、その場の空気を重要視する仕事です。限られた時間をどれだけ有意義なものにして、その日、その場所で、私だからこそ、この言葉を引き出せた、と思える瞬間が本当に楽しいんです。

京都生まれ。同志社大学文学部卒、同大学院文学研究科美学芸術学専攻博士前期課程修了。2006年、「いやしい鳥」で第103回文學界新人賞受賞。13年、「爪と目」で第149回芥川賞受賞。14年、『おはなしして子ちゃん』で第2回フラウ文芸大賞受賞。近刊は『ファイナルガール』。14年10月より同志社大学客員教授就任予定。
どんな仕事も一人ではできない
藤野 小説はひとりで作れるようで、ひとりでは作れないものです。例えば、原稿の段階で編集者さんに意見をいただきますし、そもそも編集者さんが一定のレベルをクリアしていると判断しなければ掲載されない。本になるときには装丁家さんやイラストレーターさんなど、さらに多くの人の手が必要になります。私は本という物質そのものが好きで、そうやって形になっていくのが何よりもうれしいです。
八木 私が多くの方々にインタビューさせていただくなかで強く感じるのは、一流の方ほど謙虚であるということです。例えば、吉永小百合さんは「いまだに自信が持てなくて、次はもっとうまくできないかと考える」と言われますし、渡辺謙さんも「心に贅肉をつけないように気をつけている」とおっしゃっています。一流とは、現状に満足しない、向上心のある方なのだと思いますね。
藤野 そうですね。私も芥川賞をいただきましたが、この賞は新人賞であり、まさにスタート地点に立ったばかり。新人のつもりで仕事に取り組んでいます。
八木 私も2011年に毎日放送を退社してフリーとなって、新人のつもりで日々の仕事に臨んできました。独立当時は31歳で、女性アナウンサーがフリーになる年齢としては、遅いほうだったんです。でも、自分は若さで仕事をしているわけではないし、私自身がそういう価値観にとらわれる必要はない。「自分がどれだけできるか、チャレンジしてみよう」と考えました。
本当に一から番組のオーディションを受け直したんです。「考えてみたら、入社時から同じ自己PRをずっと使っていたなあ」なんて改めて気づいたり(笑)。局アナとしての安定もとてもありがたいものだったのですが、見えない未来にチャレンジすることに惹かれてしまったんです。背中を押してくれたのは、同志社の自由精神ですね。「既存の価値観にとらわれるな、世界は広いぞ」と。
藤野 確かに、同志社精神ってありますよね。大学では同調圧力のようなものが少なくて、いい意味でみんなが放っておいてくれる。
八木 わかります。特に女子はグループで動くことが多いし、人と違うことをすると浮いてしまうことが多い。けれど、同志社では人から見たら少し変わったことをしていても、きちんとリスペクトされるような空気がありました。

――おふたりが考える、今後の大学教育のあり方についても聞かせてください。
八木 私はアナウンススクールで大勢の人の前で話す方法や、公式なプレゼンテーションの仕方を学びました。緊張感のある場面で自分の言葉で話す“会話力”はどんな仕事にも必要な能力です。大学でももっと学べたらいいと思いますね。どんな地位の方、どんな年齢の方とでも、対等に話せる言葉を持っているというのは、充実した人生を送るための武器にもなります。人はひとりでは何もできない。だから、自分の思いを伝え、共有してもらう「言葉」を持つべきだと思います。
藤野 私は会社を辞めて小説を仕事にしたとき、とても苦労しました。「フリーランスで生きていく」ということを、自分で痛い目にあって、満身創痍で学んできたんです(笑)。自分で起業したり、フリーで働いたりという人も増えていくなかで、「企業に就職する」ことと同時に、フリーランスで生きていくことのメリットやデメリットを学生時代にもっと知ることができたらいいですね。
――最後に、おふたりの目標や夢を教えてください。
藤野 死ぬまで書き続けることが目標です。たくさん小説を書いて、きちんと仕事として残していきたいですね。これまでは短編・中編が多かったので、長編の分厚くてカッコいい本も作ってみたいですね(笑)。
八木 いまは「アナウンサー」という肩書ですが、私はいい「インタビュアー」になりたいと考えています。その人の本当の思いや、普段見られない表情を引き出してみたい。人に信頼され、相手の深い部分を引き出せるようなインタビュアーになりたいですね。

(撮影:今祥雄)