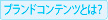Access Ranking
同志社大学大学院を修了後、博報堂、電通、グーグルという異色の職歴をたどり、現在はマーケティングエンジンの代表取締役を務める高広伯彦さん。広告・IT業界内外の注目を集める、ユーザー主導型の「インバウンドマーケティング」という考え方の普及に努めている。マーケティングに対する興味やスキルはどこで培われたのか――これまでのキャリアを振り返りつつ、クリエイティビティの育て方についても語る。
――高広さんが広告業界に進もうと思われたきっかけは何ですか。
高広 もともと大学時代から出版社でバイトをしていて、なんとなく「メディア」というものに興味があったんですよね。それで同志社大学の大学院在学中にも、社会学専攻の中で特に学んでいたのがメディアに対する研究。当時は、他大学も含めた社会学や哲学関係の院生と自主的に集まって、メディア関連の研究会を実施していたりもしました。90年代当時に、「消費者主導型の消費社会研究」というテーマを自分で立てて研究していたのですが、その当時の仲間たちと話すと、「あの当時の議論は今まさに起こってることだよね」という話をしたりもしています。就職先に広告業界を選んだのは、学生時代に広告代理店の人と出会ったのがきっかけ。修士論文は当時として新しいメディアであった「ポケベル」をテーマにしたのですが、新しいメディアも古いメディアも含めて、いろんなメディアを扱える唯一の業界が広告代理店だな、という結論に達し、学生時代のメディアの興味の延長線上で就職先を選んだわけです。
――意外でしたが、最初の配属は「営業」だったそうですね。
高広 ええ、そうです。「出版営業局」という出版物の広告を扱う部署でした。広告代理店の営業はとんでもない仕事量で、会社に入るまでは頭脳労働だと思っていたんですが、「広告代理店は肉体労働だったんだ」と思い知らされました(笑)。実際には、頭と体の両方を使わないとやっていけない職場であったことは間違いありません。もともと部屋にこもるタイプではなく、アウトドア派なこともあったので、アクティブに動くことは苦にならなかったですけど。
もともと営業時代から、当時「マルチメディア」と言われていた領域にも関わることがあった関係で、その後インタラクティブ局という部署に社内異動することになりました。2000年ぐらいのことです。これ以降、本格的にインターネットやデジタルと呼ばれる領域の仕事にどっぷりと浸かってきたわけです。ちょうど、インターネットが一般ユーザーにも普及しだし、ブロードバンドの環境も整い、ホームページやブログ、動画など、ユーザー側が生み出すコンテンツが飛躍的に増加していくというのを目の当たりにしてきたのですが、これはまさに大学院で研究してきた「消費者主導型時代」の到来だと確信しました。大学で研究としてやっていたことが、より現実化していく、、、というのは非常に不思議な体験でしたね。
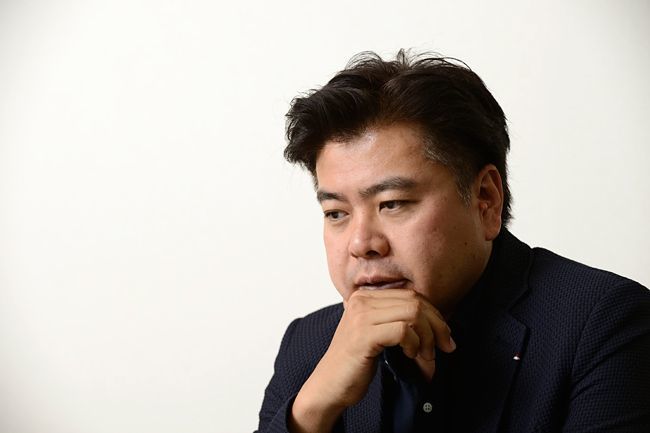
マーケティングエンジン代表取締役兼共同創業者。1970年生まれ。博報堂、博報堂DYメディアパートナーズ、電通にて、営業やデジタル領域の業務につく。2000年代には第2回東京インタラクティブアドアワード受賞などインタラクティブクリエイティブ領域での企画を強みにしていたが、新しい広告ビジネスの開発に興味を持ち、2005年にGoogle日本法人へ。AdWordsやYouTubeの日本導入やそのマーケティングを手がける。2009年1月に独立し、デジタル領域での経験を強みとしたマーケティングコミュニケーション設計やビジネス開発支援を行うスケダチを設立。2012年8月に、ソーシャルメディアマーケティング事業を手がけるコムニコと共同でアジア初のインバウンドエージェンシーとなるマーケティングエンジンを設立。2013年8月には設立1年でHubSpot社の国際部門最優秀代理店に選ばれる。著書に『次世代コミュニケーションプランニング』(ソフトバンク クリエイティブ)他。
――2003年には、日産自動車の広告「WebCINEMA TRUNK」で第2回東京インタラクティブ・アド・アワードのグランプリを受賞。翌年からは電通で活躍され、2005年にはグーグルに入社したことが広告業界でニュースになりました。
高広 博報堂時代に手がけた日産自動車の「WebCINEMA TRUNK」は、今、広告やマーケティング業界で話題になっている「コンテンツマーケティング」の走りだったかもしれません。それまでは「メディア」というのは広告業界で言えばすなわち「広告枠」のようなものだったわけですが、「WebCINEMA TRUNK」については「コンテンツそのものが、人々と企業をつなぐメディアになるのでは?」と考えたわけです。また電通時代には『牛乳に相談だ。』というプロジェクトでデジタル周りの企画をやりましたが、その際には牛乳を飲んで欲しい小中高生がネット上であつまるコミュニティを立ち上げたりもしました。メディアそのものの立ち上げに近いですね、これは。その後、縁あって、まだまだ無名だったグーグルに入社したのですが、同社にいるときにおもしろいと思ったことが主に二つあり、広告主の数と種類が爆発的に増えてきていると気づいたことと、ユーザー側が主導する広告の時代がやってきていたということでした。前者でいうと、それまで電通や博報堂にいるとテレビCMや新聞広告をやるような大企業がすなわち広告主であると無意識に認識していたわけですが、ネットの時代においては町中の零細企業であったり、たった一人の法人であっても広告主になってきた。特に検索連動型広告は1クリックいくらの非常に小さな予算から始められるので、そのような傾向が強かったわけです。電通が毎年出している『日本の広告費』は大企業を中心とした広告費で占められていたわけですが、その中身がこの10年ぐらいで大きく変わっているんです。それと、この検索連動型広告や多くのネット広告が従来の広告と大きく違ったのは、ユーザーが検索するなりサイトを開いた結果、広告が出現するという点。従来の広告は、新聞でも雑誌でも物理的に「枠」がある。でもネットの場合は「枠」を表示するのも実はユーザー主導なんですよ。この新しい広告経済が生まれているという発見は非常に興味深いものでした。
博報堂、電通という二つの広告代理店、そして外資系のテクノロジーベンチャーという別のキャリアに進んだことは、僕にとっては非常に重要なキャリアパスだったと思います。同じ業界の似たような会社間での転職だと、あまりやることも変わらなかったりする。でもあえて違うことをやってみたので、飛躍できたと思います。人事組織コンサルティングのエキスパートで高橋俊介先生(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)の話を博報堂時代に伺ったことがあったんですが、先生は、大きな成長のために「キャリアを振る」ということが大事と言われています。同じようなところから同じようなところへの転職・異動だとキャリアは伸びない、なので違うことをやったほうがスキルアップになる、ということを「振る」と呼ばれていたんですが、僕の場合は、まさにグーグルに行くことで「キャリアが振れた」ということです。
――ソーシャルメディアの隆盛も含め、ユーザー側の存在感は加速度的に増しています。高広さんも、ツイッターなどで積極的に意見を発信していますね。
高広 時にはソーシャルメディアでのたったひと言が熱い議論に繋がることがあります(笑)。ソーシャルメディアというのは面白いもので、例えばこの数年実際に会うことは全くなかったのにフェイスブックでやりとりをずっとしていたとする。そして久しぶりに本人同士があってみると、「あれ?そんなに長くあってなかったっけ?そんな気がしないね」ということがある。これなどは時間的・物理的に互いの距離があったとしても、それが縮まるような現象が起きているということ。そして一方で、全く知らない人同士がツイッター上でやりとりしていたとして、これまた距離が近い感じがする。昔は芸能人や著名人に話しかけるなんていうのは、街中で見かけたとしても距離を感じて声をかけられなかった。でもソーシャルメディアのようなオープン性の高いメディアだと、気軽に、かつ無自覚なメッセージを送ることができる。実は著名人と一般人との間の炎上というのは、このせいで起きてしまうのではないかと考えています。ある程度名の知れた方というのはそれぞれなんらかの努力をしてそのポジションにいらっしゃるわけで、それなりにプライドもある。そこで素人が心ないメッセージを投げかけると、「お前誰?」となってしまう(笑)。特にツイッターはユーザー間がすごいフラット。しかも本来、出会うことがなかったような人同士を交通事故のように出会わせてしまうから厄介。だから専門家の意見に対して素人が簡単に「噛み付く」ことができる。フラットなところはソーシャルメディアのいいところでもあり、一方で“実績を積んできた人”や“脳みそを鍛えてきた人”という努力してきた人であっても軽く見られがちなのは残念な気がします。例えば“脳みそを鍛えてきた人”というのは、スポーツで体を鍛えてきたのと同じで、それはそれでリスペクトされるべきではないかと思うんですけどね。僕は基本的に人間は怠惰な動物で、ゆるい坂ときつい坂があればゆるい坂を選ぶ傾向にあると思っていて、そこできつい坂を選んで鍛えるというのは大事なことだと考えています。
まあソーシャルメディアでの炎上なんていうのは、そういうところが踏まえられることなく、出会い頭の事故みたいなディスコミュニケーションで起きることも多いと思いますが、これはこれで新たな時代の人付き合いみたいな感じにとらえていかなければいけないかな。
――高広さんは現在、企業側から一方的にアプローチするマーケティングではなく、有益なコンテンツを作成し、それをユーザー側が発見、シェアする「インバウンドマーケティング」を提唱されています。今後に向けての目標も聞かせてください。
高広 「インバウンド」という言葉は、旅行業界でいうと海外のお客さんが日本にやってくることを指します。コールセンターでいうと企業側から電話をかけるのは「アウトバウンド」と言い、お客さんの側からかかってくる電話のことを「インバウンド」と呼びます。また、ボストンなどでは“下り”電車のことを「アウトバウンド」、“上り”電車のことを「インバウンド」と言います。つまり遠くに向かっていくのが「アウトバウンド」、こちらに向かってくるのが「インバウンド」です。これまでの広告やマーケティングは、基本的に「アウトバウンド」だったわけです。人様がコンテンツ(=番組や記事)を見ているところに“出て行って”、“○○でございます”とお邪魔していた存在だったんですよ、広告は。僕が大学院でやっていた社会学、特にメディア論や情報社会学の世界では、マスメディアは情報が一方通行ということから、「皮下注射モデル」とか「コミュニケーションの二段階モデル」なんていうのがありましたが、ネットが普及した現在ではこうした伝統的な情報浸透のモデルを見直さないといけなくなってきています。最も注目しなければならないのは、ユーザーが自ら情報を調べる時代になっていること。この変化にあわせた情報行動のモデルを考慮しなければならないし、それに応じたマーケティングを考えなければいけない。情報をユーザーが自ら調べるというのは、英語で“self education”という言い方をしますが、これまでの広告・マーケティングは古いマスマーケティングのモデルである「知らない民衆に情報を与えて教育しよう」に根っこがありますから、ユーザーや消費者と呼ばれる人々が自分たちでメディアや情報ツールを駆使して、自分たちが得たい情報にたどり着くという現在の情報行動には合わないんですよ。もしこの自分たちの得たい情報、それは得てしてなんらかの課題解決のための情報探索だったりするのですが、その先に企業の商品やサービスがあったら、それは、ユーザーが自ら企業のほうに近づいてくることになります。これが「インバウンド」なんです。
この「インバウンド」という考え方は、そもそもメディアに広告を出すとかダイレクトメールを一方的に送りつける、メールニュースという名の下に興味のないメールを何度も送りつける「アウトバウンド」と真逆で、基本的には相手にとって役に立つ情報、興味関心に合う情報を提供することで向こうから寄ってきてもらうということなのです。
この「インバウンド」というコンセプトに基づくマーケティング、「インバウンドマーケティング」は、SEO(検索エンジン最適化)やブログ、メールマーケティング、ソーシャルメディアマーケティングなどなどの様々なデジタルマーケティングの手法を駆使して行うのですが、ネットマーケティングの世界では、メールマーケティングの会社はメールマーケティングのみ、ソーシャルメディアマーケティングの会社はソーシャルメディアマーケティングだけ、などとサイロ化(縦割り化)してしまっていて、弊社のように統合的なサービスを提供しようとする会社があまりありません。でも一方で、広告主、というか広告は使わないところも多いので広告主という言葉自体が正しくありませんが、企業のマーケティング担当者は、一通りのマーケティングを全部支援してほしいと思っているところが結構ある。それでもともとコミュニケーションプランニングの『スケダチ』という法人をやっていたんですが、『コムニコ』という会社と一緒に『マーケティングエンジン』という別法人を作ったのです。
また、特にB2B(企業間取引)のビジネスにおいては、「そもそも広告を出したい媒体がないが、マーケティングは必要」ということが多い。B2B企業の場合は、広告に頼らないマーケティング、しかも営業につながるマーケティングが必要とされてるのですが、こういった企業に「インバウンドマーケティング」というのは非常に重宝されていて、今弊社の顧客は8−9割がB2Bになっています。とりわけB2B企業は国外の競合企業ともせめぎあうことが多いのに、ことB2Bマーケティングは世界標準からみても日本の企業は遅れてしまっている。いわゆる「日本はものづくりには定評があるが、マーケティングが下手」という問題があるのですが、ここをちゃんとやらないといいものを作ってても日本企業が負けてしまうわけです。この課題を乗り越えるお手伝いをしたいし、それが自分たちの知識やビジネスが社会、日本に還元できる仕事なんじゃないかな、と考えてもいます。

――高広さんのように創造的な仕事がしたい、と考える読者も多いと思います。クリエイターにとって重要な資質とは何でしょうか。
高広 いわゆる広告業界における「クリエイティブ」の仕事をする機会が格段に減ってきていて、今は事業開発やマーケティングの仕事をしているので、今の自分の仕事が一般的にイメージされる創造的な仕事かどうかはわかりません。しかし、広告であろうがビジネスであろうが「創造性・クリエイティビティ」が求められる時代にはなっていると思います。しかもそれがビジネス上のスキルとなっている。
そこで僕が重視しているのが「unlearn アンラーン」という言葉。元々『スター・ウォーズ』でヨーダが主人公のルーク・スカイウォーカーにフォースの使い方を教えているシーンで、” You must unlearn what you have learned” って台詞があったことから知った言葉です。訳しにくいんですけど、「これまで学んできたことをいったん横においておきなさい」ぐらいかな。”un-“がついてるので「学ばない」とか「忘れる」と訳されそうですが、そのどちらでもない。ネクタイや紐で言うと”tie”が「結ぶ」で、”untie”が「ほどく」ですよね。そのニュアンスに近く、単純に「忘れる」ということではなくって、「(学んだことを)ほぐす」という感じ。なので”unlearn”というのは、自分が得てきた知識や経験というのを「棚卸し」する作業。で、新たに得た知識や経験を加えて、過去に得たものも混ぜて一緒にする。
誰もが一度は手にしたことがあるであろうLEGOをイメージしてみてください。自分の経験や知識が一つ一つのブロックだとして、それを組み立てて自分ができている。で、普通は新しい知識・経験を得ると、今組み上がってるブロックの「塊」にそのまま単純に積み上げてしまう。これって、結果として過去のことを引きずってたりするので一緒。なので、それまでに作ってきた「カタチ」からは逃れられない。よく過去の成功体験から逃れられないとか、それまでの経験が邪魔をしているなんて人を見かけますが、それはこれが理由だと思います。一方で”unlearn”することというのは、まず、それまでに作っていたブロックの「塊」をバラバラにしてしまう。全部バラバラに。それで一つ一つのブロックが多数ある状態に戻る。で、そこに新しく手に入れたブロックを足す。バラバラにした以前からあったブロックと新しいブロックの両方を混ぜこぜにした状態で、また新たな「塊」を作る。こうした作業を頭の中で常にやり続けることで、ある種のクリエイティビティが生まれると考えています。ブロックの組み合わせ方なんて自由ですからね。でも昔作ったものに乗っけてくだけだと不自由。
基本的にアイデアは決して天から降ってくるものではないと思ってます。基本的に人間は、自分が経験し、見聞きしたことの範囲外でものごとを考えることはできないという考えです。ただし、自分が学んできたこと、見聞きしてきたことがそれぞれ1ピースのブロックになっていると考えれば、その組み合わせは天文学的な数字になりますよね。
情報デザインの先駆者として知られるリチャード・ソウル・ワーマンが著した『情報選択の時代』という本の最初のほうに面白い問いが書いてありまして、それはパーティーにお客さんを呼ぶとして、帽子の並べ方は何通りあるかと考える、というもの。例えば、到着順に並べる、家の距離が遠い順に並べる、名前順に並べる……など、帽子ひとつとっても、いろんな組み合わせが考えられることに気づきます。帽子そのものは変わらないのに、並べ方の違いで意味付けられることは違ってくるんです。単純な話ですが、はっとしませんか?
“unlearn”は一見「ゼロベース思考」に近い考え方ですが、「ゼロ」からスタートはしない。リセットするわけでもない。あくまでも解体するだけ、そんな感じです。
自分が学んできたことを常に解きほぐす、そしてそれらから再構築すること。このことがアイデア、クリエイティビティの源泉になるのだ、と思うので、みなさんも一度意識されてみてはいかがでしょうか。
――クリエイティブな人材を育成していく上で、大学教育にどんなことを期待されますか。
高広 「クリエイティブな人材」という言葉自体がなんか恥ずかしい言葉な気がしますけど(笑)、「クリエイティビティを発揮できる人材」ということでお話しすると、大学や大学院では、社会に出て一見無駄になるようなことをやっておくというのが大事だと思います。最近の傾向として、社会に出てすぐに活躍できるように、大学教育で「実学」を重視すべきだという意見もありますが、僕は全く逆の考え。むしろできるだけ抽象的なことや理念的なこと、実学にはほど遠い、「考えること」を訓練するような教育をもっと増やすべきだと考えています。海外の人と仕事をしていると、「日本人はどうして抽象的な概念でものごとを考えられないんだ?」と言われることが結構な頻度であります。例えば海外のビジネスマンが日本でプレゼンテーションをしたとする。日本人の聴衆の中には、「わかるんだけど抽象的だよね」とか「より具体的なケーススタディがないとよくわからない」とか言う人が少なくない数でいる。「high-level presentation」というのは、これはスキルが高いとか、理論が複雑であるという意味ではなく、抽象度が高い内容のことが「ハイレベル」。でもほんと日本人ビジネスパーソンはこれが苦手。自分が見たことや体験したことやそれに準ずることでないとイメージができない、ものごとを考えられないのです。なので、哲学や論理学などの授業は、クリエイティビティを高めたり、グローバルでビジネスを行うためにはむしろ必要なことなのではないかと。
でもこうした勉強はなかなか社会に出てからはできない。時間もとれない。だからこそ若い人には、大学や大学院では社会に出てからは勉強できない、あるいは得られないような抽象度の高い学びをしてほしい。一見ビジネスには関係ないような無駄に見える学びこそが、社会人になってからでは培うことのできない“ものの考え方”を形作ります。なので、抽象度が高く、一見ビジネスにとっては無駄なこと、でも“地頭を鍛える”ことができるような学びを提供し続ける機関であってほしいと思います。

(撮影:今祥雄)