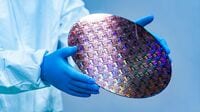日本人がイグ・ノーベル「連続受賞」の深い理由 雄が雌で雌が雄の虫から学ぶジェンダー教育
立教大学 理学部 共通教育推進室(SCOLA)特任准教授、サイエンスコミュニケーター
1977年生まれ。東京農工大学大学院農学研究科共生持続社会学専攻修了。2011年に青年海外協力隊としてアフリカのマラウイ共和国に赴任し、理数科教師として活動。帰国後、日本科学未来館の科学コミュニケーターや北海道大学の特任助教などを経て現職。イグ・ノーベル賞に関する番組解説や企画監修などを行う「イグおじさん」としても活動している
chapter.01より抜粋
なぜ、サイエンスコミュニケーションに興味を持ったのか
古澤 何をサイエンスコミュニケーションというかってすごく難しくて、学校の先生が行っている理科の授業は、サイエンスコミュニケーションなのかって言ったら、大きな意味ではサイエンスコミニケーションだと言える。ただ、狭義ではもっと科学と社会の接点に着目するみたいな形になる。
私が、サイエンスコミュニケーション関わっていたけれど、 それを自覚するようになったのは、日本科学未来館に入ってから。私が日本科学未来館にいたときの館長は、日本人初の宇宙飛行士である毛利衛さんが館長だった。毛利さんのビッグビジョンとしては、日本人とかじゃなくて、地球に生きている人類自身がこれから生き残っていくためには、サイエンスコミュニケーションが必要だっていう、かなり大きな理念の下に動いていた。
ただ、地球自体を変えていかなければいけないっていうような話をするのに対して、実際、サイエンスコミュニケーション自体の認知度がどうなのか。サイエンスコミュニケーターの人数がどうなのか。未来館の場合、50人ぐらいサイエンスコミュニケーターがいるが、それも国の事業では行われているものの、未来館だけでは足りない。
大学でもいくつかサイエンスコミュニケーターの養成機関はあるが、やっぱりその数も多くない。養成機関のようなサイエンスコミュニケーションを学べる場所が増やせないかということで、私自身もいくつかそういった大学を動いて、拠点作りに関われればいいなということで関わるようになった。
【タイムテーブル】
00:09~ これまでの経歴とサイエンスコミュニケーション
02:57~ 研究テーマについて
04:46~ なぜ、サイエンスコミュニケーションに興味を持ったのか
06:47~ 子どもたちにとっての学校の役割とは?
08:23~ 学校での学びは社会で役に立つのか