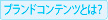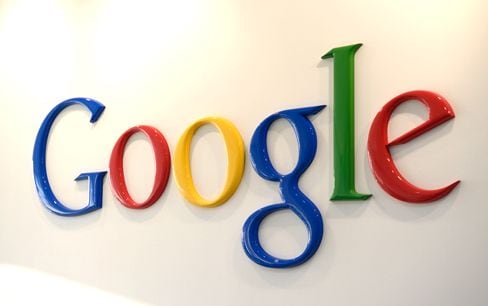Access Ranking
学校を卒業して会社員になる。今では当たり前のことが、その昔、当たり前ではなかった。サラリーマンという職業が生まれたのは、長い歴史から見ればつい最近のことだ。
場所に縛られ、時間に縛られ……とサラリーマンという職業を窮屈に感じている人もいるかもしれない。しかしサラリーマンの原型が最近できたことを知れば、もっと自由な発想で新しい働き方ができるかもしれない。
早稲田大学教授の原克(はらかつみ)さんを訪ね、話を聞いた。

立教大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻博士課程中退。85~87年、ボーフム・ルール大学客員研究員、2001~02年、ベルリン・フンボルト大学客員研究員。専門は表象文化論、ドイツ文学。19~20世紀の科学技術に関する表象分析を通じて、近代人の精神史、未来を志向する大衆の文化誌を考察・展開している。著書に『アップルパイ神話の時代』(岩波書店)『ポピュラーサイエンスの時代』(柏書房)『サラリーマン誕生物語 20世紀モダンライフの表象文化論』(講談社)など多数。
戦争と震災と
男と女、そしてサラリーマン
―――現在のサラリーマンの原型はいつごろから誕生したのでしょうか?
原:サラリーマンが誕生したのは、20世紀初頭の1920年代と言われています。先駆的な流れは明治維新直後からあるのですが、無視できない社会集団としてはっきりとかたちをなし、俸給生活者としてサラリーマンと自称するようになったのはこのころからです。
具体的には大正3~8(1914~1919)年の第1次世界大戦直後、つまり、1920年以降の産業構造の変化の中で、頭脳労働者として事務職層のボリュームが増えていったのです。そこで現在のサラリーマンの原型ができあがったと言っていいでしょう。
同時に今で言うOL、つまり、職業婦人も事務員、タイピスト、電話交換士として男性同様に増加傾向にありました。
興味深いのは、それ以降もずっと職業婦人が増えていったことです。きっかけは大正12(1923)年の関東大震災です。なぜかといえば、震災で夫を亡くした女性がいたからです。震災でたくさんの命が失われ、旦那さんが外で働いて、奥さんは家にいるという生活構造が立ち行かなくなってしまったのです。
そのため、女性たちは「台所から街頭へ」というスローガンのもと社会進出を果たし始めるのです。その結果、女性の労働人口は大正初期の43万人から、関東大震災を経て昭和初期に至るまでには87万人とほぼ倍増しています。
―――1920年代に男女ともに働き方の大きな変化があったのですね。
原:大事なのは、これは日本だけの現象ではなく、同時期にヨーロッパ先進国でも同じ傾向が見られることです。主にドイツ、フランス、イギリス、アメリカも含めてですが、サラリーマンが増えたのは1920年代であって、それ以前でもそれ以降でもない。
ヨーロッパの女性の社会進出でも、やはり第1次世界大戦が大きく影響しています。ドイツ、イギリスなどは参戦当事国ですから、男性は戦地に駆り出される。その結果、オフィスの労働者が払底し、女性が進出してくるわけです。
世界的にも1920年代がサラリーマン、OLの誕生年だったと言えるでしょう。
能力のないサラリーマンでも
会社に残れた理由
―――サラリーマンの登場で仕事のスタイルはどう変わったのでしょうか。
原:そもそも日本の近代モデルは西洋の思想哲学を参考にしてきました。多くの先導者がいるなかで、欧米に留学経験のある新渡戸稲造(農学・教育学者、当時の言論界のスター)は実業において日本の近代化をいかに進めるかに腐心した人でした。
当時、サラリーマンに人気のあった経済誌『実業之日本』に新渡戸は毎号欠かさず論説を寄せています。とりわけ明治30年代から大正初期にかけて相当開明的なことをいろんなかたちで言っているのです。
では、何が開明的であったか。要するに「タイム・イズ・マネー」という実に明快な金言を提唱したのです。そのために最小限の労力で最大限の成果を上げる方法論を説き、もっと効率的な仕事をするために欧米の最新器具を紹介しました。
そのころ日本の仕事のスタイルがどう変わったのか。いろんなエピソードがあるのですが、例えば、その1つにオフィス用具が挙げられます。「コムトメーター計算器械(小型の卓上計算機)」「自動鉛筆削り機」「新式ホチキツス」などのオフィス用具が日々の仕事に欠かせない欧米の「最新式の執務器具」として紹介されたのです。
いずれもそれまでのムダな事務作業を省き、サラリーマンの仕事を効率化するものとして使用されました。
―――新しいオフィス用具の登場は仕事の内容にも影響を与えたのでしょうか。
原:日本だけでなく、アメリカでもオフィスは男性の職場で、そこに女性が進出したとき、女性はいったい何ができるのかという話になりました。女性はそもそも仕事の訓練を受けたこともなく、書類の書き方や、業務上特有の文章の言いまわしにも習熟していないわけです。したがって仕事ができないとなるはずですが、そうはならなかった。なぜか。一言で言えば、非常にありがたい筆記用具があったのです。それがタイプライターです。
タイプライターという新しいテクノロジーが登場することによって、文章を書く、文章を練る、という仕事の内実がかなり変わっていきました。
その象徴が秘書です。英語で「セクレタリー」と訳す秘書という言葉は、じつは2番目の意味で、本来の意味は書記長、古くは枢密官、今なら官房長官、事務次官、つまり事務方のトップを表す言葉だったのです。
かつてヨーロッパの宮廷には必ずセクレタリーがいました。それは王様が書いたメモをきれいに書き移す単なるコピーの仕事ではなく、文案をつくる人だったのです。
いわば、王様の思想の内実を構築する人でした。その役割をもって初めてセクレタリーの名称を与えられるきわめてステイタスの高い役職だったわけです。そうした本来の役割がタイプライターの登場によって変容してしまったのです。
―――その結果、今では秘書は女性の仕事だと認識されるようになった。
原:その前にもう1つ段階があります。もしタイプライターが目の前にあっても、文案能力をもった人でなければ、文章を必ずしも書けるわけではありません。
では、そこで何が始まったのか。分業です。つまり、文案を考える人と実際にタイプを打って清書する人を分けたのです。
さらに面白いことに、オフィスは男性の職場でしたから、最初は分業も「文案を考える男」と「その能力のない男」で分担されていました。ところが、先ほども言ったように第1次世界大戦でオフィスに男性が減ってくると、「文案を考える男」と「タイプを打つ女」で分業するようになったのです。
では、「能力のない男」はどこへ行ったのか。会社を追い出されたわけではありません。家族制度などの社会通念上、男だからという理由だけで別の部署に配属されたわけです。
今考えれば、そこで能力主義が徹底されなかったがゆえに、現在の男女の働き方も男性優位になってしまったのかもしれません。

いつからサラリーマンは
出世を望まなくなったのか
―――当時のサラリーマンの1日の過ごし方はどんなものだったのでしょうか?
原:江戸時代の丁稚奉公ならば、勤務時間などの明確な線引きはなく、仕事とプライベートの区切りはファジーなものでした。それが明治時代になって西洋のビジネス、会社の概念が入り、雇用関係、契約関係が導入されたことで、勤務時間という概念が生まれました。
例えば、三井、三菱や官庁など大規模なところでは、始業から終業まで時間が決まっていました。大抵は朝9時~夕方の4、5時までです。それ以外の会社でも大手に合わせるかたちで、時間の使い方が統一されていきました。
その時間管理ためにタイムカードが登場します。このタイムカードを最初に日本に紹介し、さかんに勧めていたのが、経済誌『実業之日本』と新渡戸稲造だったのです。
このタイムカードの登場によって始めて、労働が時間単位で計測されるようになり、金銭的に労働を平等に計測するうえでの、ものさしとなったのです。
―――オフィスの働き方に大きな変化を与えたものはほかにありますか。
原:まずは電信、電話ですね。それに電送タイプライター、電送写真、今でいうファクシミリですが、そうした遠隔情報テクノロジーでした。導入によって事務連絡のために、わざわざ先方に出向かなくてもよくなった。時間の使い方に相当な影響を与えたでしょうね。
今もそれはパソコン、スマートフォンと加速されており、もしかしたら将来は出張自体がなくなるかもしれない。そんな将来を予見できるものが当時からあったわけです。
いわば、明治末期から大正、昭和にかけて、3~5年単位で新しい技術が出てくることによって、時間の使い方が大きく変わっていった。同時にIT技術の進化の原型もそこでできたと言えるでしょう。
―――オフィスで働くサラリーマンの大量発生で労働観はどう変わったのでしょうか。
原:一番の大きな変化は「立身出世」という意識が希薄になったことです。当時の『実業之日本』にもそうした論説があります。
戦国時代になぞらえたその論説では、明治維新から大正初期までのサラリーマンは「戦国時代の武士」だったと言っています。百人百様で、それぞれが天下を獲ろうとした。基本的には“俺は一国一城の主になるぞ"という気概があった。
会社に属していても、その会社で人生を真っ当したいと微塵も思っていない。今この会社にいたとしても、本当の目標はその先にあるという眼差しが常にあったということです。
それに対して、大正中期から昭和以降のサラリーマンは、「江戸時代の武家階層に属する武士」であったと言います。武士階級として確立された中での武士。言ってみれば、各藩の藩主にお仕えするのが仕事ですから、最終的に目指すところは家老なのです。まかり間違っても下剋上で藩主のクビをとってやろうとは誰も思わない。
戦国武士は見ようによっては荒々しく、ときに非人道的かもしれない。目標のためには破壊も躊躇しない。一方、江戸時代の武士のほうが、倫理的に確立された「武士道」という立派なものを持っている。それに比べると、戦国時代の武士には倫理観はまるでない。
しかし、その論説では倫理観がいいからと江戸時代の武士を誉めるのはどうかと疑問を呈しています。
戦国時代の武士には将来こうしたいという先を見る眼差しがありましたが、江戸時代の武士には藩のシステムの中でしか動く発想がない。「主君あっての俺」しかない。しかも藩から転職できない。辞めれば、浪人になるしかない。
この比喩はなかなか秀逸だと思いました。この論説が出たのが昭和7~8年ごろ。そのころのサラリーマンから、今に続く「会社あっての俺」という考え方があったのです。

過去に縛られるな
可能性に力を尽くせ!
―――サラリーマンの働き方はこれからどう進歩するのでしょうか。
原:例えば、科学は進歩すると言います。その際、進歩は常に直線的に成されてきたと我々は思いがちですが、じつは問題を解決する可能性がたくさんあるなかで、たまたまある1つの方法を選んで進んできたに過ぎないのです。
歴史は迷いながらジグザグに進んでいるもので、一直線に進んできたわけではありません。私たちはいつも歴史の最終地点にいると思いがちですが、見方を変えれば、私たちは毎日、歴史の最先端にいるのです。
私たちの目の前には無数の可能性があります。後を振り向けば、歴史は意味のある1つの固まり、出来事の連なりのように思えますが、それもたまたまできたものであり、そこに縛られていては何の意味もありません。
それよりも無数の可能性のどれを選ぶのか。そこを考えるために、自分の力を尽くしたほうがいいと思います。

(撮影:風間仁一郎)