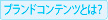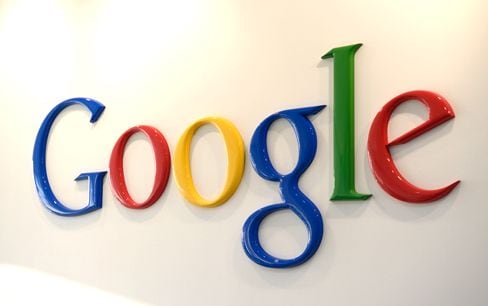Access Ranking
私たちが今会社で働くとき、一番欲しい充実とはいったい何だろうか。それはおカネなのか、ステイタスなのか、それとも仲間との一体感なのか。考えれば考えるほどわからなくなってくる。でも、一つだけ確かなのは仕事自体の面白さではないだろうか。仕事が面白くなければ、たくさんおカネをもらっても、どんなにステイタスが高くても、仲間がいてもつまらないはず。では、どんな組織であれば、仕事はもっと面白くなるのか。今回はスペシャル版として、サイボウズ社長の青野慶久さんが「ほぼ日刊イトイ新聞」の糸井重里さんを訪ねて、ともに仕事を面白くするチームや組織づくりについて探ってもらった。
※ 対談の前編はこちら
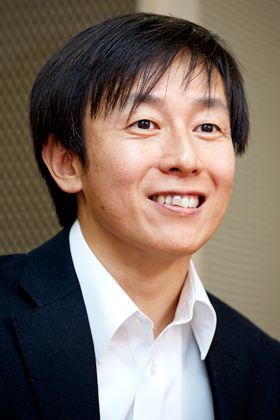
1971年生まれ。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工に入社。97年サイボウズを愛媛県松山市に設立し、取締役副社長。2005年4月に代表取締役社長に就任。
誰もが順番にリーダーになれる組織づくりとは?
青野 糸井さんは社員を怒ったりするのですか?
糸井 厳しさは、言わなくても厳しいに決まっているんです。面白く何かをするというのは、ヘラヘラしながらできない。「みんなでやろうぜ」と決めたことは、かくれんぼをするのだって厳しいじゃないですか。真剣に隠れて見つからないようにしないと面白くないですから。そんなときに「そこまでやるか」というバカが1、2人いると、そのゲームは急に水準が上がるんです。
僕がやっている厳しさというのは、その“バカの役”です。企画が出てきたときに、まず一番文句を言うときというのは、一枚の紙を見て、「できてるけどさ」と言うとき。ボツって意味なんです。
そのままお客さんに出しても大丈夫だろうなという水準のものって一番危ないんです。なぜかと言えば、それは市場をつくっていないからです。
つまり、ドラッカー流に言えば、僕たちの仕事は常に「市場の創造」なんです。「市場を創ってないね」と言ったら、みんな気づくわけです。
青野 私も会社を立ち上げて16年で、もともと経営には興味がなくて、基本的にはコンピューターおたくだったのです。でも、社長をやることになって経営を勉強したら面白くなりました。
私が思っている経営者の最大の仕事とは、糸井さんがおっしゃった「1人バカになるヤツがいないと盛り上がらない」ということです。
その意味で、スティーブ・ジョブズはわかりやすいですね。あまりにも仕事にこだわるからこそ、周りのモチベーションも上がってくる。もしリーダーが一つだけ持っておくべきものがあるとすれば、それなんじゃないかと思います。
糸井 確かにそう思いますね。一方で僕は、その役を誰でも順番にできたらいいとも思っています。一人だけに頼るのではなくて、ある仕事で「これ、誰がやったの」と聞くと、「あいつですよ」「えっ、あいつ、そんなところがあったんだ」というように、急に成層圏に出ちゃうようなことを、こないだまで静かだったヤツが成し遂げてしまう。そういうチームをつくってみたいですよね。
僕は映画「がんばれ!ベアーズ」が好きなんですが、それが一つのフォーマットになっています。要するにヘタクソな子を集めて、少しずつうまくいく喜びを得て一人ずつが変わっていく。そういう組織を目指したくなるんです。

1948年生まれ。コピーライターほか、作詞、小説、エッセイ、ゲーム制作など様々な分野で創作活動を行う。98年『ほぼ日刊イトイ新聞』を開設。
組織にはマニュアル化できない部分がある
青野 私の会社も400人くらい社員がいるんですが、全員が全員違うんです。それぞれこだわりが違いますから、そのこだわりが活きる場所でそれぞれ仕事ができるように努力していますが、難しいですね。
糸井 これまで組織や評価で、人に係わる部分の研究は続けられているのですが、じつはまだ確立されていないんですね。
例えば、クロネコヤマトの宅急便をつくった小倉昌男さん(ヤマト運輸元会長)も著書の中で、「人事については結局、俺は何もできなかった」と引退してから、おっしゃっています。非常に優れた経営者である小倉さんでさえ、何もできなかったと言っているんです。
そこに人というものを考えるときの逆の大きなヒントがあると思っています。わかると思い過ぎると、結局、ルールを万全につくれば、うまくいくという幻想を生んでしまう。
もし会社で困ったことがあっても、“バカの役”の社長がよくやることですが、「ここは俺がお縄を頂戴してでもやりたいんだよ」と言えば、みんなは説得されたりしますよね。
そういうことが結局、マニュアル化できない部分なのです。誰が責任をとって、誰が一番やりたいのかということを、みんなが同じ目で見ていることが大事なんじゃないでしょうか。
科学で人間とか組織というものをうまくコントロールできるという幻想を持つと、どこかで官僚主義的になったり、褒めるだとか罰を与えるだけになってしまう。
そもそも人間はそんな都合のいい生き物ではありません。グズグズしていても、愛すべき目をもって、あの人の笑顔を見たいと思えたほうがいい。
先日、任天堂元社長の山内溥(やまうち・ひろし)さんのお葬式にお伺いしたとき、僕ら山内さんとよく会っていた人間同士がしゃべるとついつい泣いちゃうんです。普段そんなヤツらじゃないんですけど、近くで彼を見ていた人たちと昔話をしていると「あっ、俺たち好きだったんだね」と。気づいてなかったんです。
山内さんが、どんな無茶を言ったとか、そんな話ばかりが聞こえてくる。だけど、社長がちょっとニヤっとするところが見たかったとか、大きく褒めてほしいわけじゃないんです。それだけある種の説得力を人間として持っていたんでしょう。
亡くなると業績ばかりが語られますが、業績は結果にしか過ぎないんです。それよりは、そこに存在があるという状態が素敵だと思うのです。そういう面白さは自分も味わいたいですね。
青野 私も社長になって、社員に言うことを聞けと言っても聞かないものですから、悩んでいろいろ本を読んだりしました。糸井さんの会社も糸井さんのレスポンスを期待している社員が少なくないと思うのですが、その自覚はありますか?
糸井 それはないです。僕自身が頼ってはダメだと思うんです。そしたら僕は「俺を好きになれ」というパフォーマンスを最大化したくなるでしょう。
むしろ「何もサービスしませんよ」というところから、一緒にやりたいと言われるだけのアイデアや仕組みなどをつくるのが自分の仕事だと思っています。
人っていいかげんなところがあって人なのです。過剰に何かを望んじゃダメで、できるだけさっぱりとしていたいですね。ただ、それでもチームで仕事をするのが一番面白いんだって言ってほしいです。

当事者意識はアイデアの核の磁力から生まれる
青野 昔はチームのゆるさとか、いいかげんさが良い仕事に結びつくことがあったようですが、今はそれがどんどん排除されていく方向にあると思います。
糸井 いいかげんさというのはちょっと神話化されている気もするんです。昭和の時代は貧しいところから右肩上がりで行かざるを得ない産業構造をしていたわけですから、サボっている会社でも儲かっていたんです。それを物語として描くと面白い逸話がたまたまできたということでしょう。
しかし、今は普通にしていると結構行き詰る。しかも行き詰るのが早いですね。あるサービスを始めても、すぐに誰かがそのサービスをマネしてしまう。そこでの競争というのは、昭和の人が感じていたものとは全然違うわけです。
僕は「余裕だ、ゆとりだ」というより「ムダなことも面白い」ということを会社が組み込むことではないかと思います。個人が趣味で考えたことがそのまま仕事になる時代、そうした面白さを活かせるかどうかが、とても重要になってくる気がします。
青野 それぞれの社員が当事者意識をもって仕事に取り組むには、どうすればよいと考えますか?
糸井 当事者意識はどうしても持てるときと持てないときがあるものです。でも、もし魅力のあるコンテンツの提案があったら「やらせてください」と、みんなが当事者意識を持ちたがるでしょうね。問題は最初の核になるアイデアです。「つまらないことを考えたんでけど一緒にやらない」と言われても、やりたくないのは当たり前。問題はアイデアの核の磁力なのです。
(撮影:谷川真紀子)