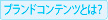Access Ranking

サッカーのために逆算して、生活すべてを自己管理
――同志社大学のご出身ですが、志望された理由は何でしょうか?
宮本 18歳でプロサッカー選手になることを選びました。でも、サッカーだけでは何か足りないのではないか。ほかにも何かを学びたい。そう思ったのです。同志社大学は当時の自分にとってプロサッカー選手としてオン活動をしながらも学びやすい環境であり、理想的な学校でした。学部は、より人間の生活に近い学問だと思って、経済学部を選びました。
――大学在学中には、どのような学びや活動をされていましたか。また、人との出会いなど印象に残っているエピソードはございますか。
宮本 大学に入って、「サークルってどうなってるんやろ」と思い、テニスサークルの練習会に一度参加したことがあります。それもガンバ大阪の先輩のクルマにわざわざ乗せてもらってです(笑)。そのころは、大学の生活とプロ選手としての活動を両立する生活を送っていました。火曜から金曜の午前中は練習があり、午後から大学。行ける時間が限られていた分、集中して勉強していましたね。
でも、ほかの大学生から見れば、私がサッカー選手であることは、効率の良いアルバイトをしているように見えたのかもしれません(笑)。当時のガンバ大阪のトップクラスの選手の中には月に数百万円以上もらっている選手もいましたし、私たちも試合に出場して勝利するとボーナスをもらえましたから。でも実際は、お金を使う暇はほとんどなく、練習ばかりしていましたね。

――大学卒業後、本格的にプロ選手としての道を歩まれることになります。
宮本 大学3年生の頃には、年間で30試合ほど出場できるようになり、ずっとプロでやっていくという決意を持つようになりました。実際にプロ選手になると、毎日が勝負です。レギュラーのポジションをつかんでからは、絶対にそのポジションを人に渡したくないと思うようになります。そのために、ケガをしない、風邪を引かないように注意する。さらにメンタル面などを含め、生活のすべてをサッカーのために逆算して自己管理していました。
結果を出そうと考えすぎてはいけない
――試合に臨む時は、どのようにメンタルをコントロールされていましたか。
宮本 自分の気持ちが高ぶり過ぎて失敗したことがあります。それがシドニーオリンピックでの試合でした。久しぶりのスタメンだったこともあり、「結果を出そう、出さなければならない」と考え過ぎて、逆にパフォーマンスを上げることができませんでした。
その時から、気持ちの高ぶりは試合の直前に持っていかなければダメだと考えるようになりました。試合までにいろいろと準備はしますが、気持ちを入れるのは最後でいい。そう気づいてからメンタルをコントロールできるようになりました。2002年の日韓ワールドカップの試合直前も、心地良いプレッシャーはありましたが、変な緊張感はありませんでした。
――緊張しないためのルーティンワークはありますか。
宮本 自己流として、まず靴下を左足から履き、シューズも左足から履き、最後に左足からピッチに入るようにしています。食事は特にありませんが、ガンバ大阪のホームゲームの時は、うどん、餅、バナナを食べた後、カステラを一片食べていました。食事は試合の3時間半前までにとっていましたね。

「なぜ失敗したのか?」論理的に反省する
――試合で結果が出なかった時は、悔やむものですか。
宮本 もちろん悔やみますね。ナイターの試合ですと、特に寝つきが悪くなります。でも、1~2日経って、新しい練習を始める時は、気持ちを切り替えるようにしています。次の試合で良いパフォーマンス、結果を出すことでしか、悔しい気持ちを晴らせませんから。
――経験を積むごとに、後悔することは減っていきますか。
宮本 後悔する回数は減るとは思いますが、なくなりはしません。そもそもサッカーはミスが当たり前のスポーツです。監督であれば采配が良かったか考えますし、選手ならばあの練習をもう少し突き詰めておけばよかった、などと考える。そうしたことの繰り返しです。
――自己反省の連続と言えるわけですね。
宮本 そうです。選手時代も監督になってもそうですが、失点したシーンは覚えています。なぜやられたのか。次にやられないようにするにはどうすればいいのか。それを選手に問うた時に、頭の中で再現できない選手はなかなか成長しません。なぜ失敗したのか。論理的に反省できるようにならなければ、良い選手にはなれないのです。
目標を持てばポジティブになれる
――サッカーの世界でも、失敗が選手の成長を促すということですか。
宮本 何度も同じ失敗を繰り返すようではいけませんが、「チャレンジしろ!」とは、いつも言っています。何事もチャレンジしてみなければわからない。チャレンジすべき状況がそろっているのに行かない選手には、「なぜ行かないのか」と指摘するようにしています。
――もし失敗ばかりを繰り返している時、どうすればモチベーションを上げることができるのでしょうか。
宮本 昔、うまくいかない時は、サッカーから離れてみることをしていましたね。映画を観に行ったり、普段とまったく違う景色を見に行ったり。一度離れてみると、客観的に見えてくるものがあるからです。

――オーストリア・ブンデスリーガのレッドブル・ザルツブルク時代には、ケガをされて、試合に出場できないことがありました。
宮本 一時は選手生命も危ぶまれました。ちょうど2年目のシーズンを迎え、気合を入れていた時で、ショックも大きかった。でも、しばらくして「しゃあないな」とポジティブに考えられるようになりました。その時から「いつ、どんな状態で戻れるのか」目標設定をすることにしました。「より強くなってピッチに戻りたい」。そう考えると、よりリハビリにも力を入れることができるようになった。目標を持つことで、よりポジティブに取り組むことができるようになったのです。
各人に何が求められているか? それがわかっていれば勝てる
――日本代表選手として、あるいは主将として、個性的な選手をまとめていくうえで、重視したことは何でしょうか。
宮本 2002年の日韓ワールドカップの際はベテラン選手の存在が大きく、若いチームを引っ張ってくれました。その意味で、06年のドイツワールドカップのほうが難しさがありました。チームがうまくいかないと、みんながそれぞれの意見を言い出してバラバラになってしまう。チームが一つにまとまり、勝つために一人ひとりに何ができるのか。何がそれぞれの強みなのか。再確認するようにしていました。
――そのために、特別にしたことはありますか。
宮本 腹を割って話し合うべく、一人ひとりの部屋を回りました。日本代表選手ともなれば、よく考えてサッカーに取り組んでいる選手が多いです。日本代表のメンタリティを変えようとしていたり、どうすればチームがうまくいくのか、つねに考えていたり。
また、当然ながら戦術的な理解度はそろって高いので、それぞれが何を求められているのかをはっきりさせれば、一つの方向にまとまっていくようになります。
――主将から見て、勝つ時のチームの雰囲気とはどんな感じなのでしょうか。
宮本 勝つ時は戦術的なことを言わなくても、それぞれがやるべきことを理解して実行に移しています。その中で各人の強みが出て、勝負を決めてしまうようなところがありました。勝つか、負けるか。試合前のロッカールームからわかる時すらあります。みんなの表情だったり、話している内容や声のトーンだったり。

負ける時は、ふわっとしたゆるさがあります。たとえば、2002年日韓大会決勝トーナメントのトルコ戦の前などは、まさにそうでした。ベスト16に残って、その先にいけるかどうかを懸けた重要な試合でしたが、あの時、なぜかロッカールームに漂っていたのは、ここまで来たという満足感、安心感でした。
言うべき時は言う。それがリーダーの役目
――そうした雰囲気をコントロールすることはできないのでしょうか。
宮本 やはり難しいところがあります。ゆるい雰囲気が危ないと気づいていた選手もいましたが、全体的にもなんとなく違和感があったのです。それまでと違う陸上トラックのついたスタジアムだったり、トルシエ監督がそれまで紺色だったスーツをベージュのスーツに突然変えたり。いろんな要素がいつもと違っていた。何とも言えない雰囲気がありました。
――主将としては、どんな気持ちで試合に臨まれるのですか。
宮本 自分個人が活躍するというよりも、結果的にチームが勝つために自分は何ができるのか。そればかり考えています。チームにとっては勝つことが一番良いことです。勝利に到達するために、できることは何でもやる。それは監督になった今も変わらないことです。
――リーダーの出番はどんな時に来るのですか。
宮本 チームが勝つ時は、誰も何も言わなくても、すべてが良い方向に向かう時です。一方、歯車が狂った時は、どの時点で誰が何を言うのかが大切になります。誰も何も言わなくなった時こそ、リーダーの出番です。「問題はここにあるから、こうしよう」と指摘する。ときには厳しいことも言わなければならない。一瞬の痛みが伴うかもしれませんが、誰かが何かを言わないと始まらない時があるのです。それがリーダーの役目だと思っています。
チームが成功する条件は、お互いを「信頼」すること
――時には悪役になったりもするのですか。
宮本 そうですね。現役時代を振り返ると、自分も甘かった部分があると思います。あまり事を荒立てたくないから、言うべきところで言えなかったこともありました。きちんと言うべきことを言って、それがチームの勝利につながるのであれば、リーダーの役目としてしっかり全うすべきです。
――その意味で、リーダーの仕事の基本原則とは何でしょうか。
宮本 最近は監督として考えることが多いのですが、まずは練習や戦術を練る「準備」が大事だと思います。次が「観察」です。私はつねに選手一人ひとりの状態を見ています。そして「予測」です。つまり、何が起こるのかを予測して、準備をするということです。
そもそも、サッカーは不確定な要素がたくさんあります。ビジネスではよく「仮説」と「検証」と言われますが、サッカーの場合は、仮説を立て、なぜ問題が起こったのか、必ず検証するだけでなく改善が必要になってきます。次の試合を見据えた、この「改善」という作業が非常に重要なのです。

――では、チームが成功するための条件とは何でしょうか。
宮本 それは選手同士の「信頼」を、日々の練習の中で築くことです。たとえば、ある条件の中で「この人はこんなプレーができる」ということを選手同士で共有する。そうすれば、「こんな時はあいつに任せることができる。俺はこちらのプレーをやろう」と考えることができる。一人ひとりの選手の力を信頼してこそ、それぞれが力を発揮できるのです。
日本のチームには組織力がある
――日本と海外を比べて、信頼に対する考え方の違いはありますか。
宮本 日本の選手のほうが、チーム内でメンバーをバックアップしようという気持ちが強いと思います。海外の選手は、「自分の持ち場は自分でしっかり守れ」「自分の責任は自分で果たしてくれ」という感覚です。海外のほうが個人に任せる部分は大きいですね。
チームとして規律が取れているのは日本であり、より組織力があると思います。海外は個の力でそれぞれがプレーをしていますが、ときに高い次元でお互いの考えを自然発生的に共有できた時、力を発揮すると思います。
――ワールドカップで勝ち進んでいくチームは、やはりチーム力が抜きん出ているのですか。
宮本 抜きん出ているところもありますし、抜きん出るように仕向けられているところもあります。たとえば、ドイツでは普段プロチームでライバル関係にある選手でも、一緒になって戦わなければならない時は宿舎で共に生活させることで協調性を育んでいく。そうしたチーム運営の効果がピッチ上で現れる時があります。
ほかにも、アルゼンチンは真面目なイメージがあります。一方、ブラジルはロッカールームの前を通ると、みんなサンバを踊っていましたね(笑)。でも周知のとおり、実力は確実にある。すごいなと思いました。
――現役引退後は、日本の元プロサッカー選手としては初めて「FIFAマスター」に入学されました。そこでどんなことを学んだのでしょうか。
宮本 選手時代はがむしゃらにピッチの上しか見ていませんでしたが、「FIFAマスター」で歴史や経営、法律を学ぶことで、サッカーをもっと多角的に見ることができるようになりました。スタジアムに行っても、どんなスポンサーが付いているのか。どのクラブがどんなチーム運営をしているのか。サッカーを総合的な観点から見ることができるようになりました。

サッカーを通じて世界に貢献したい
――現在、ガンバ大阪U-23の監督として、どんなことを心掛けるようになりましたか。
宮本 主将と比べると、監督のほうが、チームリーダーとして考える物事の量がはるかに多いと思います。それぞれ個別の選手のことを考える必要がありますし、トレーニングメニューや試合相手のこと、さらにクラブ全体のマネジメントのことも考えなければなりません。選手としての面白味はもちろんありますが、今は監督の仕事を楽しんでいます。
――伸びる選手に特徴はありますか。
宮本 何事に対しても、耳を傾ける選手です。良い選手は必ず相手の話を聞こうとします。傾聴力というのは、若手選手が伸びていくためにとても大事な要素だと思います。
――宮本さんはボスニア・ヘルツェゴビナで民族融和のための、ある国際プロジェクトを進められているそうですね。
宮本 民族紛争により分断の傷痕が根強く残るボスニア・ヘルツェゴビナで、スポーツを通じた民族融和を目指す「マリモスト」プロジェクトを2013年からスタートさせています。これはFIFAマスター時代に勉強したグループ研究がもとになっています。
現在はプロジェクトリーダーとして、紛争で傷ついた街に復興の証としてサッカー場をつくったり、サッカーを通じて民族融和が進むよう地域の子供たちの交流を進めたりしています。16年10月にはスポーツアカデミーを開講し、将来サッカー選手を目指す子供たちをサポートしています。彼らにとって、サッカーは自分の夢を叶えるための一つの手段です。サッカーを通じて、これからも日本に、そして世界に貢献していきたいと思っています。

/1977年大阪府生まれ。同志社大学経済学部卒。10歳で本格的にサッカーを始め、95年ガンバ大阪入団。日本代表では各世代別で主将を務め、2002年日韓大会、06年ドイツ大会と2回のFIFAワールドカップでも、主将として日本代表を牽引した。11年12月、惜しまれつつ34歳で現役を引退。その後「FIFAマスター」に挑戦し、13年7月末に修了。現在はガンバ大阪U-23監督を務めている。また、ボスニア・ヘルツェゴビナで、スポーツを通じた民族融和を目指す「マリモスト」プロジェクト(http://little-bridge.net/)を2013年8月からスタート。現在はプロジェクトリーダーとして、16年10月にスポーツアカデミーも開講した