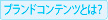Access Ranking
インタビューシリーズの第二回目は瀧本哲史氏。瀧本氏は意思決定に携わらないサラリーマンを「作業員」と呼ぶ。企業組織はほとんどの場合ピラミッド型をしており、その下部に属する人間は「作業すること」がその組織での役割だ。だが、スタートが作業員だったとしても作業員のままずっと他人任せの人生でもいいのか。瀧本氏の言葉の裏にある思いとは――。

東京大学法学部を卒業後、東京大学大学院法学政治学研究科助手を経て、マッキンゼーに入社。3年で独立し、日本交通の経営再建などを手掛けながら、エンジェル投資家としても活動する。NPO法人全日本ディベート連盟代表理事。著書に『僕は君たちに武器を配りたい』(講談社)など。京都大学客員准教授
もう、無料コンテンツは
読まないようにしている
瀧本 『週刊東洋経済プラス』は新しいウェブサービスということですが、いくらなんですか?
髙橋 月額2500円(7月31日まで)です。定期購読していただくと、雑誌の『週刊東洋経済』が毎週届いて、しかも同じ内容がウェブでも見られる、という形でスタートしています。『東洋経済オンライン』は今後も無料で続けて、『週刊東洋経済プラス』は課金する。2つを両立するという戦略です。
瀧本 そうか、ついに東洋経済も月額課金のサービスを始めるのか……。私が今連載を持っているのは『東洋経済オンライン』のほかには『クーリエ・ジャポン』だけですが、クーリエもすでに月額課金システムに移行しましたからね。
実は私はもう、無料コンテンツはなるべく読まないようにしています。たとえば私は移動にタクシーをよく使いますが、タクシーって移動時間を短縮して、なおかつ移動中も仕事ができる。つまり、おカネで時間を買っているわけじゃないですか。それなのにタクシーの中で無益なコンテンツを読んで時間を無駄にしてしまっては何の意味もない。編集におカネをかけてあって、ちゃんと取材しているコンテンツに触れないと時間の無駄ですよ。
いいコンテンツにはコストがかかるのが当然で、広告料だけではなかなか成り立たないはずなんです。実際、私が今いいなと思っているコンテンツはどんどん課金されていて、ある種の壁の向こう側に行ってしまっています。壁のこちら側には、ライターが安いギャラで書いた適当な記事が蔓延しているイメージです。
髙橋 今回4人の方に同じインタビューシリーズに出ていただくんですけれども、共通した質問が「30歳の頃にどんな情報を得ていたか」というものなんです。今のお話は年代を問わず、すごく良い参考になるはずです。そうすると瀧本さんは、いわゆる「まとめサイト」もご覧になりませんか。
瀧本 自分にはあまり関係ないですね。非専門家のブログなんかも同格で検証なく並べられていますから。ストレートニュースにも、誰もが言える一般論にも、ほとんど付加価値はない。ニュースを基にした突っ込んだ見解や、時間をかけた分析にこそ付加価値が生じるんです。コモディティ情報に基づいてコモディティ的な発言をすればその人自体もコモディティになる。ほかの人がタダで手に入れているものを手にしても、「その他大勢」になるだけですよ。
私に言わせると、ほとんどの日本のサラリーマンは意思決定をしない、ただの作業員です。でも今はたとえ大企業であっても、組織の上のほうの現状を見れば、これはヤバイという感じが漂っているじゃないですか。不祥事とか、身売りとか……。
最近、私のよく知っている大学生が大手商社に入社したんですが、内定前のインターン中に普段から「どうもエネルギー部門が危険だ」と感じていたので、最終日に「私の分析ではエネルギーが危ないと思うのですが」と役員に聞いたら、口ごもってしまったらしいんですね。
髙橋 今どの商社も資源で減損の嵐ですが、それを予見していたと。そのまま採用はされたんですね。
瀧本 ええ。そのあたりは、一流商社にはまだまだ度量がありますね。入社後もエネルギーではない部の配属を望んだそうです。そうしたらついにエネルギー問題が表面化した、と。彼は今も「上のいうことをそのまま信じていると、まさかということとがあるので、自分で分析して、上司と議論するようにしています」と話しています。

すべてのサラリーマンは会社の中である程度ゲリラ戦をする必要があります。ただの作業員Aのままでは、その戦いの中で死んでしまう可能性が高い。自分が会社で影響力を持てるようになった時にすぐに対応できるようにするか、今のうちから、見えない影響力のネットワークを作る。そのために今のうちから勉強しておく必要がある。もちろん、ビジネススクールに通ってもいいですが、いろんなケーススタディが載っている雑誌や質の高い有料サイトは身近にたくさんある。それらを読まずして、無料のストレートニュースだけであなたは10年後生き残れますか、という話です。
こう考えれば自然に有料課金ユーザーにならざるを得ない。たとえば私は普段からネットで『週刊東洋経済』を買ってますよ。
髙橋 ネットで、ですか。キンドルなどで読める『週刊東洋経済eビジネス新書』のことかな。
瀧本 ええ。何か過去のことを調べようという時に重宝します。特集ごとに売られているから買いやすい。紙の雑誌も、バックナンバーが置いてある書店に買いに行くこともあります。
髙橋 『週刊東洋経済プラス』は過去の記事も読めるんです。6月のサービス開始時点ではアーカイブはまだ弱いですが、着々と増やしていく予定ですので、請うご期待です。
瀧本 過去記事をまとめて見たいという時は、紙だと大変なことになるので、検索してアーカイブを見られるのは価値がありますね。ちゃんと取材していて、アーカイブ性があるものだったらおカネを払ってもいいと思います。
ビジネス書っぽい経済誌ではなく
経済書っぽい経済誌へ
髙橋 『読書は格闘技』(集英社)、拝読しました。12のテーマについて異なる切り口から論じている良著を「対決」させる内容で、おもしろかったです。せっかくですので「ラウンド13」として、『週刊東洋経済』も他誌と対決させてもらえませんか。
瀧本 たとえば、今元気がいい雑誌って『週刊文春』ですけど、やはりすごくコストをかけているんですよね。知り合いの編集者が「雑誌はこのままでは死ぬ」とよく言っています。「昔の雑誌はライターを『飼えた』」と。要はおもしろいネタを持ってこなくても原稿がひどくても、ライターを養成するために長い時間をかけて、囲い込んで養成できた。そこから一流のライターが生まれてくる。ところが、今はそういうことができる余裕のある出版社はどんどんなくなっているんです。

その結果、取材費かけてスクープする、売り上げが伸びる、おカネがあるから情報が集まる、というサイクルが回っているのは『週刊文春』ぐらい。実は昔、私も取材を申し込まれたことがあります。仕事場にも家にも来て手紙を置いていって。私がかつてかかわっていた業界のキーパーソンの情報収集をしていたようですが、その時は私はもうその業界は離れていたし、全くの無名で、その業界に詳しいことも外部にはすぐにはわからない。それでも追いかけてくる。取材は受けませんでしたが、彼らはここまでコストをかけるのかと思い知らされました。
文春はちょっとスキャンダラスですけれども、『週刊東洋経済』も腕とカネをかけられる雑誌だという印象があります。だから、経済誌の文春みたいな感じですかね。名前は伏せますが、実は私のゼミ生が御社に就職しているのですが、彼の仕事の仕方を聞いていると、かけているコストが全然違う。特集を作るサイクルや結果的にやらなかった特集の下調べ。同じ企業に同時期に取材していても「やりこみ」度合いが違う。やり甲斐があると言っていました。デザイン系もそう。この取材のカメラマンも社内で、かなり丁寧な仕事ぶりですよね。
髙橋 確かにコストはかけます。自宅への手紙作戦もよくやりますよ(笑)。記者だけでも社内に100人以上いますし、デザイナーも多く抱えています。実は第一回の糸井さんの時にも同じ話になったんですが、読者に質の高いコンテンツを届けるためには必要だと思っています。
瀧本 純粋な出版社であることも僕にはプラスに映ります。新聞社が発行する週刊誌は、よく言えばシナジーがあるけれど、雑誌を売らないと死んでしまうということにはならない。たくさんの不動産を持つリッチな大手出版社もありますが、東洋経済はそういうものもなさそうですので(笑)、ちゃんと雑誌を売らないと死ぬというような……。
髙橋 危機感、のような。
瀧本 そう。そういう意味で東洋経済は、社員が雑誌に賭けているという感じがすごくある。
髙橋 内容、企画に関してはいかがですか。
瀧本 ほかの経済誌は、読者がすぐ使えるノウハウ的なものが増えている印象がありますね。特集が「ちょっと差がつくパワーポイントのつくり方」みたいな方向になってきていて、経済誌がいわゆるビジネス書とだんだん近くなってきてしまっている。見方を変えれば、経済書っぽい経済誌というのが少なくなっているのかなと。
髙橋 その危機感は、私自身も編集長就任以前から持っています。ですから、いわゆる自己啓発ものや医療もの……『週刊東洋経済』でも認知症とか鬱とか不眠といった特集を頻繁に組んでいた時期があるんですが、「それって経済誌がやることなのか?」と反省して、今は意識的に減らしています。
瀧本 さっきも言ったように、ほとんどの日本のサラリーマンはただの作業員なんですけど、中堅になるにつれ、この会社の戦略を考えなきゃいけないとか、ほかの業界でやっている動きを自分の会社に取り入れたらどうなるかということも考えるようになる。経営判断をする立場に近づいていく過程で必要な情報源は何かと言うと、それは多分東洋経済になるのかなと思う。「日本の会社は動きも遅くて出世も遅いから、僕たちには関係ないし、まずはパワポをもっときれいにするか」、じゃないでしょ、と(笑)。
日本の未来を変えるのは
今の女子中学生たち
髙橋 もう長い間、出版危機が叫ばれていますが、瀧本さんが今注目されているテーマや読者層はありますか。
瀧本 日本を引っ張っていくような人材を養成するには、中学生の頃から自分で仮説を立てて世の中を変える意識を持ってもらう必要があるな、と。新しい本『ミライの授業』(講談社)は女子中学生を仮想ターゲットにして書きました。
髙橋 だいぶ年齢層を下げましたね。
瀧本 小学校の頃って女の子のほうが賢いしリーダーシップもあるんですが、中学校で精神的な変化があり、高校になると普通の人になってしまうというパターンが多いんです。だったら女子中学生に「君たちに世界を変えられるか」とあおったほうがいい。この本は実際の出張授業をまとめた内容ですが、授業でも女の子のほうが反応が良かったですね。「私もいっちょやってやろうと思いました!」って。
髙橋 頼もしいですね。ただ、中学生の女の子に何が起きてしまうんでしょうか。
瀧本 結局はモテたくなるのかな(笑)。大概の男子中高生は「いっちょやってやろう!」という女子より、ふわふわしたカワイイ女子を求めるというイメージがありますし、メディアがそれを強化しますから。
今の世の中の大きな流れからすると、ある種、傍流の人たちが新しい日本を作っていくと思っていて、私の関心の一つはそこにあります。
髙橋 いわゆる周辺の人たちですね。
瀧本 そうです。地方経済を変えるのは若者、よそ者、バカ者とよく言うじゃないですか。もう日本のメインストリームは書き換えられないので、この本では若い人、特に女性に日本を変えてくださいと訴えています。
『僕は君たちに武器を配りたい』を出した時、当初はそんなに売れるとは思わなかったんですけど結局13万部ぐらい売れたのかな。「この本が売れるぐらいなら日本は大丈夫だ」と思えた。同じように、今度は仮想ターゲットを中2の女の子に置いて……内容的には「中学生だから」という妥協は一切ないので、実際は親とか「日本を変えよう」と思う大人がメインターゲットになるのだと思いますが、また売れたら「日本もまだ捨てたもんじゃない」と思えるはずです。
髙橋 その時には『週刊東洋経済』も中2女子を特集しようかしら。その時は取材に行きます。最後に、瀧本さんの東洋経済観を教えていただけますか。

瀧本 せっかくなんで、ヨイショしましょうか(笑)。冒頭でも触れた『東洋経済オンライン』の連載についてなんですが、企業の広報担当者によっては、対談が終わった後になって「ここを変えたい、あそこも修正したい」と言ってくる。広告でもないのに。中には無茶苦茶な注文をしてくる人もいます。実際にそういうことが一度あって、そしたら連載の担当者が「じゃあ今回の記事はなかったということにしましょう」と言って、かなりのコストをかけてきたのにあっさり記事を潰したんですよ。企業となれ合っていない。東洋経済には経済ジャーナリズムがあると感じました。
髙橋 その話は知らなかったですが、うれしいですね。その担当者の名前教えてもらえます(笑)? あまり大上段に語るのもおこがましいですが、経済ジャーナリズム魂はずっと持ち続けていきたいですね。
 編集後記
編集後記
ちなみに瀧本さんは『週刊東洋経済』を直接競合する各誌とも詳しく比較して下さったのですが、相手のあることですので詳しくは書きません(笑)。ただ、今の路線を突き進んでいく自信が持てた気がします!
1994年に東洋経済新報社に入社し、会社・業界担当記者として自動車、製薬、空運・陸運、ホテル、百貨店などを担当。『週刊東洋経済』編集部では「人」を中心とした記事づくりをベースに、幅広いテーマで特集を制作。2014年4月より女性として初めての編集長に就任。早稲田大学政治経済学部卒