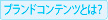Access Ranking
6月1日の『週刊東洋経済プラス』のサービス開始に合わせて始まったこの企画。『週刊東洋経済』の髙橋由里編集長が「会いたい」という理由で4人の人物にインタビューに行くのだが、第1回となる今回、糸井重里氏から告げられたのは「今、まったく雑誌読んでないんだよね」という雑誌の編集長には耳の痛い言葉。糸井氏の考える雑誌とは――、髙橋編集長が読者に訴えたい誌面とは――。

これまでの主な仕事は、コピーライター、エッセイスト、編集者、ゲーム制作、など。月間PV130万を超えるウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」主宰。「ほぼ」と言いながら、1998年6月6日の創刊から、一度も更新しなかった日はない。著書に『ふたつめのボールのようなことば。』など多数。1948年生まれ
上場はゴールではないからこそ
上場できたら1カ月休みたい
髙橋 ごぶさたしています。前回取材させていただいたのは去年の3月でしたね。「僕たち、『ほぼ』上場します」(2015年4月18日号)というタイトルの巻頭特集で。
糸井 あれは去年でしたか。今回ね、「編集長が会いたい」って企画書が来て、うれしかったです。「会いたい」と言われたことがたまらなく(笑)。
髙橋 そこに反応していただけるとは、こちらもうれしい限りです(笑)。あれから上場の話はどうなっていますか。
糸井 今僕の周りでは沈静化していますね。当たり前のこととして、しみ込んじゃったからかな。ただ、案外後ろ向きにとらえている人もいましたね。
髙橋 後ろ向きですか。それは意外です。
糸井 「お前ごときが」的なのはありましたよ。「うちの旦那の会社がどれだけ苦労してもダメだったのに、お前ごときが何を言ってるんだ」って。あとは、「『ほぼ日』のいいところがなくなっちゃうんじゃないか」って心配される人もいましたね。
髙橋 去年のインタビューでも「そういうところはさんざん考えた結果、上場を検討しているんだ」と話されていますが。
糸井 周りには僕が考えているようには見えなかったのかなぁ。でもやってます、ずっと、着々と。実は、もし上場ができたら僕は休もうと思っているんです。一カ月くらい。上場がゴールだと思ってる人というか、思いたがっている人がいっぱいいる。そうじゃないことをどう表現しようかと思った時に、答えが休むだったんです。本当に上場をゴールだと思ってる人は、休まずにやってるフリしますから。
髙橋 休まれている間に、『週刊東洋経済』で集中連載をお願いしたいところです(笑)。さて、今回の一つのテーマが「30歳の時にどんな雑誌を読んでいたか」、「どんな情報収集していたか」ということなんですね。糸井さんの30歳というと矢沢永吉さんの『成りあがり』(角川文庫)に携わられていた頃ですね。
糸井 そんな頃ですか。「やりませんか」と言われることが増えてきた頃ですね。「○○がやりたい」というよりも、「やってみませんか」「やりませんか」と持ちかけられてきて、そんなに忙しくないんで、「やれたらやるけど、やれるかなぁ」「やれますよ!」「そうかなぁ」って言って引き受けるという感じでした。非常に受動的で、そのうえ鼻の下を伸ばしている、というような時期でしたね。
髙橋 20代はだいたい「これがやりたい」「俺が、俺が」となりがちですけど。そういう20代の時期を通り越して……。
糸井 いや、20代はもっとあきらめてたんです。何かやりたいって言ってもできるものじゃないし、ホントに夢も希望もなく、くたびれてたんです。大学も中退してるし、「こんなワタクシがおカネもらっていいんでしょうか」みたいな気持ちもあって。だから、できることがあればお役に立ちたいっていう気持ちはありました。そしたらちょっとずつ「やらないか」ということが増えてきた、というのが本音ですね。
髙橋 受動的でいるって、実は大変なことですよね。何でも受け止める必要がある。自分から「やりたい」と言う時は、自分の得意なことをやりたいと言えばいいわけですから。
糸井 そんな大したものじゃないんです。昔、雑誌『MEN'S CLUB』の知り合いの知り合いが編集者だったので、会う機会があったんですね。「連載とかやりたい?」って聞かれて、「あぁ、ハイ」って言ったら、「じゃあどういうことが得意なの、映画とかさ?」。正直に「得意なことないんですよね」って答えました。僕は、映画が得意とか自分で言うやつは映画をちょっと余計に見てるぐらいで大したことないって思ってたし、若いから生意気な部分もあって、「そういうのどっちでもいいんじゃないですか」って言ったら、「それじゃダメなんだよ」って言われて。でもなぜか連載をやらせてくれることになったんです。
プロレスのことを書いたりしてましたね。ある時、すごく首が強くて、首をどれだけひねっても大丈夫っていうプロレスラーが来日したんです。でも、「プロレスで首はかまれたりしないから、実はたいしたことないんじゃないか」って書くわけです(笑)。
酸素じゃなく窒素としてなら
雑誌も必要かもしれない
髙橋 当時はどんな雑誌を読まれていたんですか。
糸井 マガジンハウス系の雑誌は憧れでした。『an・an』や『POPEYE』とか、あとはマンガ誌かな。今で言う一般週刊誌は、熱心にではないけど、たまに読んでました。ああいう雑誌はやはり劣情を刺激しますから、南の島に行ったりするとまったくいらなくなるんですよね。心から劣情がなくなるんです。でも、日本に戻ると読みたくなる。
髙橋 セットなんですね。
糸井 当時はそうでしたね。ただ、今は極端に言うと、雑誌をまったく読んでない。
髙橋 それは雑誌というパッケージに魅力を感じないのか、あるいは載っている記事に興味を感じないんでしょうか。
糸井 載っているものかな。追い立てられるようにして情報に接するということを、僕はやはり無駄だなと思っていて。自分の言葉で考えていることだったら、時代性とか関係なく、しつこく考えるべきこともある。たまたまどこかの女の子が言ったようなことの中に考えるべきヒントがあるかもしれないとも思うわけです。
たとえば、今日は会社の全員ミーティングの日なんですね。それで話しながらふと思ったんですけど、地下鉄の表参道駅の誰もが見えるところにブラジャーの専門店がある。「あれはなんであそこにあるんだろう」って聞いたんです。そしたら、わかる人もいないし、買ったことがある人もいない。じゃあなんだってなったら、それは雑誌一冊買うよりも僕にとっては考えるにふさわしい題材なのかもしれない。
髙橋 そしたら雑誌がいらなくなっちゃいますね。
糸井 そうなんです。
髙橋 それは困ったものです(笑)。

糸井 ただ時々、週刊誌の「誰々の離婚が成立した」みたいな情報は入ってきていたほうがいい。それは窒素みたいなものです。人間は酸素吸ってるはずなんだけど、空気の中でいちばん多いのは窒素でしょ。だから、酸素だと思い込まなければ、雑誌も僕にとっては必要なのかもしれないですね。たとえば、雑誌で「ランチのおいしいレストラン」特集をしていて山形にある店まで載っている。そこにはたぶん行きっこない(笑)。でも、読んでいる時に旅をしている神経回路みたいのは刺激されているわけです。
糸井事務所が上場する話も窒素と一緒で、多くの人には差し支えあるような話でもないんですね。でも空気が全部酸素になったら火事だらけになって大変なことになる。だから窒素も必要なんだろうし、それも含めて人生なのかもしれないなぁ。
ピロンピロン♪(携帯が鳴る)
糸井 あ、すみません。(携帯を見て)あぁ、なるほど……。今、まさしく窒素的なメールが(笑)。実は昨日、『真田丸』(NHK大河ドラマ)のことを『ほぼ日』に書いたんですね。そうしたら、出演者の方がそれを見てうれしかったってメール送ってくれました。これも深く考えることじゃないですよね(笑)。もちろん芝居した人がうれしいと思ってくれたら、書いた自分もまたうれしいですよ。でも、会った時言ってもいいんだし。ブラジャーの売り場について考えるのもそういうことだし、今日の取材も「この人に今会うべきだ」じゃなく、あそこに行ったらなんかあるんじゃないかということでしょう? そう思われるのはとてもうれしいし、何でみんなうちに来てくれるんだろうかって考えると……、うちも結局窒素だらけだからかな(笑)。
髙橋 雑誌の存在自体も窒素というか、社会の一つの構成要素だというところはあるかもしれません。書店や駅の売店で、表紙の見出しが目の端に入る。「ああ、こんなことが今話題なんだ」と。並んでいるだけで実は雑誌の存在意義ってあると思うんですよね。もちろん、買ってもらいたいですが。
糸井 あらゆる雑誌の奥付に「どうもすいません」って書いたらどうだろう。今、スクープを連発している週刊誌は、もともと文学好きの人がその出版社に入社して週刊誌に配属されていたりするじゃないですか。そこで、自分が組織の一員として機能するために記事を書いているんですよね。その時に、「断罪する」ってところに結論を持ってくるんじゃなくて、断罪するとか間違って書いちゃったとしても、表3(裏表紙の内側)には「ホントに申し訳ありませんでした」って毎週毎週やれば、僕はすごく好きだな。「書かれている人もどうかと思うけど、でもそれ書いている俺もどうかと思うよ」という表明というか。漫才とか落語で「どうも失礼しましたー」とか「お後がよろしいようで」って言うじゃないですか。
ジャーナリズムというのも、もともとの意味をたどればただの騒ぎ屋という意味もあるんですよね。その手前で社会の木鐸論があったり、カウンターカルチャーとして権力の暴走を止める役割があるというジャーナリズム論があったりする。歴史の中では両方あったはずなんだけど、メディアがどこかで都合よく解釈して、つまり、おカネを出して買ってくれる人がいることを理由に「私たちは正しい」と言っているだけだと思うんですよね。
髙橋 なるほど。ただ、私は雑誌の騒ぎ屋的な部分は大事にしたいと思ってるんですね。東洋経済の記者は『会社四季報』の記事も書いているので、数字に強い人が多いんですが、であるがゆえに、かつては『週刊東洋経済』の記事も数字をずらっと並べたような記事が多かった。でも自分が編集長になった時に、それってつまんないよね、と思って。もっと騒がれている人物をどんどん載せたいよね、会社の人事一つにも騒ぎたいよね、と、実際そういう記事を増やしてきました。この前も、トヨタ自動車社長の14ページ独占インタビューを目玉にした「経営者 豊田章男」という特集を組みました。
インタビューだけで1万4000字くらいあって、いろんな人に「この分量はちょっと雑誌でしか読めないね」って言われたんですけど、こういう記事はやっぱり印刷メディアのいいところだなと再確認しました。『ほぼ日』は、元は長いインタビューでも何回かに分けて掲載されますね。
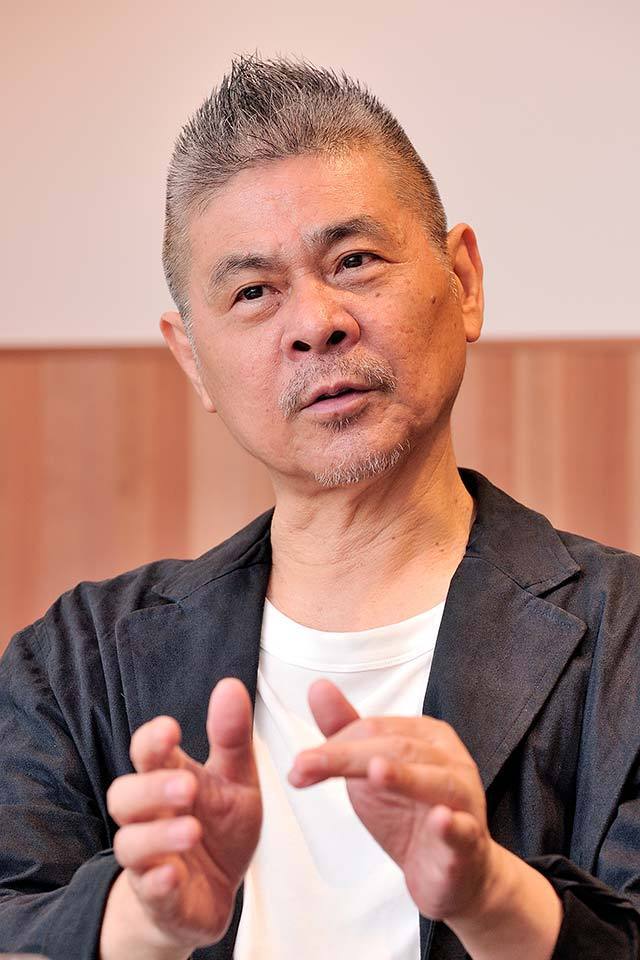
糸井 ちぎって載せられるのがネットの特性でしょうね。どの時間をお客さんからいただくか、という話だと思うんです。おカネ以上に、今は。ネットだと、「20分下さい」じゃもう長い。3分くらいですかね。でも、読み始めたら3分経っていたっていうのが理想。3分経ったら勢いで10分くらいいっちゃうからね。最初の3分は信用みたいなもので、好かれていたら3分はもらえる。そのうえで、もっと読みたくなるとか、人に言いたくなるとか、SNSでつぶやくとか、転がっていく可能性が増えるのがネット。雑誌は「俺が読もう」って取っておくでしょう?
髙橋 取っておく、という表現がまさにそうですが、雑誌ってとても個人的なメディアじゃないですか? 新聞みたいに家族みんなで読むものじゃなくて、自分で買って、自分一人で読む。そこには濃密で深い関係があると思います。
糸井 ぱらぱら開いていると副菜が目に入るのも雑誌ならではですよね。第一特集というステーキ食べるつもりだったけど、その前後にある短い記事というニンジンをつまんでみたりできる。『ほぼ日』でも「小ネタ劇場」という短いコンテンツが読まれる率はすごく高いですね。
髙橋 やっぱり、ニンジンみたいな……。
糸井 ニンジンというか、パセリくらいかな(笑)。
髙橋 私が30歳の頃読んでいた雑誌って『BRUTUS』なんです。当時、斎藤和弘さんが編集長をされていて。
糸井 斎藤さんって平凡社に入って徐々に頭角を現してマガジンハウスで編集長になった方でしたよね。斎藤さん物語、誰か本にでもしてないかな。絶対おもしろいはずですよね。
髙橋 あ、それ私やりたいな(笑)。当時、斎藤さんにインタビューして、「あらゆる雑誌はスキャンダルを扱うものだ」という言葉がすごく印象的でした。「たとえば、東京に2000軒あるイタリアンレストランを載せるだけだったら単なるカタログ誌だ。しかしそこにイタリアのレストランガイドの編集長が来て、ここはいい、ここはダメ、って鑑定して、その結果を載せたらスキャンダルになると思う」って。『週刊東洋経済』もスキャンダラスでありたい、と思っています。
糸井 それは「クリエイティブ」って言葉に置き換えられるんじゃないかな。最近、「スキャンダル」っていう言葉が前に出過ぎていると思うんです。僕は、「スキャンダル」って好かれない理由にもなると思うんです。友達になるのに、スキャンダラスなことばっかり言ってる人を選ばないでしょ。いつもスキャンダラスな情報持ってくるやつにカネ貸したくないですし。むしろ財布を隠しますよね。僕はそこは「クリエイティブ」ってことだと思うなぁ。
髙橋 そうか、クリエイティブな経済誌。おもしろいですね。
「ほぼ日」はまだ成功してない
自由でいられる権利を得ただけ
糸井 クリエイティブって価値が価値を呼び起こすことだと思っていて、それは主観なんですよね。みんながこう思うってものを持ってきても主観にならない。「間違ってるかもしれないけど、俺はこう思うんだ」、雑誌にはそういう「言い切る勇気」があって、それが読者のクリエイティブを呼び起こす。
髙橋 それが続くと雑誌に人格が伴ってきますね。
糸井 そうそう。この人の言ってること聞きたくなるなぁって思えたら信用になるし、好きになると思うんですよね。
髙橋 自分と意見は違うかもしれないけど、この人の言うことは聞いておくかって。
糸井 そうなれば貴重ですよね。みんながどう思うかをみんなで確認しあっているようなものに比べたら。
髙橋 『ほぼ日』は、すでに糸井さんという人格とリンクしているわけですが、それをどう永続的に続けていくんですか。
糸井 もう、僕のご関心はそこですよ(笑)。僕が『ほぼ日』のすべてじゃないのは確かですけど、人格的な代表になっているわけですから、今後そこが同じであり続けるはずがない。いい違いを僕がいるうちに生み出して、それに追い出されるのが理想ですよね。
僕らは「成功してない」っていうのがおもしろいところで、僕自身も『ほぼ日』もなんにも成功してないんですよ。自由でいられる権利を得ただけなんです。成功したっていうのは力の使い道を考えなくちゃいけないことを言うんです、たぶんね。そんな力は持ってないんです。
ただ、自由でいられるまでにはなった。だから、成功するみたいなことは、僕のあとの代の人たちがやることだと思うんです。「力がないとお役に立てないでしょ」っていうのは自分には言えないけどほかのスタッフにはぜひ伝えたいことで、次の代の人には「ちゃんとお役に立てよ」って言いたいですね。僕の個性であるうちは、きっとそこには届かないで終わるかな。
この前『考える人』と『つるとはな』の編集長と雑誌の可能性について話す機会があったんです。商品としては、雑誌の形をした雑誌のことを雑誌って言っているけど、本当は作るプロセスひっくるめて雑誌なんだよねという結論になりました。それは作家に連載を頼もうか検討している時間だとか、前工程なんか全部含めてのパフォーマンスだよねと。ヒントはそこにある気がするんですよね。つまり一座の動き、なんですよ。
髙橋 すごくよくわかります。『週刊東洋経済』も前工程はものすごく時間かけてます。たとえば前回の『ほぼ日』の記事のタイトルの「ほぼ」のところ。どれくらい本物に似せるべきなのか、いやそもそも似せるべきなのかとか、ものすごく議論して。あと、これをお話すると驚かれるんですけど、東洋経済には記者が約100人いて、記事の内製化比率が高いんです。さらに、私のすぐ近くに社内デザイナーさんが何人もいる。席にいると、いつも何かのデザインをチェックしている感じです。
糸井 激しくコストがかかってる感じしますね(笑)。人生分×人数ですから。でもそのコストは、お客さんにいいものをお渡しできるためだと信じたいですよね。
髙橋 はい。ちなみにさっきのタイトルに関連して言うと、『週刊東洋経済』のタイトル文字、ものすごく大きいんですよ。これだけはネットに勝ってるぞっていばっています(笑)。
糸井 大きいね~(笑)。スポーツ紙よりでかいね。
髙橋 字って読むだけでなく、眺めて感じてもらうところがあると思うんです。
糸井 表意文字だから。文字のことを文字だと思っているとそれはできなくて、漢字の持っている抽象性、表意性を出すというのは『週刊東洋経済』の特徴なんじゃないのかな。僕もコピーライター時代はものすごくこだわりました。
さっき話に出た『BRUTUS』も、読まなくても感じるページってあったじゃないですか。ともすると読まれることを拒否するかのように小さい文字なんかもあって(笑)。ああいうのってデザイナーとの共犯なんだけど、読みたいやつだけ読めばいいくらいの思い切りがあった。ああいう雑誌が好きだったという話、なんとなく納得しますね。

髙橋 最後に糸井さんの東洋経済観を教えてください。
糸井 去年、取材してもらった記事が出た後、周りの人に驚くほど「読んだ」って言われました。地方の人にまで言われましたから。それは、いつの間にかWOWOW見てる人ってこんなにいるんだ、って感覚と似ていましたね。僕はWOWOWが好きだから結構見てるんだけど、WOWOWって知らない人からするとなかったことになってる。ネットって実は結構狭いところの人を相手にしている部分があって、東洋経済に出たことで、僕らが相手にしなければいけない人たちの多さとか広さを思い知らされました。
髙橋 糸井さんが思い出さなくても済むようにこれからもっと頑張ります。今日はどうもありがとうございました。
糸井 こちらこそありがとうございました。また来てくださいね。
 編集後記
編集後記
これは、分単位で更新されるインターネットメディアへの、私たちなりの対抗策。糸井さんは「追い立てられるように情報に接するのは無駄」とおっしゃいましたが、週単位である週刊誌はもう少しどっしり腰の据わった情報をお届けしたいなと思います。
1994年に東洋経済新報社に入社し、会社・業界担当記者として自動車、製薬、空運・陸運、ホテル、百貨店などを担当。『週刊東洋経済』編集部では「人」を中心とした記事づくりをベースに、幅広いテーマで特集を制作。2014年4月より女性として初めての編集長に就任。早稲田大学政治経済学部卒