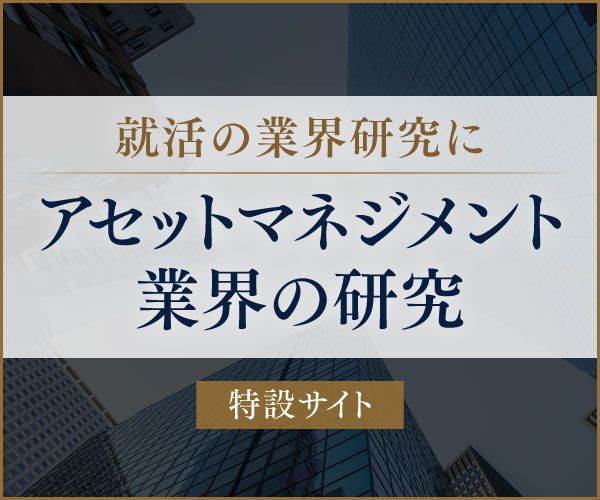運用会社トップ座談会 資産運用の浸透を実感 次の10年、国民を豊かにする「新たな次元」に
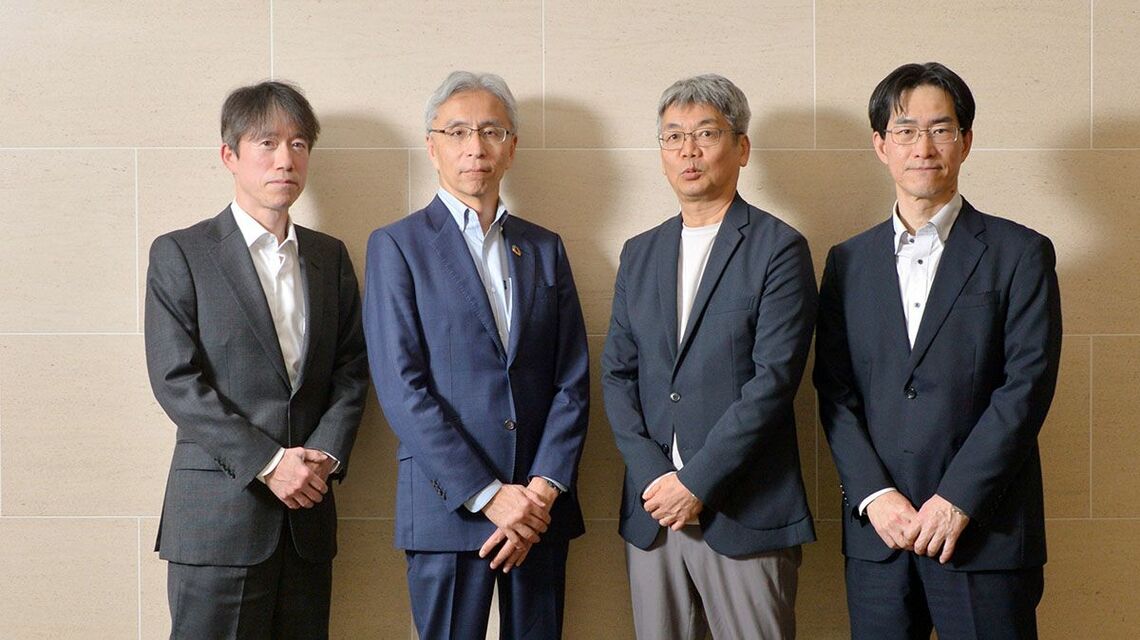
不確実性と資源の最適分配、経営と運用の共通点
杉原 規之氏 アセットマネジメントOne 取締役社長
菱田 賀夫氏 三井住友トラスト・アセットマネジメント 代表取締役社長
横川 直氏 三菱UFJアセットマネジメント取締役社長
西山 明宏氏 りそなアセットマネジメント 代表取締役社長
――皆さん4人のうち3人はファンドマネージャーの経験があります。この経験は運用会社の経営に生きていますか。
菱田 20代、30代のときはファンドマネージャーをやっていました。その経験はすごく生きています。不確実でダイナミックに動くマーケットと向き合うことや、つねに最適なポートフォリオを考えて資源を配分するなど、経営と運用は共通する点が多く、当時の経験が役立っているのは確かです。
ただし、20代、30代のときにマネジメントに関心があったかというと、まったくありませんでした(笑)。生涯、ファンドマネージャーでいたかったです。ファンドマネージャーの経験は生きるのですが、運用部門の中にマネジメントに関心のある人材は多くないので、そこが経営上の課題かなと思います。

菱田 賀夫(ひしだ・よしお)氏
1986年に住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)入社。内外株式ファンドマネージャー、クオンツリサーチヘッド等を経て、同社受託ビジネス全体の経営に当たる。2018年10月より現職。CFA(米国)
西山 アセットマネジメント業界、その中でも私たちのような運用会社がお客さまに提供する最大の価値は長期的なリターンです。その根幹となる運用部門でキャリアを積んだことは、非常に大きかったと思います。
各社とも同じだと思いますが、運用業務を長くやってきた人材が経営を引き継いでいくことで、市場での取引や運用商品に対する考え方など運用のカルチャーを会社経営で長期的に生かせるようになります。
とくに運用者としての視線やこだわりを示すことができるのは運用会社を経営するうえで、メリットだと感じます。
横川 私はキャリアの前半20年をファンドマネージャーとして過ごし、そこから経営企画部や人事部などの管理・企画部門に転じました。運用の仕事に手応えを感じていましたが、ある段階までいくともっと優秀な人材が出てくるわけです。それで自らキャリアチェンジし、会社の経営に携わる部門に移りました。
ファンドマネージャーの経験が役に立ったなと思うことは、通訳のようなスキルを高められたことです。自分の考えや取り組んでいることをお客さまにわかりやすく伝えないと、このビジネスは成り立ちません。「パフォーマンスがよければそれでよいでしょう」ではないのです。
経営も一緒でトップの考えをどう伝えどう実現していくかが重要で、この感覚は役立ったと思います。当時はそれが経営に役立つとは思っていませんでしたが。

横川 直(よこかわ・すなお)氏
1986年に三菱信託銀行(現・三菱UFJ 信託銀行)入社以降、ファンドマネージャーなどアセットマネジメントを中心とする受託財産ビジネスに従事。2017 年に受託財産部門長 MUFG 受託財産事業本部長、21年4月より現職
――杉原さんはファンドを管理する立場でキャリアを積まれました。
杉原 私は30代まで主に有価証券の保管や管理などのカストディアン業務や、ファンドの資産管理の仕事をしていました。そこでは運用会社がお客さまです。運用会社から新しい商品のアイデアや新しいファンドの立ち上げの話を聞き、これをどうマネジメントするかという役割です。
日々、怒られながら仕事をしていました(笑)。でも、資産管理の立場から運用会社とつながっていて、運用の世界を垣間見てきたのが私のキャリアの前半です。
40代になってから運用会社の側に入りました。ただし、そのときも企画的なポジションでした。運用会社のビジネスをどうやって大きくしていくかといった仕事です。結果的に運用会社を別の立場から見てきたことはすごく役立っています。
運用会社には運用に対する自負や思いがあります。一方、それがお客さまに伝わっているのか、支持されているのかというのは大事な視点です。別の立場にいたことでこの点を客観的に見られるようになったと思います。
新人研修でFDの洗礼、35年経っても忘れない体験
――信託銀行から運用会社に移られて違和感はありましたか。逆に運用会社だからできたというものがあれば教えてください。
西山 新卒で年金資産の運用部門に配属されて以降、お客さまの財産を管理・運用する信託業務にずっと携わってきて、その部門を切り出す形で今の会社ができたので、ほとんど違和感を覚えませんでした。どちらもフィデューシャリー・デューティー(FD・受託者責任:顧客の利益を第一に考える姿勢)を思考の中心に置いていますから。
このビジネスならではの経験では、責任投資を通じてSDGsの分野にいち早く取り組めたことです。1990年代にはこの考え方が国内の運用会社に広がりました。SDGsの考えを運用会社で具体化していき、しかも長期にわたって取り組んでいます。こうしたことはこの業界ならではだと思います。
この場を借りて社会貢献に関心のある若い方にお伝えしたいのですが、この業界は仕事を通じて社会に貢献でき、そのことを実感する機会が多いところです。

西山 明宏(にしやま・あきひろ)氏
1990年に大和銀行(現・りそな銀行)入社。一貫して信託財産運用部門にて資産運用業務に従事。主に企画部門、プロダクト開発、インデックス運用を担当。2015年にりそなアセットマネジメント代表取締役社長、18年にりそな銀行 執行役員 信託財産運用部門担当 兼 アセットマネジメント部担当。23年4月より現職
横川 フィデューシャリー・デューティーを前提に働く感覚は本当に共通で、その意味で違和感はほとんどありません。海外の運用会社の方と話していてもフィデューシャリー・デューティーという言葉は私たちの世界で共通言語になっています。
ただ、信託銀行では企業年金や公的年金とのお付き合いが多かったのに対し、運用会社ではほぼ個人投資家向けで、ターゲット層が違うという点では慣れが必要でした。
菱田 アセットマネジメントの仕事は信託銀行とすごく近いので、私の印象も一緒です。1つはフィデューシャリー・デューティーの考え方で、もう1つは長期にわたって投資するとか長期にわたってお客さまとリレーションを持つ点です。どちらの業界も短期のビジネスはほとんどありません。
他方、運用会社は銀行に比べて組織がフラットです。フラットな組織にも課題はありますが、フラットだといろいろなところからいろいろなアイデアが出て、それが通りやすいことがメリットです。想像力やアイデアを生み出すためにも、運用会社に限らずプロフェッショナルな組織はフラットになっていく気がします。
杉原 お話のあった長期という言葉は私もキーワードだと感じます。年金ビジネスは現役世代が今払っている掛け金をリタイア後に受け取るわけで、非常に時間の長いビジネスです。信託銀行の業務と運用会社の業務は長期の時間軸でお客さまの伴走役を務める点が共通で、両者は極めて近い存在にあるといえます。

杉原 規之(すぎはら・のりゆき)氏
1992年に日本長期信用銀行(現・SBI新生銀行)入社。99年には興銀信託銀行(現・みずほ信託銀行)に入社し、みずほグループにおける資産運用および資産管理ビジネスの拡大に取り組む。2021年にみずほ信託銀行アセットマネジメント部門長。23年4月より現職
西山 新人時代のことになりますが、研修で外国株式のファンドマネージャーの講師に、いきなり「フィデューシャリー・デューティーという言葉の意味がわかりますか」と聞かれました。もちろん、誰もわかりません。それでも、講師の方はフィデューシャリー・デューティーについてすごい熱意で話されました。
ほかの講義のことは正直あまり覚えていませんが、そのコマのその一瞬だけはすごく覚えています。あれから35年が経ちましたが、フィデューシャリー・デューティーを徹底しようという考えの根底には、あの時の体験があると思います。
横川 ほかのいわゆる銀行業務では銀行の利益とお客さまの利益が対立する局面がどうしてもあるわけです。アセットマネジメントの業務にはそれがないというか、お客さまがプラスにならないと私たちもプラスにならないビジネスです。
信託銀行と運用会社はそこが一緒で、キャリアの最初からそうした仕事をしているので、違和感を持たないのだと思います。
菱田 以前は世界に「トラスト(信託)」と名の付く金融機関がいくつもありましたが、今ではほとんど日本だけになりました。ですから日本の信託銀行はユニークな存在に見えます。
しかし、欧州のプライベートバンクは信託銀行と同じで、資産運用と資産管理、銀行業と不動産などさまざまな業務を抱えながらお客さまと一緒に成長しようとしています。それを考えると、信託銀行や私たちのビジネスモデルは自然なもので、お客さまにサービスを提供する会社の自然な形だと感じます。
NISAでレジームチェンジ、有望企業に投資家の目を
――社長就任後に手応えのあった仕事は何ですか。逆に課題に感じる点はありますか。
西山 これは皆さんも共通だと思いますが、NISAの導入で「長期・積み立て・分散」という私たちがずっと主張してきたスタイルでの投資が浸透し、そうした形で資産形成を始められるお客さまが圧倒的に増え、本当にうれしい限りです。
もう1つは若い世代向けに金融教育が広がっていることは、すごくよいことだと思います。資産運用に興味を持つ高校生も増えていて、講義が終わった後も講師を取り囲んで質問攻めにしたりします。こうした反響に手応えを感じます。
横川 自分の実績ではありませんが、新NISAの口座が2024年末に約2560万件まで増えました。2560万件といえば、成人の4人に1人の割合です。資産残高でいえば、投資信託の世界では長年、「60兆円の壁」がいわれてきました。
主なお客さまは相場に興味のある方で、値上がりすると売り、値下がりすると買うということを繰り返すため、資産残高が60兆円を超えることができませんでした。それが今や100兆円を超え、約140兆円です。日本に世の中の意識が変わるレジームチェンジが起きたのだと感じました。
もう1つ、自分で商品を選ぶ個人投資家の方が増えた点も大きな変化です。自分が社長に就任してからの4年間で本当に変わったと思います。
これから取り組みたいのは、インデックス投信で運用を始める方が多い中、運用の選択肢はそれだけでないと伝えることです。有望企業を発掘するアクティブ投信にも目を向けてもらえるように、投資家の方をサポートしていきたいです。業界全体で切磋琢磨していければと思っています。

杉原 私たちは今、運用会社が発信する金融経済教育に力を入れています。23年には、個人の方への資産運用や金融についての啓発・普及活動を目的とする研究所を社内に立ち上げました。
学生向けに講義などをしますが、大学ではまず投資の社会的意義についてお話しします。運用会社はお預かりしている資産を投資してリターンを上げることに加え、責任ある機関投資家としての役割を果たしていることも伝えます。
後者では投資先の企業の価値を見極め、そこに資金を投じることで対象企業の価値が高まり、それがリターンとして返ってくる。この好循環を運用会社は生み出していると説明します。単体の企業だけでなく、社会全体の課題解決にもつながる。そうした話に対する学生の感度はすごく高いです。
講義後のアンケートに「そういう役割が運用会社にあるとは知らなかった」「すごくやりがいのある仕事と感じた」などびっしり書いてあります。将来を担う世代の感性は、やはりそうした面に向くのだなと感じました。私たちがこうした点の情報発信を続けることで、若い方たちをこの世界に引きつけていきたいです。
菱田 私は、この業界が抱える課題についてお話ししたいと思います。それは世界の中で日本の運用会社の認知度が低いことです。この国の経済力から見て残念と言わざるをえません。
認知度が高ければ、もっとできることがあります。それは日本に投資する海外のお客さまを増やすことです。これは私たちの使命の1つだと思います。若い方がこの世界を目指す際の夢になるはずです。
具体例を挙げますと、私が中東のお客さまを訪ねるようになって10年ほど経ちます。中東のお客さまに会おうとすると、いわゆる事情通の方から「やるだけ無駄だ」と言われました。彼らをめぐり世界中の運用会社が競争を繰り広げ、報酬は低く、要求水準は極めて高い。しかも、パフォーマンスが悪ければすぐに契約を切られてしまうと。
しかし、よく考えてみると、今挙げた状況は日本の運用会社を取り巻く環境と同じではないかと気づきました。私たちが同じメンバーで5年、10年と訪問を続けると、次第に親しくなるし、いろいろな情報を交換できるようになりました。日本の運用会社が世界でできることはたくさんあります。
次の10年で運用を生活の中へ、今が重要な転換点
――NISAが誕生して10年が経過しました。次の10年で、アセットマネジメント業界や運用会社はどう変わるとみていますか。
西山 1つはNISAの効果もあり、国民に資産運用が浸透し、当たり前になっていくとみています。もう1つは企業や社会を変えていく活動に対する運用会社の貢献は大きくなり、そうした面の見える化というか情報発信がますます求められると思います。
責任投資などは長期的な視点で取り組むものなので、その成果を実感してもらえるような10年にしたいなと思います。
菱田 同感です。「さぁ、銀行に預金をするぞ!」と意気込む人はいませんよね(笑)。気がついたら預金があるのと同様、資産運用をしているような形が望ましいと思います。これからインフレの世の中になると、国民の皆さんが普通に考える選択肢になるでしょう。10年後に資産運用が生活の中で当たり前になっているとよいですし、そうしなければと思います。
杉原 米国で401k(確定拠出年金制度)が導入されたのが1980年代前半で、そこを起点として米国の家計金融資産は90年代前半に20兆ドルとなりました。これは現在の日本の家計金融資産とほぼ同じ規模です。それが2024年3月時点で約120兆ドルと30年間で6倍ぐらいになっています。
私たちは今、米国の90年代と同じような転換点にあると考えれば、これから30年で日本の家計金融資産も5倍、6倍になっておかしくないと思います。
そうなれば少子高齢化による社会保障の課題解決や税収増にもつながり、国家にとってもプラスです。資産運用はこれからの10年、国家戦略上も重要な局面に入ると考えています。
横川 NISAも銀行口座と同じように18歳や20歳になったら普通に持っている感覚にならなければと思います。投資先企業への貢献も私たちの使命です。
それは上場企業だけでなく、インフラ資産や非上場企業への投資などが増える中、そうした分野での貢献は直接投資の担い手として私たちが国民経済の中に根付かせないといけませんし、できると思います。
日本の運用会社が世界で存在感を発揮することも10年後に達成しないといけません。ただし、それは運用残高だけではなく、運用のクオリティーも含めて見るべきです。
社会の課題解決に企業の発展に、皆さんの力が必要
――最後にアセットマネジメント業界を発展させるため、若手社員やこの業界を目指す学生の方に期待することをお願いします。
菱田 これまでの皆さんのお話にあったように、運用会社は投資先企業や国などと一緒に成長できるビジネスです。そして社会の課題を解決できる仕事です。こういう仕事はなかなかありません。そういう世界にぜひ加わっていただきたいと思います。
横川 これから伸びていく産業なので、やれることがどんどん広がります。投資対象も広がりますし、活用するテクノロジーや活動する地域や領域も広がる可能性があります。
こう語っていますが、次の10年は今思っているのとはまったく違う未来が待っているかもしれません。好奇心を持って挑戦したいという方は大歓迎です。
西山 皆さんが言われたように、将来世代に対して豊かさや幸せを提供できる大きな力を持っている産業です。多くの若い方にこの業界に参加していただき、将来世代の幸せに携わっていただけたら、今この業界で働く者の一人としてこれほど心強いことはありません。
杉原 最後になりあまり付け加えることもありませんが、あえて言えばこれからこの業界に入ってくる若い方にとって、30年後の業界の発展とか個人の成長とかが見通せる希有な産業だということです。しかも社会の課題を解決する大義がある仕事です。
この国をよくする大きなテーマにアセットマネジメント業界は深く関わっています。社会の課題解決のため、投資先企業の発展のため、若い方の力が必要です。皆さんの力で業界の成長を担ってほしいと思います。