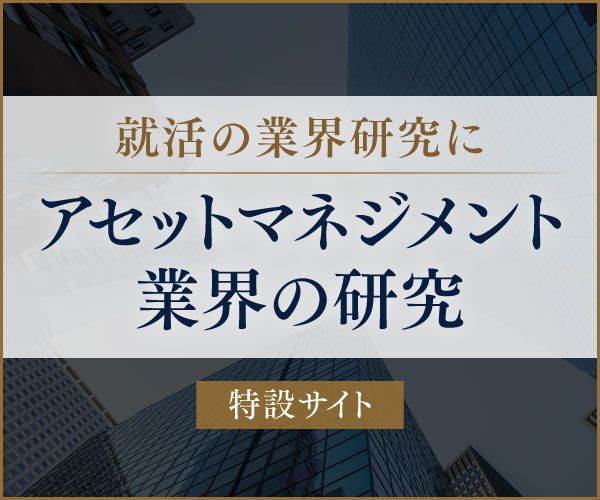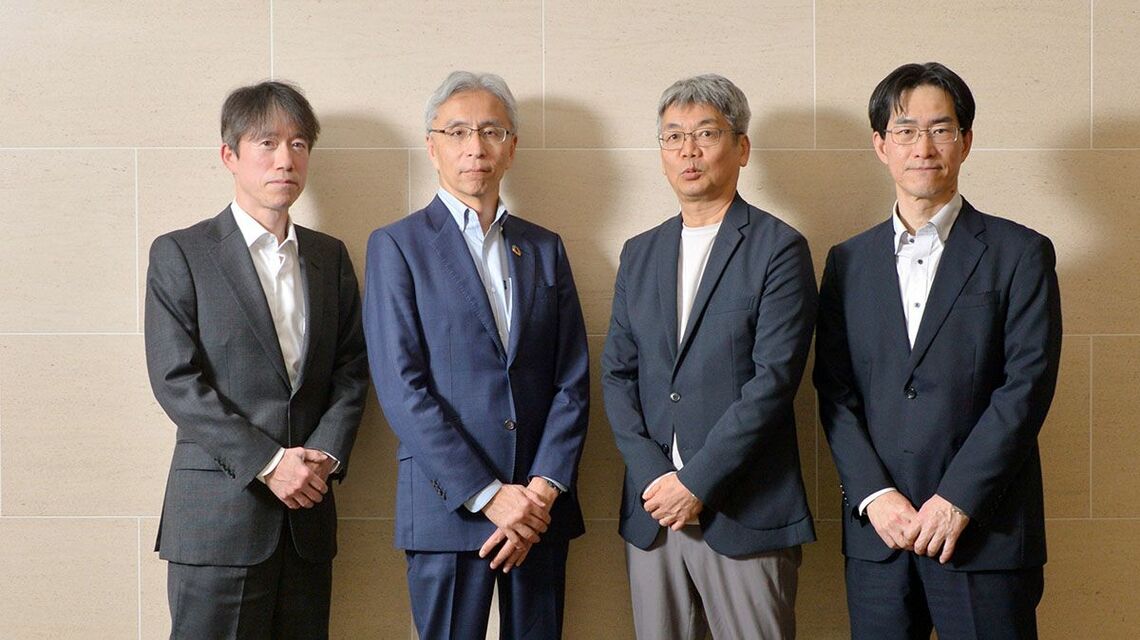「貯蓄から投資へ」動く!運用会社への期待大きく 政治からの提言続けるーー岸田前首相が語る

資産運用立国実現プラン、経済の好循環を金融で支える
――首相在任中に資産所得倍増プラン、資産運用立国実現プランと矢継ぎ早に国民の資産形成を促進する政策を打ち出されました。それは、どのような問題意識からでしょうか。
私が政権を担うことになった2021年の状況を思い返すと、30年続いたデフレ経済から脱して成長型の経済ステージに引き上げるという経済の再生が最大の政策課題でした。そのため、新しい資本主義という経済モデルを掲げ、賃上げを起点とした経済の好循環を再生させることに取り組みました。
まずは、持続的・構造的な賃上げ、三位一体の労働市場改革※1、企業の稼ぐ力を復活させるためにDXやGX※2、AIや半導体などへの官民による戦略的な投資を進めました。さらにはイノベーションの牽引役となるスタートアップ企業を支援する5カ年計画などにも取り組みました。こうしたことで経済の成長と分配の好循環を取り戻そうと考えました。
この好循環を金融の面から支える重要な施策が、資産運用立国実現プランです。わが国の家計金融資産約2200兆円のうち、およそ半分が現金・預貯金で、この割合は私が社会人になった40年以上前から変わっていません。当時から「貯蓄から投資へ」と叫ばれていましたが、これがまったく動いていませんでした。
そのため、これを動かさなければと考えました。家計の金融資産を投資に振り向け、投資された企業はその資金を活用して企業価値を高める。その恩恵を家計に還元することで、国民は次の投資や消費につなげていける。この好循環を生み出そうというのが、資産運用立国実現プランの基本的な考え方です。

1957年東京都渋谷区生まれ。早稲田大学法学部卒業後、日本長期信用銀行(当時)入社。93年に広島1区から自由民主党公認で出馬し、衆議院議員に初当選。現在11期目。2021年から約3年にわたり、内閣総理大臣を務める
新NISAは資産運用立国の象徴、成人の4人に1人が利用
プランの実現に向けて、インベストメントチェーン全体を動かす必要があります。家計や企業、資産運用業、金融商品の販売会社、企業年金などのアセットオーナーといったインベストメントチェーンの各主体に効果的な政策を用意し、さらにこれらの政策は、最終的に家計の金融資産を動かすという同じ方向を向いてもらわないといけません。そうした意図に基づいて、一連の政策を用意しました。
結果としては成果を上げることができたと自負しています。企業収益は過去最高を更新し、株価も2024年に、バブル時に記録された最高値を塗り替えました。また、25年の春闘はほとんど満額かそれ以上の回答でした。
そして象徴的なのが新NISAです。24年1月にスタートし、すでに18歳以上の国民の4人に1人が口座を持ち、投資額も口座数も一気に増えています。間違いなく、「貯蓄から投資へ」は動き始めたと感じています。
改革継続へ議連を結成、情報発信や提言を続ける
――首相退任後に、資産運用立国議員連盟(以下、議連)※3を立ち上げました。議連を結成した狙いや、目指している国づくりはどのようなものですか。
資産運用立国実現プランは大きな成果を上げたと思っています。とくに若い世代には投資が身近なものになり、30代では3人に1人が新NISAの口座を持っています。ただし、この取り組みはわが国の資金の流れを大きく変えることを意図しているので、これからも改革を続けることが求められます。
この改革を継続していくためには、政府だけではなく、政治サイドとしても議連を設立してメッセージの発信を続けていくこと、さらに法改正や税制改正、予算の議論などのタイミングで具体的な提言をしていくことが必要であると考えました。
そのために仲間を集めて、議連を立ち上げました。これまでの取り組みを継続するために、この議連はたいへん重要な存在だと思います。
国民本位の政策を、「資産運用立国」と名付けた思い
――その議連が名乗っている「資産運用立国」というネーミングは、少し耳慣れない響きです。
いろいろな言い方ができると思いますが、まず「投資」では企業の活動がイメージされやすいのではないでしょうか。そうではなく、国民一人ひとりの視点に立ち、国民が自らの資産を運用するという理念が伝わる言葉が大事だと考えました。企業側ではなく、国民の側に立ちたいという思いを「資産運用」に込めました。
次に「立国」は、ある方針や計画に基づいて国を発展させる意味で使っています。つまり国民本位の資産運用で長期的・計画的に国を栄えさせるというのがこのネーミングの意図です。
――議連で継続的に情報発信や提言を続けるとのお考えですが、実際にどのような活動をなさっていますか。
2024年11月に議連を立ち上げ、年末に最初の提言を出しました。それは予算や税制改正に反映されています。また、それ以降も議連では2週間に1回は必ず集まって議論をしています。
夏には政府の「骨太の方針」が公表されるなど、政治的な節目がいろいろとあります。それらの節目に向けて、議連が提言すべきことについて話し合い、その内容を今年4月に提言※4としてまとめました。
海外投資の制限はナンセンス、国内の魅力向上が王道

――資産運用立国実現プランで家計の金融資産が動き始めたことは同感です。動き始めた資金の行く先について、政治家としてどのような考えをお持ちですか。
動き出した資金の行く先でよく話題にされるのは、新NISAの口座に入った資金の投資先が海外資産に偏りすぎではないかというものです。「もっと国内に投資されるべきでは。もっと国内の経済成長に振り向けられるべきでは」と。極端な例には「税制優遇のある新NISAでは、海外への投資を制限すべきだ」といった声まであります。
私の考え方は少し違います。新NISAでは「長期・積み立て・分散」に基づいた安定的な資産形成を目指すべきです。海外への投資は否定されるべきものではありません。国民の選択肢として大事なものです。
さらにわが国の資本市場は、双方向のプラットフォームであるべきです。国内の投資家が国内に加えて海外にも投資する。同時に世界からも投資を呼び込む。このように資本市場は双方向でなければいけません。
したがって海外投資の選択肢は否定しませんが、国内への投資、国内の成長のための資金も重要な存在です。資金を投じてもらうためには、国内の市場や企業が魅力的でないといけません。これが政策の王道だと思います。海外に負けないだけの魅力が国内にあれば、国民の皆さんは国内に資金を投じることでしょう。
その国内の魅力を高めるために、例えばコーポレートガバナンス改革などを通じて企業の魅力、稼ぐ力を高めていこうとしています。また、官民連携での戦略的な投資プロジェクトにも取り組んでいます。魅力的な投資先やプロジェクトを用意することで、国内に投資しようという機運を高めたいですね。
運用会社に対するお願いを言うなら、稼ぐ力を持った企業をしっかり見極め、国民に魅力的な商品を作っていただきたいです。さらに言えば、国民の一人ひとりには人生のステージに合わせてさまざまなリスクを勘案し、自分で投資先を選択できるようになっていただきたい。こうした社会をつくっていきたいと思っています。
こういった考えもあり2024年4月にJ-FLEC(金融経済教育推進機構) を立ち上げました。国民が金融リテラシーを持つ社会は、投資先として国内を魅力的にする重要なポイントになります。国内の金融リテラシーに鍛えられたわが国の企業やプロジェクトは、きっと魅力的なものになるでしょう。
――官民連携の戦略的な投資プロジェクトですが、具体的にどのようなものがありますか。
いろいろなプロジェクトがありますが、私の政権でいちばんの目玉になったのは2050年カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギー等への戦略的な取り組み、つまりGX投資です。国がGX経済移行債※5で20兆円規模の資金を用意し、それを呼び水として10年間で官民合わせて150兆円超を投資して、脱炭素成長型経済に移行する取り組みを始めました。
脱炭素の関連で言えば、私はアジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)の議員連盟の最高顧問を務めています。これは、アジアの脱炭素への取り組みを、わが国の技術と資金で支援するプロジェクトを推進する集まりです。資金需要は総額で約400兆円といわれています。
脱炭素へのアジアの関心は高く、プロジェクトの事務局はインドネシアの希望で同国に置くことになりました。国内という範囲からは離れるかもしれませんが、このプロジェクトには経団連の関心も高く、アジアを大きく巻き込んだ形でわが国を核とした投資プロジェクトを進めています。
運用会社の皆さん、プロとしての誇りを持って仕事を

――資産運用立国実現プランが、たいへんに意義深い政策であることがわかりました。これから資産運用立国の推進を担う運用会社の若い社員や、資産運用業を目指す学生に、メッセージをお願いします。
まず、運用会社でいま働いている若い皆さんに申し上げたいことは、わが国のインベストメントチェーンの中で運用会社はたいへん重要な役割を担っているということです。今後もますます成長が期待されると思います。
政府に対しても、資産運用業が国内の金融業界で「銀行・証券・保険」に並ぶ第4の柱となるべく、資産運用業の発展のための政策を遂行していくことを確認しています。
例えば資産運用立国議連が2024年末、金融庁に銀行第一課と第二課、証券課、保険課に肩を並べる資産運用課をつくるべきだと提言しました。その結果、今夏に資産運用課が新設されることになりました。この業界を発展させる大きな成果だと思っています。
そしてこの提言の中で、国民の資産運用を推進するために政府に新たな会議体をつくることを申し上げたところ、今年3月には石破茂首相によって「資産運用立国推進分科会」が設置されました。これは省庁横断的に資産運用立国を推進するもので、これも大きな成果といえるでしょう。
このように、資産運用業は、わが国のインベストメントチェーンの中で大きな役割を果たしていく存在です。この分野で働く皆さんにはぜひ頑張っていただきたいと願っています。
運用会社にはファンドマネージャーやアナリストだけでなく、商品開発や資料作成、提案などの業務においても「これぞプロ」と呼ぶべき人材がそろっています。そうしたプロフェッショナル集団の中で働いていることに、誇りを持っていただきたいです。
学生の皆さん、プロフェッショナルとなり人生を切り開いてほしい
このページを目にする学生の皆さんは、金融業界や資産運用業に関心のある方だと思います。そうした学生の方にお伝えしたいことは、国の経済を活性化し企業を成長させ、そして国民を豊かにするために、資産運用業はたいへん重要な仕事だということです。
その職場には先に申し上げたようにそれぞれの分野のプロフェッショナルがおり、そこでは優秀な人材が求められます。志のある学生の皆さんにこの仲間に加わっていただき、プロフェッショナルの一人として自分の人生を切り開いていただきたい。こうしたことにぜひチャレンジしてください。
※2 GX:グリーントランスフォーメーション。化石燃料をクリーンエネルギーに転換して世界を脱炭素社会に転換しようとする取り組み
※3 資産運用立国議員連盟:岸田前首相が退任後に資産運用立国実現プランを推進するため、2024年11月に結成したもので、金融や経済分野に精通した国会議員を中心に参加
※4 同議連は2025年4月16日に、NISAでつみたて投資枠の年齢制限の撤廃や高齢者向けに対象商品の拡大などを盛り込んだ提言をまとめ、同23日に石破首相に手渡した
※5 GX経済移行債:脱炭素成長型経済構造移行債。脱炭素社会に移行するためGX推進法に基づき、国が20兆円規模で発行する新型の国債