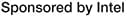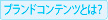Access Ranking
「インテル、入ってる」。もはやそれはハード面を超えて、ついに起業家マインドの中にも進出しようとしている。現在、インテルはスタートアップ企業との連携に力を入れはじめた。IT業界の先駆者とも言うべきインテルが大企業だけでなく、スタートアップ企業と連携を図る狙いとは何か。前後編の2回に分けて紹介する。
前編ではスタートアップ企業との連携をサポートしているソフトウェア・サービス戦略本部アライアンス・マネージャーの柳原明人氏、スタートアップ企業の代表としてしくみデザインの中村俊介社長に話を聞いた。

アライアンス・マネージャー
柳原明人
スタートアップ企業には
大企業にはないアイデアとスピードがある
―――スタートアップ企業をサポートする狙いとは何でしょうか。
柳原 IT業界では今、過去にないくらい変革のスピードが速くなっています。これまでにないイノベーションがスマホやタブレット、アプリで起きているのです。
インテルはこれまで、大手のハードウェアメーカーやソフトウェア会社と協業してきましたが、それだけでは現在の市場変革スピードに追い付いていけません。
そこで従来の協業企業に加えて、新たにスタートアップ企業とも連携することによってイノベーションのスピードを加速できないかと考えたのです。スタートアップ企業には、素晴らしいアイデアとスピードがあります。そのアイデアとスピード感が、市場を新しく創造するうえで不可欠になってくると思います。
―――どのような企業を協業の相手として想定していますか。
柳原 現状、主にはウェブ・IT関連企業になります。しかし、今後はウェアラブルなどの分野で異業種の企業との協業の可能性もあると思います。基本はインテルのチップが搭載されたデバイスに付加価値をつけたり、ソリューションとしてエンドユーザーに使い方を届けてくれる会社であればいいのです。
今はパソコン一台、
一人で起業できる時代
―――協業する相手方企業にとってインテルと連携する魅力はどこにありますか。
柳原 彼らが一番求めているのは世間での認知です。いかに良いコンテンツやサービスであっても、世間に認知されなければ意味がありません。スタートアップ企業のサービスを、インテルが開催する国内を含む世界レベルの大規模なイベントや展示会で紹介するなど、マーケティング協力が可能です。また、技術的な支援も積極的に行っています。日本からうまれるエッジの効いたサービスやアプリケーションを、世界に広げていく手助けができればと思います。
―――現在の日本のスタートアップ企業の状況をどうとらえていますか。
柳原 非常に盛り上がってきていると思います。一番大きいのは、起業の垣根が下がったことでしょう。今はパソコン一台あれば、一人でも起業できる時代です。テクノロジーとクラウドの進化により、誰もが起業しやすい環境にあると思います。誰もがITの力を使って、自分たちのやりたいサービスをネット上で実現できるわけです。
新しい利用モデルが生まれるなら
協業する企業の規模は問わない
―――スタートアップ企業とおつきあいすることでインテルに変化はありましたか。
柳原 スタートアップ企業は、ユーザーに近いところでアプリやサービスをつくっているので、市場のニーズにとても敏感です。大企業でも、100%でなくても早く市場に出して反応を見て、製品化のスピードを上げようとしています。スタートアップ企業と連携することで、新たなテクノロジーをプロダクト、あるいはデモとして早く市場に出し、市場の反応を吸い上げ、改善することが大企業でも必要になっているのです。
―――スタートアップ企業から学ぶことも多いといえそうですね。
柳原 われわれも若いスタートアップの経営者の柔軟な考え方や実行の速さを学び、変化する市場のニーズに応えるよう技術を進化させ、市場にイノベーションを起こしたいと思っています。イベントのスポンサーや交流会などを行いながら、彼らが我々から何を必要としているかヒアリングしています。日本発のスタートアップ企業のビジネスアイデアが世界に基盤を広げる手助けができればと考えています。

中村俊介
1975年生まれ。名古屋大学工学部建築学科卒業後、九州芸術工科大学大学院(現・九州大学大学院芸術工学府・同研究院)博士課程修了。2004年九州工業大学専任講師に就任。05年しくみデザインを創業。09年より代表取締役。
しくみデザイン――
国立大学講師がつくった博多発のベンチャー企業
―――主力事業であるインタラクティブ・デジタルサイネージとはどのようなものなのでしょうか。
中村 一言でいえば、見ている人が参加できる広告です。従来の広告は画面を見るだけでしたが、私たちのつくっている広告は見ている人がインタラクティブにその世界に入り、楽しむことができます。
―――デジタルサイネージが注目されたきっかけは何ですか。
中村 2007~08年頃でしょうか。当時、僕は並行して九州工業大学の講師もしていたのですが、地元に北九州空港ができるので、「何か試してみないか」との依頼が北九州市からありました。そこで参加型ディスプレイを市のPRとしてつくったものが創業後、初の取り組みとなりました。
最も大きな反響があったのが「笑っていいとも!増刊号」に出たことです。そこから大手広告代理店から映画プロモーションの声がかかり、大阪・道頓堀のディスプレイを使って、日本初の参加型広告を大々的に展開することによって、こんな手法があるのかと業界内でも知られるようになりました。
―――なぜ博多で創業しようと思われたのでしょうか。
中村 そもそも大学では建築学科に籍をおき、建築家を目指していました。しかし、建築は自分で考えたものが完成するまでに様々な人が介在する。僕は自分で考えたものを最後まで自分でつくりたいと思ったのです。もっと身近なグラフィックなどのデザインのほうが僕に向いているんじゃないかと考え、九州芸術工科大学大学院(現・九州大学大学院芸術工学府・同研究院)に進学しました。
このとき初めて博多の地に足を踏み入れました。博多の気候や食べ物も良くて、非常に過ごしやすく馴染みましたね。受け入れてもらいやすい面もあって、以来ずっと博多に居座っています(笑)。

会社の残金が5万円という危機
そんなピンチをチャンスに変える方法
―――起業のきっかけは何ですか。
中村 博士課程を修了し、任期付きの専任講師を引き受けたことです。5年の間に将来何をすればいいのか、考えられる猶予期間をもらった格好となりました。実際には1年も経たないうちに現在の会社を立ち上げてしまったのですが。
―――創業資金はどうしましたか。
中村 院生時代につくった作品が、トヨタ九州が主催する学生向けの技術コンペで賞をもらい、トヨタと共同で国際特許を出すという話になりました。それでいただいた300万円を創業資金に充てました。また、福岡県のヤングベンチャー支援事業に採択されたことで年間700万円を2年ほどもらうことになり、それを運転資金に充てました。起業した最初の2年間はかたちになる仕事がなかなかできませんでしたが、会社としては、バイトの給料は助成金で賄い、自分は大学講師の給料で生活していたので、比較的幸運な起業をすることができました。
―――会社としてのピンチはありましたか。
中村 助成金の期間が終わって、細々と食いつないでいるときに、会社の通帳の残金が5万円しかないことが判明しました。もともと僕は財務に興味がなく、当時の社長にすべて任せていたのですが、その人が行方不明になってしまったのです。残された財務資料を見てもよくわからない。
「これはヤバイ」と、そこで初めて会社をきちんとしようと気づきました。会計の専門家から「このままでは会社として無理」と言われたことで、大学時代の友人を口説き落として、体制を根本から立て直すことにしました。そこから会社としてのカタチを少しずつ整備していったのです。
いかに人が気持ち良く
技術を使えるかを追求する
―――インテルと協業することでどのような変化がありましたか。
中村 インテルさんからサジェッションをもらって、パーセプチュアル・コンピューティング(PerC:人間の意図をデバイスにより自然に認識させることを目的とするインテルが推進している概念)を基本とした様々なアイデアを具現化しています。
インテルさんの意見を聞かなければ思いつかなかったものも多くあります。例えば、ジェスチャーで音をコントロールする技術として、これまでPCに標準搭載のウェブカメラを使ったアプリを開発していましたが、インテルのPerCの技術を使うことで、より細かな部分を認識できるようになりました。さらに、インテルさんと協業したことで、自分たちの技術がCEATECでのデモ展示ほか、グローバルな展示会などで紹介され、ビジネスのきっかけが生まれる機会が増えました。一気に世界が拡がったと思います。
12月には、インテル社主催のアプリコンテストPerceptual Computing Challengeで私たちの制作した「KAGURA」が大賞を受賞しました。もちろん、この賞は第三者機関の評価によるものです。こうした評価と認知が私たちスタートアップ企業には大きな励みとなるのです。
―――今後についてはどのように考えていますか。
中村 今の技術をもっと人間の知覚に合ったものにできないかと考えています。僕たちがずっとやっているのは、最新技術を取り入れるというよりは、いかに技術を感じさせないで気持ちよい体験をしてもらえるか、ということです。それは人間と技術のインタラクティブであり、いかに互いが近付けるのかという考えがベースにあります。
例えば今、子供でも気軽に音と絵を組み合わせてコンテンツをつくれるアプリも提供しています。子供たちは感性も豊かでみんなが天才だと言ってもいい。それがなぜ大人になって普通の人になっていくのか。考えてみれば、そうした感性を生かす場が減っていくからだと思うのです。だからこそ、私たちのツールを使って、その感性をどんどん発展させてほしいと思っています。
(撮影:今祥雄)