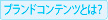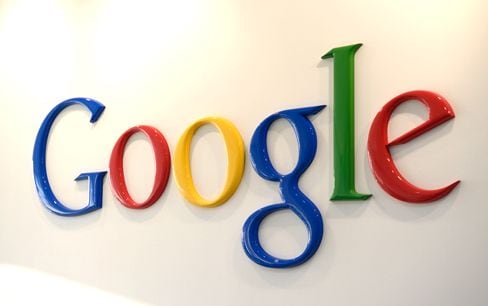Access Ranking
勢いがある企業のチカラの源を探る本コーナー。今回は、持っているだけでもワクワクしてしまうシステム手帳「ほぼ日手帳」のチームに取材しました。 糸井重里氏が1998年に開設した「ほぼ日刊イトイ新聞」から生まれた本手帳 は、「自分たちが欲しいもの」を徹底的に追求し、ビジネス用途が主だったシステム手帳に新たなユーザーを巻き込むことに成功。「最も大切にしているのは “動機”です」と語るのは、手帳チームのリーダー棟廣祐一氏。
“動機”が手帳の成功にどう繋がるのか、また独自のワークスタイルポリシー、昨年受賞した ポーター賞について、サイボウズ式の編集長大槻が棟廣氏、齋藤正輝氏、デザインチームの田口智規氏にお話を伺いました。

ほぼ日手帳チームは少数精鋭
――ほぼ日手帳は、システム手帳に今までにない価値をもたらしたように感じています。アイデアの源泉や、昨年受賞されたポーター賞についてお話を伺いたいと思い取材を依頼致しました。まず、会社の構成を教えていただけますか?
棟廣:ほぼ日刊イトイ新聞が登場した当初は糸井と1名の社員、そして外部の協力スタッフでスタートしたそうです。現在社員は50名ほど。創刊時と比べるとだいぶ会社らしくなってきました。
――50名の内訳は?
棟廣:ほぼ日の編集部、デザインチーム、商品企画チーム、プロモーション、ほぼ日ストア、カスタマーサポート、管 理部門、大きく分けるとそのぐらいです。商品は手帳のほか、ハラマキやタオル、扇子もあり、それぞれ3〜4名ほどのチームを組んで企画、制作。ほぼ日手帳 チームの企画制作メンバーは、ここにいる3名と女性2名の計5名です。企画が固まってきたら、手帳の編集をするもの、生産まわりを担当するものなど、チー ムにどんどんひとが入ってきます。
――チーム内でも担当があるのですか?
棟廣:私は東京糸井重里事務所に入社する以前は文房具や雑貨に携わっていましたが、縁あって入社。現在、ほぼ日手帳チームのリーダーを担当しています。
齋藤:私は棟廣の1年後ぐらいに入社しました。前職では、電機メーカーでプロダクトデザインを担当。糸井事務所に入社してからは、ほぼ日のモノ作りの考え方を学んで、手帳のような“柱”になる商品を作ることをテーマとしています。
田口:私は2007年入社で、デザインチームに所属しほぼ日手帳のデザイン周りを担当。コンテンツのほか、商品、取材時の写真撮影なども行っています。
――手帳の企画から制作のプロセスを教えていただけますか?
棟廣:ほぼ日手帳は毎年9月1日に翌年版をリリースしています。リリースから年末にかけては発売した手帳のプロ モーションを行いながら、翌年版のアイデアを出し合います。年明けからは「4月はじまり」の「ほぼ日手帳 spring」のプロモーションも行いながら、出したアイデアを具体化させ、翌年の手帳制作へ進みます。
齋藤:年2回ある手帳のユーザーを対象にしたアンケートからもアイデアの種を探します。フリー回答の質問にもきっ ちり目を通し、気になる指摘を見かけたらすぐに調べて、商品企画に反映できないか検討します。試行錯誤しながらサンプルを何度か作り仕様を固め、本格的に 工場に依頼をするのが大体5月ぐらいです。
田口:その後は私や編集部の人にも混ざってもらい、Webショップやパッケージ、ディスプレイなどデザインに入り ます。ひとつひとつの商品にフォーカスしたコンテンツを作成し、写真の見せ方も考えながら制作。今回(2012年発売)はWebショップから「ワクワク」 を伝えたいと考え、手帳が織りなす世界観を表現していただきたいとファッション誌で活躍するスタイリストさんに依頼。そのおかげで、一昨年と比べてページ ビュー数が5倍まで増加しました。

ほぼ日手帳は「自分の分身」
――ほぼ日手帳が高い評価を受ける理由が見えてくるようにも感じます。皆さんは何が魅力になっていると考えていますか?
棟廣:自分たちでも「欲しい」と思っていることでしょうか。日々集めた「これが欲しい」、「こうすると面白い」、 それらを集約したのがほぼ日手帳。社内にいる“手帳の使い手”に届くアイデアを盛り込みカタチにしていく、そこにお客様からの共感をいただけているんだと 思います。自分たちや社内のスタッフもいちユーザーとして「欲しい」もの、「面白いもの」へ目を光らせています。
――世の中に出る前に社内の“使い手”が立ちはだかるんですね。
齋藤:糸井事務所では、常にそのアイデアが「本当に面白いのか?」を問いながら企画を進めていきます。企画には難しい課題や、調整が必要なことがつきものですが、「本当に面白いのか?」を問いながら、強い“動機”を持って進めることが重要です。
田口:自信のあるアイデアでも「本当に面白いと思ってる?」の一言で、自信が崩れることがあります。その場合、“動機”が甘いんでしょうね。
――つまり、自分が「この手帳が欲しい」と思い切れていない?
齋藤:そうだと思います。ほぼ日手帳とは「自分の分身」のようなものなんです。予定やメモだけでなく、思った事や旅行先のレシートや美術館のチケットなど、自分が体験したことをそのまま記録しています。自分の分身ともなると、生半可な「欲しい」では“動機”も揺らぎますし、それではお客さまにもひびかないと思っています。
田口:糸井は「頭から血が出るまで考えろ」とよく言っています。「アイデアはいいんだけど、面白くない」、こんな評価が出ることも…アイデアには「いいね!」がついているのに、自問自答が足りず面白味が不足してしまった。メンタルダメージが大きい一言です。糸井事務所は、自由で緩さもある社風。しかし、“自問自答”や“考えること“にはとても厳しいです。
――「自分が本当に欲しいと思う」。つまり、“シーズ”に該当すると思います。さきほど、アンケートのお話も出ましたが、お客様が求める“ニーズ”はどのように盛り込んでいますか?
齋藤:1万通を越えるアンケートに加え、感想や意見が書かれたEメールも全て目を通しています。ほぼ日手帳をどのように使っているか、気になる使い方はないか。自由回答が多いのですが、時間をかけてきっちり読んでいます。
棟廣:ただし、アイデアの“動機”を問われて、「お客様が求めているから(=ニーズがある)」では我々はもちろん、お客様に届く手帳は作れません。自分たちを“使い手の一人”と意識することで、自然に“欲しいもの”も見えてくるのではないでしょうか。お客様の考える“面白い”を隅から隅まで目を通した上で、徹底的にアイデア、ひいては自分自身を客観的に見て、掘り下げる。このアクションはお客様の“欲しいもの”にも繋がると考えています。

“優秀さ”よりもたいせつなこと
――自分自身を客観的に見る。ユニークですが、とても難しい切り口ですね。
田口:普通の人が一所懸命にやることで出来ることはたくさんある。背伸びをして、アイデアを良く見せる必要はない。“何をしたいのか”をしっかり自覚することが大切。糸井事務所では“優秀”であることはあまり求められていません。
棟廣:採用募集で重視しているのが「一緒に働くイメージが持てるか」。肩書きやスキルではなく、その人がどういうことを“うれしい、面白い”と思っているのかも重要です。コンテンツや商品を作って行く中で、それぞれが“面白い”を感じて、「本当にやりたいと思うこと」に盛り込んでいきたい。それが私たちも入社を希望してくれる方もイメージができるかを大切にしているんです。
――お客様から共感を得るために制作しているのではなく、自分の本心を追求した結果、お客様が共感してくれる商品が生まれる。アイデアの共有はどのように行っているんですか?
棟廣:“井戸端”会議です(笑)。時間を決めて、資料を作って、会議室でじっくり…は少なめです。「あ、面白 い!」をその場で話し始め、気付いたらアイデアがまとまっていたことも多々。もちろん、仕様を決める際など、きっちりやらないといけない場合は会議室で じっくり話し合います。
齋藤:弊社には、資料をじっくり作るなら、考えたり、だれかと話しをする時間にあてたほうが良い、と考える雰囲気 があります。実際、パワーポイントで企画書を作ることはありません。クライアントがいる仕事ではありませんし、企画を話し合う時に誰かを説得する必要もありません。案を複数出す必要はないので、一本“本気”で考えたアイデアを出すことが求められます。
――メンバー間でセンスとか考え方とか、似てきたりしませんか?
齋藤:大事にしたいポイントや“動機”は似てきます。 例えば「ほぼ日手帳を若い人にも使ってもらいたい」と意見が出た場合、「若い人に何故使ってもらいたいか」の部分はそんなに話し合わなくても共有できたり します。「どうしたら使ってもらえるか」を具体的に話し合いながら“動機”が整理されていくような感じです。“動機”が似てくることは、メンバーが同じ方 向を向きながら、異なるセンスやアイデアを盛り込む“土壌”にもなっていると言えるかもしれません。
※ 後編に続きます
(撮影 :橋本 直己)