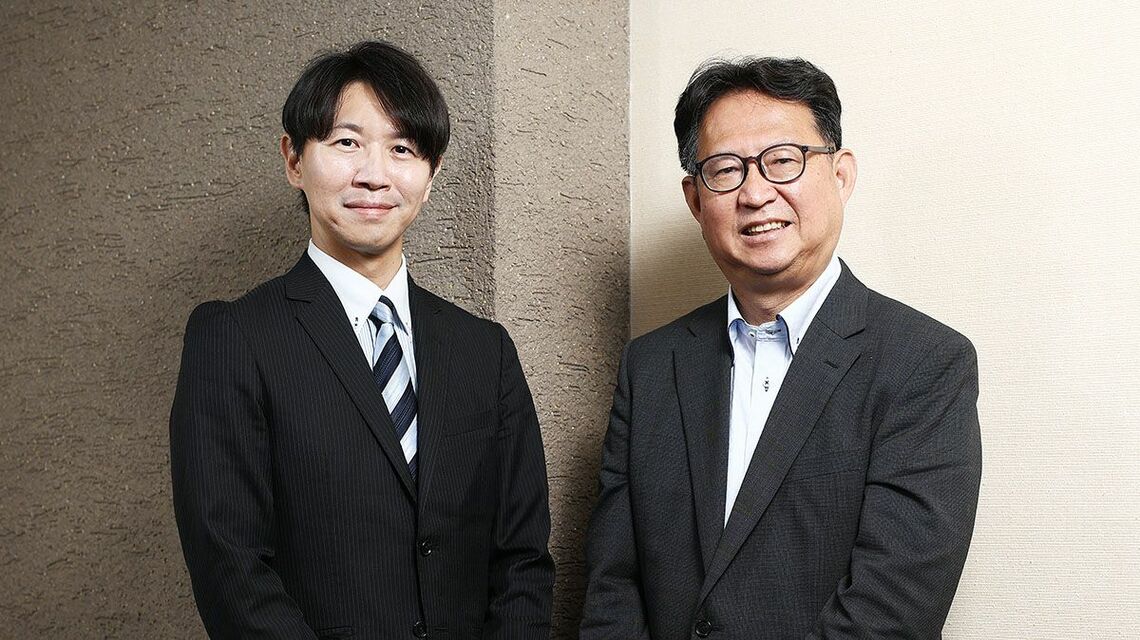疾患治療の選択肢、「行動経済学」に相関関係? 家族や医療従事者も理解したい「バイアス」とは
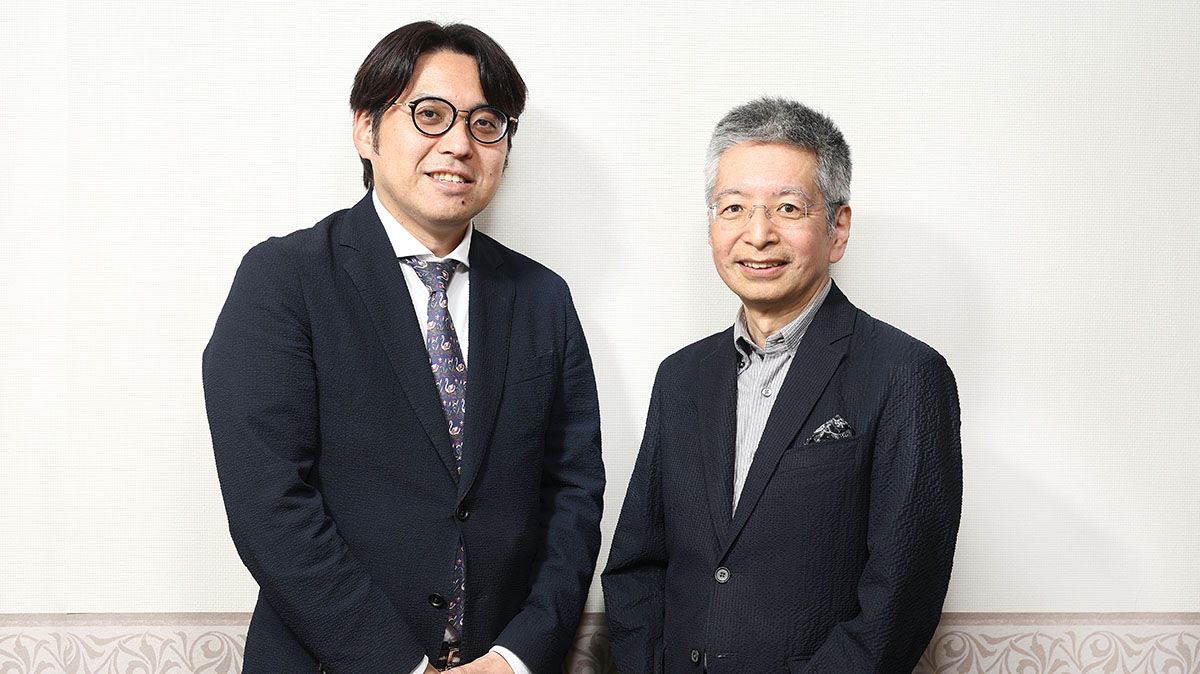
行動経済学は、ビジネスの場でどう活用されている?
――行動経済学とはどのような学問ですか。
大竹 一言で言えば、心理学を経済学に組み込んだ学問です。広く世に知られるようになったのは、行動経済学に関する内容が、2002年と17年の2回、ノーベル経済学賞を受賞したことです。そこから、行動経済学の考えが社会に普及しました。
行動経済学で代表的な「ナッジ」の例を挙げましょう。「ナッジ」とは、選択を禁じることも経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、表現の工夫でよい行動を促したり逆によくない行動を抑制したりする方法です。その1つに、望ましい選択肢を初期設定にする方法があります。
千葉市では17年度より、男性職員が育児休業を取得しない場合、人事が職員の上司から取得しない理由を聞き取ることにしました。部下が育児休業を取得すれば何も聞かれず、取得しないと聞き取りがあるため、取得が初期設定となります。その結果、16年度には12.6%だった男性職員の育休取得率が、19年度には92.3%に向上しました(※1)。
一方、ビジネスではこの手法が悪用されるケースもあります。「情報メールを受け取る」にあらかじめチェックが入っており、そのままにしておくと山のようにメールが届くというのは悪用例の1つです。
これは法改正で規制されましたが、ナッジは社会をよい方向にも悪い方向にも変えうる手法であることを覚えておいたほうがよいかもしれません。

大竹 文雄氏
大塚 私が行動経済学に出合ったのは、臨床現場でのアプローチに悩んでいた時でした。今でこそアトピー性皮膚炎の治療にはさまざまな選択肢が増えていますが、当時はステロイド外用薬の使用が主な治療法でした。1990年代に報道の影響でバッシングが始まり、ステロイドを忌避する傾向が出てきました。
「どうすればきちんと薬を塗ってくれるのだろうか」と心理学を勉強し始めたところ、行動経済学の存在を知りました。当時の医療分野では行動経済学の研究は進んでおらず、ステロイド忌避への対処が医療分野における活用の先駆けだったと思います。
脳内で覚えている情報が、重要なものとは限らない
――医療分野ではどのようなバイアスが生じやすいのでしょうか。
大竹 医療分野には2つの難しさがあります。1つは、一般的に治療薬を使った後、すぐに効果が出ない場合がある点です。そうなると患者さんとしては「結果的に自分にとって最良の方法だったとしても、すぐに効果が出ないなら今はやらなくていい」と感じてしまう。その結果、治療の忌避につながる可能性があります。
もう1つは、治療で確実に効果が出るわけではない点です。治療に100%はないので、医師は何があっても「確実に治る」とは言いません。一方、「絶対に治る」とうたっている適切ではない情報も世の中には存在します。自信を持って「治る」と言い切られると、一部の患者さんはその情報を信じてしまうのです。
大塚 これまでに私が診てきたアトピー性皮膚炎患者さんの中には、標準治療をしている期間に効果がなかなか出ないと医師に不信感を抱き、最終的に標準治療を忌避するという方がいらっしゃいます。
一度、患者さんが不信感を抱かれると、こちらから丁寧に説明しても認識を変えていただくことは難しいと感じています。私が説明すればするほど、信念が強固になる印象もあります。
また、「テレビで副作用があると聞いたから」という理由で標準治療を忌避するケースもあります。こちらは強固に不信感を抱く患者さんと比べると、ナッジが効きやすいです。
例えば患者さんからの説明をじっくり聞きつつ、「別のアトピー性皮膚炎患者さんは以前この治療でよくなった」と説明すると、受け入れられることが多いです。

大塚 篤司氏
大竹 まずは相手の好みや信念を認めてあげること、迷っている場合にはナッジで後押ししてあげることが大切です。私たちは覚えている情報や最近聞いた情報を重要だと錯覚し、その結果、正しい情報を入手することなく意思決定することがあります。
これは「利用可能性ヒューリスティック」と呼ばれていますが、「よく覚えているからそれが重要な情報である」とは限りません。標準治療を忌避する患者さんの一部で、この影響を受けている可能性があります。
大塚先生が、医学的な知識よりも別の患者さんの例を使って説明されるのは、利用可能性ヒューリスティックをうまく使われていると思います。そのうえで、「今はいろいろな治療の選択肢がある」と伝えるのがよいのではないでしょうか。
効果が高いのは、利益よりも損失を強調するメッセージ
――合理的な意思決定に影響を与えるバイアスに、患者や患者のご家族、そして医療従事者はどのように向き合えばいいのでしょうか。
大竹 ナッジをうまく活用したいところです。以前、厚生労働省は中高年男性に対して、風疹(ふうしん)の抗体検査と予防接種の無料クーポンを配布していました。ですが、受診率が上がりませんでした。
そこで、チラシのメッセージを「未来の子どもたちを守る」から「あなたがきっかけで、妊婦さんが風疹に感染すると赤ちゃんが障害を持って生まれる可能性があります」へ変更したところ、抗体検査の受診率が向上しました(※2)。
まず、中高年男性の多くは風疹が胎児の健康に悪影響があるという知識を持たないので、医学的情報を提供することが重要です。そのうえで、人は利得より損失の回避を重視するという「損失回避バイアス」が働きます。医学知識を盛り込みつつ、損失を防ぐという利他的メッセージを伝えるチラシに変更したことで男性の行動が変わったのです。
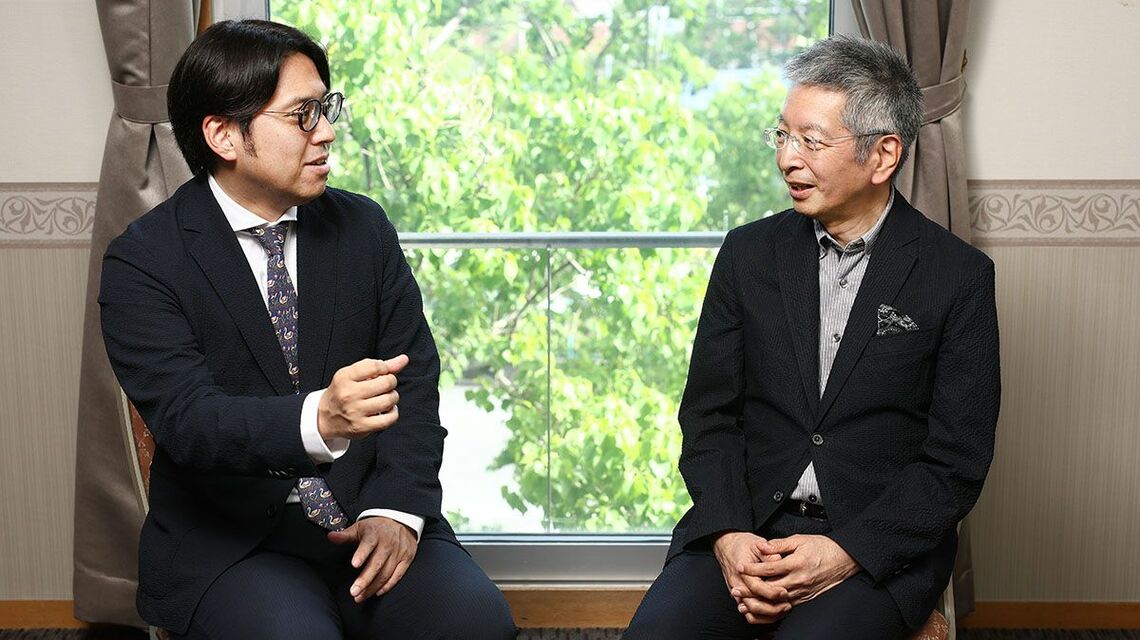
大塚 身近な情報に引っ張られる性質を、ナッジに使えるとよいですよね。アトピー性皮膚炎患者さんの中には、これまで続けてきた治療を変えられない方も多くいらっしゃいます。
今までの治療が効かなかったとしても、ご自分が治療にかけてきたお金や時間というコストをもったいなく感じてしまい、これまでの治療をやめられないという「サンクコストバイアス」が発生している場合があります。
実は2018年以降、アトピー性皮膚炎には新しい治療の選択肢が増え、よりよい状態の肌を目指せるようになってきました。人々の行動を変えるには、技術や発明は重要だと思います。実際に従来の治療法にはない注射剤や錠剤の登場を知り、これまで皮膚科に来院されなかった患者さんも来院されるようになりました。
正しい知識を持つことは、正しい意思決定につながります。身近な人が「今はいろいろな治療法がある」と伝えてあげれば、患者さんも行動を変えやすくなるのではないでしょうか。
大竹 身近な人からの情報は重要です。先ほどの風疹抗体検査の受診促進キャンペーンでは、電車内に動画広告を打ちました。その結果、本人ではなく妻が動画を見て「あなたも見て」と勧めたことで、受診率向上につながったのではないかという分析を進めています。
大塚 ご家族から伝えるときに意識してほしいのは、怒らないことです。患者さんのことを思うがゆえに、「なぜ標準治療や新しい治療をしないのか」と怒ってしまう気持ちもわかります。
しかし、怒っても何も変わりませんし、患者さんご自身が「周りはこのつらさをわかってくれない」と心を閉ざしてしまうかもしれません。
大竹 確かにご家族の気持ちもわかります。しかし、バイアスは患者さんだけが持つものではありません。患者さんのご家族や医療従事者を含め誰でも、バイアスを持った意思決定をしているのです。
誰でも不合理な意思決定をする可能性があると理解していれば、自分にもバイアスがあり、患者さんがバイアスを持った意思決定をするのは自然なことだと考えられるのではないでしょうか。
出所:千葉市:千葉市職員の子育て支援計画(第3期特定事業主行動計画)実施結果報告 2020年11月
※2
出所:Hiroki Kato, Shusaku Sasaki, Fumio Ohtake: “Adding nudge-based reminders to financial incentives for promoting antibody testing and vaccination to prevent the spread of rubella” Journal of Behavioral and Experimental Economics Volume 113, December 2024
MAT-JP-2504454-1.0-08/2025